グループホームの看護師や介護士の人員配置基準とは?スタッフ管理や運営効率の改善方法も紹介
2025.01.28
2025.05.26
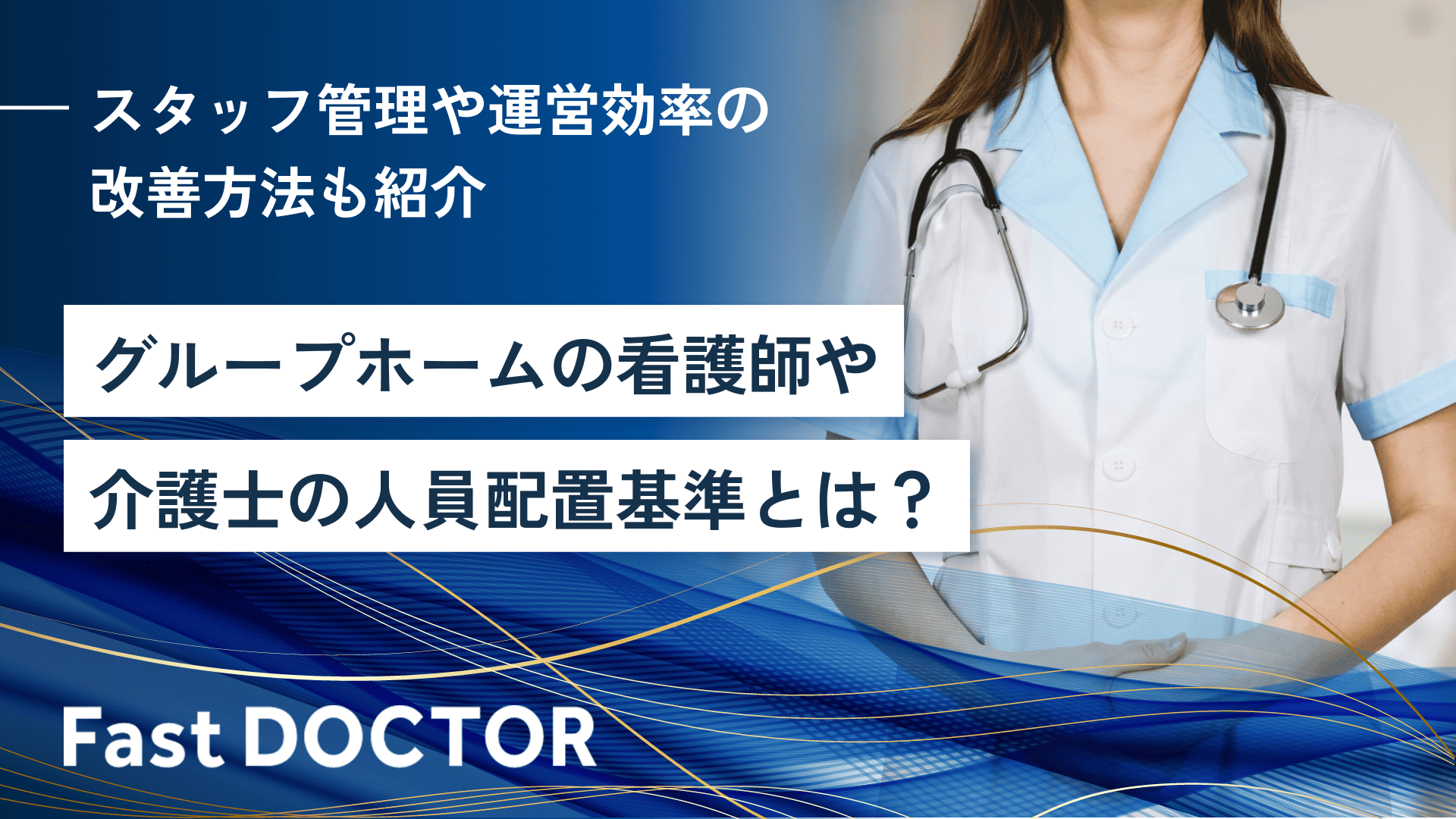
高齢化が進む昨今、グループホームの運営に関わっているまたは興味を持っており、看護師や介護士の人員配置基準が知りたいと思っている方もいるのではないでしょうか。
特に、医療ケアを行っていないグループホームでは、看護師の必要性や配置基準が気になるところでしょう。
そこで本記事では、グループホームの人員配置基準やグループホーム運営の課題、運営効率改善方法について解説します。
人員配置基準やコストなどを考慮したうえで効率的に運営していきたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

グループホームの人員配置基準とは?

グループホームでは、厚生労働省によって定められた人員配置基準を守る必要があり、下記4つの職種の人員配置基準が設けられています。
- 介護士
- 管理者
- 代表者
- 計画作成担当者
それぞれどのような人員配置基準になっているのか解説します。
介護士の人員配置基準
介護士の人員配置基準は、以下の通りです。
- 日中帯は利用者3人に対して1人
- 夜間はユニットごとに1人
日中帯は利用者3人に対して介護士1人となっていますが、これは常に3:1にしなければならないという意味ではありません。
介護職員の働いている合計時間が、利用者の総数に対して3:1になればよいという意味なので、時間帯によっては介護職員が少なくなる場合があります。
また、夜間については1ユニットの人数に関わらず1人となっています。
ユニットの人数が少なくても、複数のユニットを掛け持ちすることはできません。加えて介護職員が複数人いる場合は、常勤勤務の人が1人以上いなければいけません。
これは1人でも常勤の人がいれば、他はパートやアルバイトでも問題ないということになります。
参照:厚生労働省「認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)」
参照:厚生労働省「高齢者施設・障害者施設等における医療」
管理者の人員配置基準
管理者は、1つのユニットに対して1人常勤で配置されなければいけません。
管理者は、主に人事や労務、経営管理などの管理業務を実施します。現場に入ることもあるため、介護の知識や経験が必要になります。
また、管理者になるためには、下記の条件を満たしている必要があります。
- 3年以上認知症の介護従事経験がある
- 厚生労働大臣が定める研修を修了している
なお、管理業務に支障をきたさなければ、他職種との掛け持ちが可能です。そのため、コストの関係上、管理者は掛け持ちで行っている場合が多い傾向にあります。
参照:厚生労働省「認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)」
代表者の人員配置基準
代表者は、グループホーム全体を管理するために必要不可欠な存在です。
代表者になるためには、下記要件を満たす必要があります。
- 介護施設で認知症高齢者の介護に従事していた または 保険や医療、福祉サービスを提供する事業所の経営に携わった経験がある
- 厚生労働省の定めた「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了している
グループ全体を管理するため、介護に関する知識や経験はもちろん、経営についての知見が必要となるポジションです。
加えて、制度の変更や介護業界の動向について常に情報をアップデートし、迅速に対応していくことも求められます。
参照:厚生労働省「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の報酬・基準について」
計画作成担当者の人員配置基準
計画作成担当者は、ユニットごとに1人配置されるよう定められています。
ユニットが複数ある場合は、ユニットの数だけ計画作成担当者が必要です。
また、計画作成担当者のうち最低1人は介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を保有していなければいけません。
計画作成担当者は、下記要件を満たしている必要があります。
- 認知症介護実践者研修を修了している
- 専らその職務に従事するもの
計画作成担当者は、利用者のケアプランの作成を行う重要な職種です。ひとりひとりに合ったプランを作成するため、利用者の心と体の状態や、家族関係、生活環境などを把握します。家族や利用者の声を聞く傾聴力と、変化を見逃さない観察力が必要とされます。
参照:厚生労働省「認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)」
グループホームの人員配置において看護師は必要?

グループホームは医療ケアを行っていないため、看護師の配置は義務付けられていません。
しかし、グループホームに看護師を配置する必要はあると言えます。
なぜなら、利用者の高齢化が進んでおり、持病や急な体調の変化に対する医療サポートの必要性が高まっているからです。
グループホームでの看護師の仕事は、利用者が自立した生活を送れるように健康管理をする業務です。
高齢者はいつ体調が変化するか分かりません。加えて利用者の多くは認知症の方である場合が多いため、体調の変化に気づきにくく、体の不調を伝えるのが難しいです。
そういった利用者の不調の際に、看護師であれば小さな変化に気づき、重症化を防止できる可能性があります。
また、看護師がいることで、医療体制が整っている点をアピールでき、利用者の家族への印象も良くなります。利用者の家族に好印象を抱いてもらえると退所を防げるだけでなく、入居希望者が増加する可能性も考えられるでしょう。
医療ケアを行っていないグループホームでも、利用者の高齢化が進んでいる限り急変は避けられません。万が一に備えて迅速に正しい対応ができるよう、看護師を配置しておく必要があります。
看護師は配置した方が良いものの、配置を義務付けられていない職種のため、勤務形態も定められていません。そのため常勤で配置するグループホームもあれば、非常勤や夜勤のみで配置するグループホームもあります。看護師の必要性やコストなどを考慮して、看護師を配置するか検討するといいでしょう。
グループホーム運営における課題

高齢化が進んでいる日本では、グループホームの需要は高まっています。しかし、グループホームを運営するには、下記3つの課題があります。
- 人員配置の条件の厳しさ
- 看護師や医師の必要性
- 夜間対応の難易度の高さ
それぞれ詳しく解説します。
参照:総務省「統計からみた我が国の高齢者 」
人員配置の条件の厳しさ
グループホーム運営の課題のひとつとして、人員配置の厳しさが挙げられます。
前述した通りグループホームには、介護士と管理者、代表者、計画作成担当者の人員配置基準が設けられています。さらに職種によっては、経験年数や資格、研修が必要です。
もし新規採用が難しく、働いているスタッフのなかで対応する場合は、研修を受けさせる時間などを確保しなければいけません。
新たに人員を確保する場合は、条件に合った人を一から見つけなければいけません。人材不足だと言われているなか、条件も満たしつつ、グループホームに合う人を見つけるのはなかなか難しいでしょう。
また介護士は常勤が1人いれば、他の介護士はパートやアルバイトでも良いという配置条件となっていますが、実際は常勤のスタッフの責任が重くなり常勤の介護士の離職につながりかねません。
とはいえ多くの常勤の介護士を雇うのは、人件費がかかり経営が難しくなってしまう場合もあるでしょう。予算を考慮しつつ、人員配置基準やスタッフの負担なども考えなければいけない点が、グループホームの運営を厳しくさせている要因だと考えられます。
看護師や医師の必要性
看護師や医師が必要になる点も、グループホーム運営の課題です。
グループホームの本来の目的は、認知症の方が自立した生活を送れるようにサポートすることです。そのため、医療ケアを実施していないグループホームが多い傾向にあります。
しかし、入居者の高齢化が進み、持病が重症化したり急に体調が悪くなったりするリスクが高くなっていることから医療ケアが必要になってきています。そうなると、看護師や医師など医療行為が行えるスタッフが必要です。
しかし看護師や医師などを配置するとなると、それだけ人件費や必要な備品費などコストがかかります。
看護師を配置していたり、医療提供体制が整っていたりする介護施設には、医療連携体制加算がつくようになりましたが、これだけでは補えないのが現状です。
夜間対応の難易度の高さ
夜間対応の難易度の高さも、グループホーム運営の課題になります。
グループホームは、認知症の方が生活をしている場なので24時間体制となります。
そのため、夜間もスタッフを配置しなければいけません。
夜間は日中帯に比べて、活動をしていない方が多いのでスタッフ数が少なくなります。
しかし、利用者が夜間に重症化する可能性はゼロではありません。
急変したときに、スタッフの数が限られていると対応が遅れてしまいます。それだけでなく、スタッフの精神的、身体的な負担も大きくなります。
スタッフの負担軽減やサービスの質を高めるために、夜勤の人員を増やそうとしても、夜勤手当などのコスト面やスタッフの獲得が難しいという問題があります。
このようにグループホームを運営するときは、夜間対応の難しさと向き合わなければいけません。
グループホームの運営課題や運営効率の改善方法

グループホーム運営の課題について解説しましたが、課題を改善しつつ効率よく運用するためにはどうしていけばいいのでしょうか。
グループホームの運営効率を改善する方法として、下記2つが挙げられます。
- 介護職員にできることを増やす
- オンコールサービスの利用という選択肢
それぞれ詳しく解説します。
介護職員にできることを増やす
グループホームの運営効率を改善する方法の1つ目は、介護職員にできる業務を増やす方法です。
高齢化が進み医療が必要な利用者が増えていくなかで、看護師など医療従事者を配置できるのが一番ですが、採用コストが限られており実現できないグループホームもあります。
そういった場合は、介護職員ができることを増やしていくといいでしょう。
介護職員にできることを増やすためには、教育制度を整える必要があります。急変時の対応や介護職員でもできる医療ケア方法など、医療に関する知識を身に着けられるようにしましょう。
近年では、介護士でも研修を受ければ、痰の吸引など一部医療行為ができるようになりました。そのような研修受講を推奨していくのも1つの方法です。
また、特定処遇改善加算という制度を活用してみるのも、職員のキャリアアップを促すのに役立ちます。
しかし、介護士が実施できる医療行為は非常に限られています。医療行為は医療資格者が行い、介護職員には介護は介護職員が行うといったように、正しく役割分担をしましょう。
参照:厚生労働省「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令案」
参照:厚生労働省「介護職員の処遇改善に係る加算の概要」
オンコールサービスの利用という選択肢
オンコールサービスを利用するのも、グループホームの運営効率化につながります。
オンコールサービスとは、夜間や休日に看護師や医師が対応する必要がある、オンコールを代行するサービスです。
オンコールサービスを利用すれば、現場で働く介護施設の看護師の負担やプレッシャーの軽減につながります。
人員確保やコスト面で厳しい状況にある夜間対応にはオンコールサービスを利用することでも運営効率の改善が期待できるでしょう。
グループホームに看護師を配置して効率のよい運営を

グループホームの人員配置基準や、運営の課題点、運営効率の改善方法について解説しました。
グループホームには、介護士、管理者、代表者、計画作成担当者の人員配置基準があり、運営するためには基準を満たさなければいけません。
また、看護師の配置は義務付けられていませんが、利用者の高齢化が進んでいる点から看護師を配置しておいたほうがいいと言えます。
しかし、コスト面から看護師などの医療従事者を採用することが難しいグループホームもあるでしょう。そんなときは、介護士の対応可能な業務を増やしたりオンコールサービスを利用したりすることで改善が期待できます。
適切な人員配置は、グループホームでの質の高いサービス提供の基礎を作ります。看護師の配置によっては、さらに安心感を提供し、利用者及びその家族からの信頼を得ることができるでしょう。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。


関連記事RELATED







