看護師のストレスマネジメント方法とは?考えられる課題と組織で取り組む職場環境の改善策を解説
2025.01.29
2025.05.26
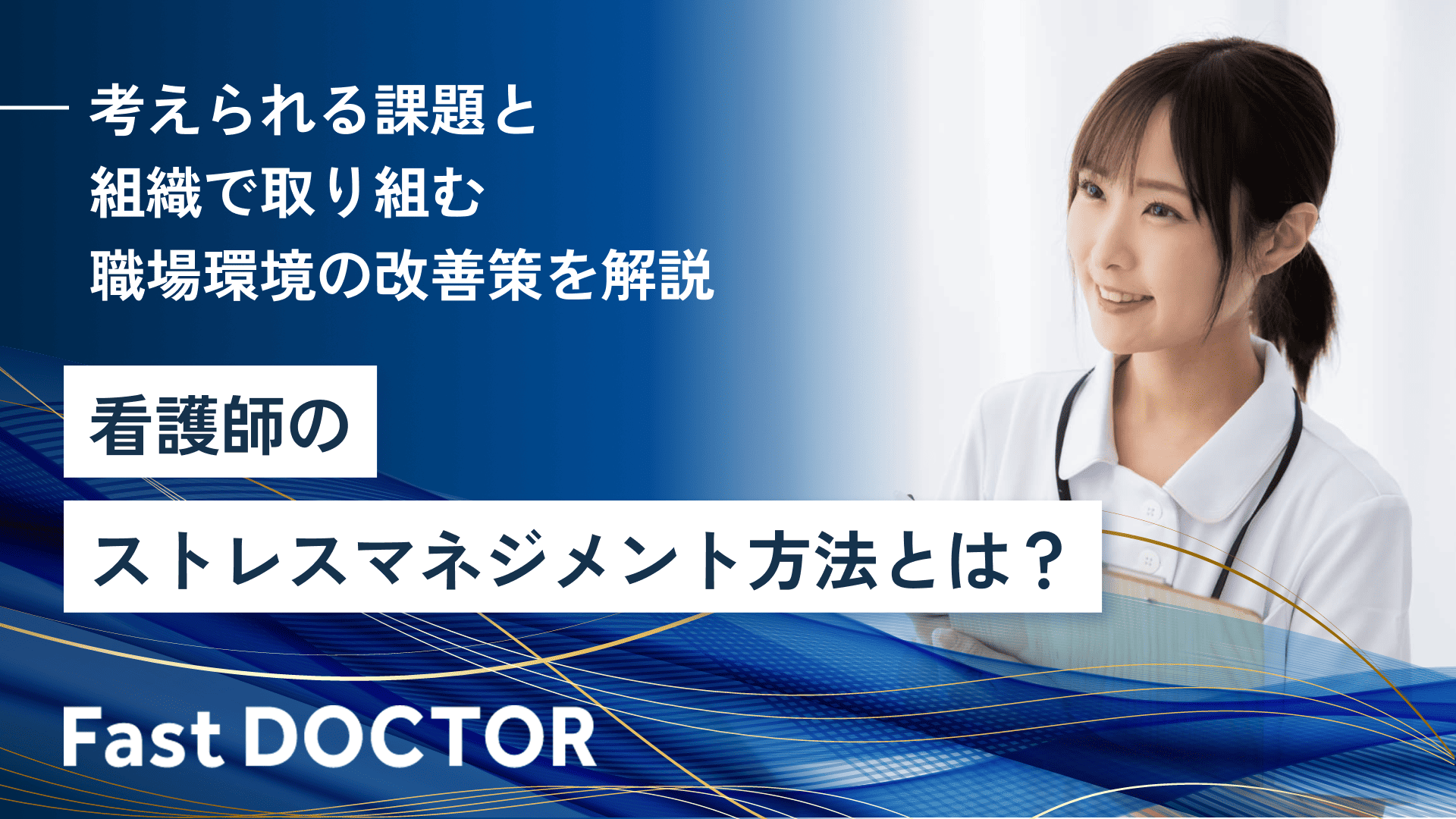
看護師は医療現場に必要不可欠な存在ですが、労働環境からストレスがたまりやすく離職率が高い職種です。
離職を防ぐために、看護師のストレスを軽減するための方法を知りたいと思っている医療機関の管理者やリーダーは多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、看護師のストレスの原因や組織で看護師のストレスマネジメントをする方法、ストレスマネジメントにおける注意点について解説します。
看護師のストレスを少しでも減らして職場環境を改善していきたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
参照:日本看護協会「2022 年 病院看護実態調査」
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

看護師が働くなかで抱えやすいストレスの原因とは

看護師の業務内容は、負担が大きく仕事量のコントロールがしにくいという特徴があり、ストレスがたまりやすい傾向にあります。
実際に、2022年度の「精神障害の請求件数の多い職種」で第2位になっています。
では、このようにストレスを抱えやすくなっている原因は何なのでしょうか。ストレスを抱え込んでしまう原因には、下記4つが考えられます。
- 人間関係
- 前残業や後残業
- 給料への不満
- 不規則な勤務形態
それぞれ詳しく解説します。
参照:日本看護協会「メンタルヘルスケア」
厚生労働省「精神障害に関する事案の労災補償状況」
人間関係
ストレスの原因として、人間関係が挙げられます。
看護師は、看護師同士はもちろん医師などの他の医療従事者、患者、その家族など様々な人達と接する機会が多い職種です。
看護師同士であれば、先輩に理不尽に怒られたり後輩への指導がうまくいかなかったりすることで、精神的負担が積み重なっていきます。
医師をはじめとする他の医療従事者との意見の食い違いも、ストレスの元になるでしょう。
また、患者からは感謝されることもありますが、罵声を浴びたり悪口を言われることも少なくありません。
このように、看護師は多くの人と関わることによって、ストレスをためこんでしまいます。
参照:日本看護協会「メンタルヘルスケア」
前残業や後残業
前残業や後残業の多さも、ストレスを抱え込む原因です。
前残業とは、就業開始時刻よりも早く出勤して仕事をすることをいい、看護師特有の文化と言えます。
実際に、日本看護協会が行った時間外労働の調査によると、回答者の8割以上が前残業を実施しているという結果が出ています。
また、前残業だけでなく通常の業務後に残業をすることも多い傾向にあるようです。
このように、時間外労働が多くなってしまうのは、やらなければいけない業務に加えてイレギュラーな業務にも対応しなければいけないからでしょう。
常に緊張感があるなかで長時間労働をすることになるので、心身ともに負担が大きくなりストレスにつながります。
参照:日本看護協会「時間外勤務、夜勤・交代制勤務等緊急実態調査」
給料への不満
ストレスを抱え込む原因として、給料に不満があると考えられます。
看護師の給料は高いというイメージがありますが、実際は責務に対して見合っていないと感じる人もいます。
看護師は、人の命に関わる現場で働いている方がほとんどで、特に救急やICUなどでは1つのミスで重大な事態を引き起こしかねません。
そういった緊張感と責任のある仕事のため、身体的にも精神的にも疲れがたまりやすいのが特徴です。
それに加え、残業をしても残業代の申請ができなかったり、一部しか手当がつかなかったりすることも少なくありません。
このように、仕事内容に対して給料が見合ってないと不満を持つ人がいるのが現状です。
参照:日本看護協会「時間外勤務、夜勤・交代制勤務等緊急実態調査」
日本看護協会「日本の医療を救え」
不規則な勤務形態
不規則な勤務形態も、ストレスの原因となります。
看護師は夜勤が必須な医療機関が多く、不規則な勤務形態になりやすい職種です。医療機関によって二交代制と三交代制に分かれますが、どちらの場合も生活リズムの乱れにつながり、負担は大きくなります。
夜勤と日勤が混合したシフトで、勤務間の時間間隔が短いと十分な休息がとれず疲労が回復しません。特に夜勤後は日中帯に眠ることになるので、睡眠の質が下がり日勤後よりも疲労回復に時間がかかります。
しかし、看護師は残業などで勤務間の時間間隔が短くなる可能性があります。不規則な勤務形態によって疲労が回復しきれない状態が続き、ストレスがたまっていきます。
参照:日本看護協会「交代制勤務看護師の勤務間インターバルと疲労回復に関する研究」
看護師に対して組織でストレスマネジメントする方法

仕事内容や勤務形態から、看護師はストレスを抱えやすい職種だということがわかります。
そのため、組織として看護師のストレスマネジメントをすることが大切です。
では、看護師に対するストレスマネジメントにはどのような方法があるのでしょうか。
主なものとして、下記3つが挙げられます。
- ストレスを吐き出す窓口や機会を設ける
- セルフマネジメント能力を高める
- 職場環境の改善により負担をなるべく減らす
それぞれの方法について、解説します。
ストレスを吐き出す窓口や機会を設ける
看護師のストレスマネジメントをする方法の1つが、ストレスを吐き出す窓口や機会を設けることです。
ストレスに対して、家族や友人、同僚などに話すことによって、発散することができます。
また、誰かに話すと気持ちや頭の中が整理でき、落ち着いて考えられるようになるでしょう。
そのため、組織としてストレスを吐き出す窓口や機会を設けることは大切です。
しかし上司や同僚に相談できる環境があったとしても、忙しくて相談するのをためらってしまうときもあります。
そんなときのために、専用の相談窓口を設けるといいでしょう。合わせて、公的機関の相談窓口の案内を公開しておくのもストレスマネジメントにつながります。
相談窓口を開設するときは、若手や中堅だけでなく師長や管理職など役職がついている人も利用できる場にする必要があります。
看護師がストレスによって休職や離職に追い込まれる前に、相談できる環境を整えるようにしましょう。
参照:日本看護協会「個人での対応(セルフケア)」
セルフマネジメント能力を高める
ストレスマネジメントをするためには、セルフマネジメント能力を高めることも大切です。
組織に相談窓口があっても、利用するのに抵抗がある人もいるでしょう。
そういったときでもストレスを発散できるよう、セルフマネジメント能力を高めるようにしましょう。
セルフマネジメント能力を高めるために、下記2つを意識してみてください。
- キャリアプランの見直しやキャリアアップの道を考える
- 組織からキャリアパスを提示する
それぞれについて解説します。
キャリアプランの見直しやキャリアアップの道を考える
キャリアプランの見直しやキャリアアップの道を考えることが、セルフマネジメントにつながります。
看護師として働いていくと、自分の理想とする看護師像と現実のギャップを感じて今後のキャリアについて悩み、働く意欲が低下してしまうことがあります。
そうなったときは一度キャリアプランを見直してみてください。今の状況にあったキャリアを考えることで、目標が見つかり道筋をたてやすくなるでしょう。
参照: 吉井忍, 八塚美樹「看護職員のセルフマネジメントの構造」
組織からキャリアパスを提示する
組織からキャリアパスを提示するのも、看護師のセルフマネジメント力を向上させるのに大切です。
看護師全員がキャリアプランを立てているわけではありません。また、前述したように働いている途中でキャリアプランを見失ってしまう人もいます。
このような人達に、キャリアパスを提示して道を作ることも組織の役割の1つです。
また、組織の制度改革などを行うのも看護師個々のセルフマネジメントを促進する方法の1つです。
看護師のセルフマネジメント能力を高めるために、どのような制度や環境、キャリアパスがあるといいか検討するといいでしょう。
参照: 吉井忍, 八塚美樹「看護職員のセルフマネジメントの構造」
職場環境の改善により負担をなるべく減らす
職場環境の改善による看護師の負担をなるべく減らすことも、ストレスマネジメントにつながります。
前述した通り、看護師は人間関係や長時間労働、不規則な勤務形態などによってストレスがたまりやすい職種です。
看護師のストレスを少しでも減らすために、職場環境の改善を行い負担を少しでも減らせるようにしていく必要があります。
新たに人員を採用する方法もありますが、時間とコストがかかります。
そんなときは、オンコール代行や往診代行サービスの活用を検討してみてください。看護師の働きやすい環境を整えることに繋がるのはもちろん、患者さんに対しても安心と信頼を提供できる環境が整います。
看護師のストレスマネジメントにおける注意点

看護師のストレスマネジメントをするときは、下記2点に注意してください。
- メンタルヘルスケアを怠らない
- 労働環境を正しく管理する
それぞれ、詳しく解説していきます。
メンタルヘルスケアを怠らない
ストレスマネジメントをするときは、メンタルヘルスケアを怠らないようにしましょう。
看護師は感情労働の職業と言われており、心身ともに大きなストレスがかかります。
そのため、心の健康を保つメンタルヘルスケアはとても重要です。
精神的に不安定になっている看護師を早期発見することや治療を勧めること、メンタルヘルス不調にならないような取り組みをすることなどがメンタルヘルスケアとして挙げられます。
看護師のストレスを少しでも減らすために、メンタルヘルスケアは必要不可欠です。
参照:厚生労働省「ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について」
労働環境を正しく管理する
看護師の労働環境を正しく管理できないと、ストレスマネジメントにはならないので注意が必要です。
看護師の労働環境は過酷で、過去には過労死が認められたケースもあります。
そのため、労働環境を正しく管理することはストレスマネジメントにおいて必須と言えます。
有給休暇の取得促進や残業時間を正確に管理する、勤務終了から次の勤務開始までの時間を十分に取るなど、負担が蓄積されないように管理するようにしましょう。
参照:日本看護協会「ナースのかえるプロジェクト」
ストレスマネジメントをして職場環境の改善を

看護師が抱えやすいストレスの原因や、組織でストレスマネジメントをする方法、ストレスマネジメントの注意点について解説しました。
看護師は人間関係や労働時間、給料、勤務形態によってストレスを抱えやすい職種です。そのため、心身ともに負担が大きくなり離職や休職につながります。
そうならないために、組織としてストレスマネジメントをする必要があります。少しでもストレスを減らすため、相談窓口を設けたりキャリアパスを提示したりするといいでしょう。
組織におけるストレスマネジメントの取り組みは、看護師の職場満足度を高め、結果的に患者へのケアの質を向上させることにつながります。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。


関連記事RELATED







