チーム医療における課題とは?課題の解決策やチーム医療の効率向上のための戦略を紹介
2025.01.30
2025.05.26
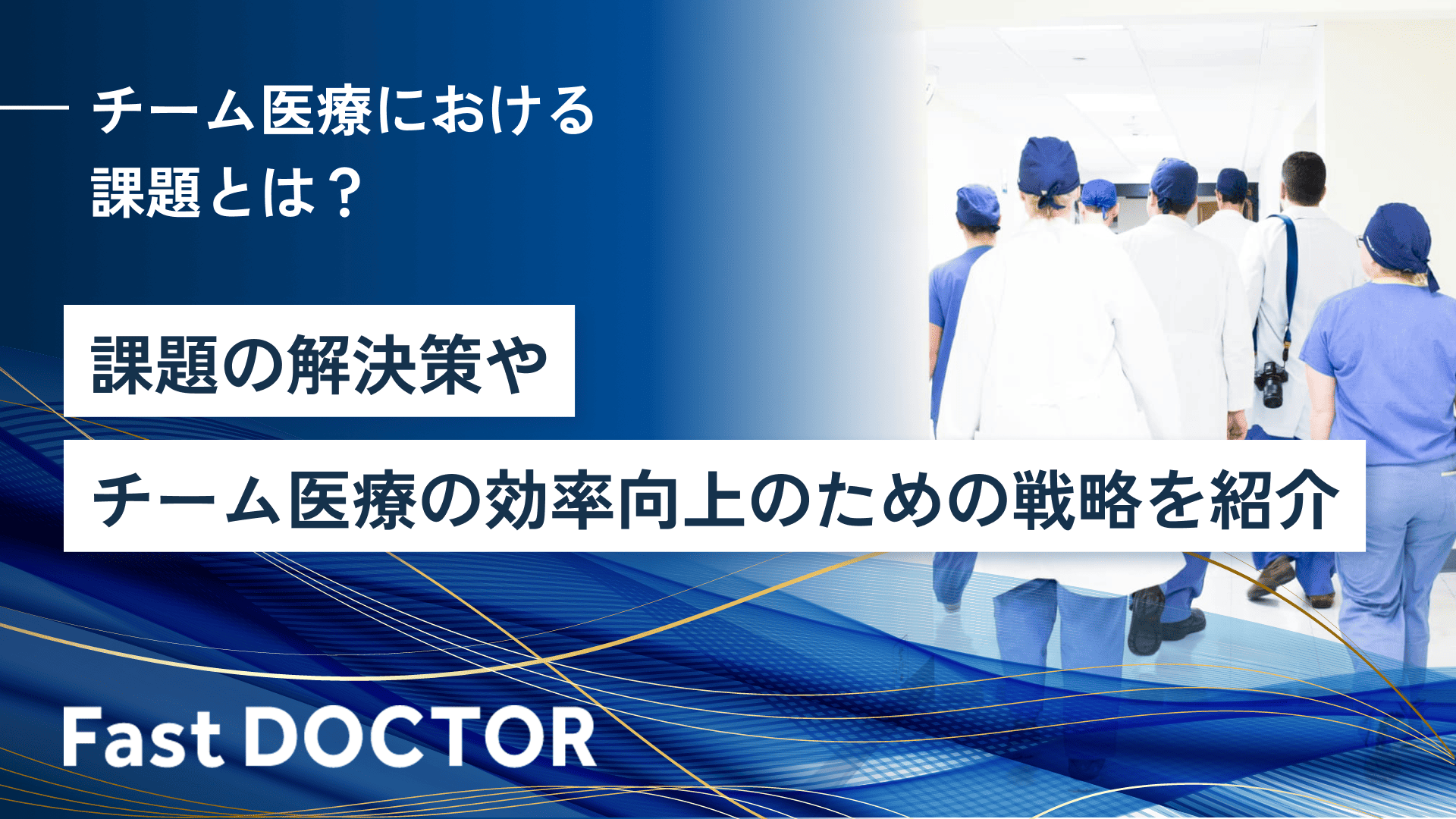
高齢化や医療の高度化が進んでいくなかで、チーム医療は必要不可欠となってきます。そのため、チーム医療の推進を検討している管理職の方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、チーム医療の課題や重要性、チーム医療の効率性を向上させる方法について解説します。
効率よく質の高いチーム医療を提供したい方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

チーム医療って何?関わっている職種とは

チーム医療とは、1人の患者のために、複数の医療従事者が連携して治療やケアにあたることです。
さまざまな医療従事者が対応することで、高い専門性を発揮でき、質の高い医療の提供につながります。
患者の状態や目標によって、チーム医療に関わる職種と役割は異なりますが、下記表のような職種がチーム医療に関わっています。
| 職種 | 役割 |
| 医師 | ・診断と治療方針を決定し、チームへ指示をする ・治療の実施 ・患者や家族への説明 |
| 看護師 | ・診察、治療に関連する検査や処置 ・患者や家族への補足説明 ・患者、家族へのケア |
| 薬剤師 | ・調剤 ・患者に合わせた服薬指導 ・医師の処方に対する確認作業 |
| 理学療法士 | ・基本動作(立つ、歩く、座るなど)の回復や維持のためのリハビリテーション |
| 作業療法士 | ・日常生活動作(食事、排泄、入浴など)に関するリハビリテーション ・高次機能障害や発達障害などに対するリハビリテーション |
| 言語聴覚士 | ・ことばによるコミュニケーション ・摂食・嚥下訓練 |
| 臨床検査技師 | ・生体検査(心電図、肺活量、脳波、超音波検査など) ・検体検査(血液、尿、細胞などの検体) |
| 臨床工学技士 | ・生命維持装置(人工呼吸器、血液透析装置、人工心肺装置など)の操作 ・医療機器の点検、管理 |
| 診療放射線技師 | ・検査の実施(レントゲン検査やCT検査) ・装置の管理 |
| 臨床心理士 | ・患者や家族への心理的援助 |
| 医療ソーシャルワーカー | ・病院の総合相談窓口 ・心理的・社会的問題解決のサポート ・退院サポート ・社会復帰の援助 ・受診・受療援助 ・経済的問題の解決、調整援助 |
| ケアマネージャー(介護支援専門員) | ・ケアプラン作成 ・利用者とサービス提供事業者の連絡調整 |
| 管理栄養士 | ・栄養管理 ・栄養指導 |
参照:全日本病院協会「チーム医療」
参照:チーム医療推進協議会「チーム医療とは」
チーム医療の実現にあたって抱えやすい課題

チーム医療を実現するにあたって抱えやすい課題が3つあります。
- 他職種の専門性に対する理解
- チーム医療による効果が実証しにくく導入しにくい
- 専門職の人員確保
それぞれどのような課題なのか、解説します。
他職種の専門性に対する理解
チーム医療が抱えやすい課題の1つとして、他職種の専門性に対する理解ができていないことが挙げられます。
チーム医療は、1人の患者に対して複数の医療従事者が関与しています。医療従事者といっても、それぞれの対応する分野が異なるため、自分の分野に固執した考えが生まれてしまうことは少なくありません。
それぞれが固執した考えを持ってしまうと、意見がぶつかり同じ目標に向かっていくのが難しくなってしまいます。
また、チーム医療には上下関係や主従関係などは存在しませんが、経験年数の差などによって、自然と上下関係が生まれてしまうことがあります。
そうすると、意見を言い出せなかったり能力不足を感じたりしてしまい、チーム医療本来の目的が果たせなくなってしまうかもしれません。
患者のことを第一に考えて治療やケアをしていくためには、それぞれの職種の専門性を理解し合って、柔軟に対応していくことが重要となります。
参照:吾妻知美,神谷美紀子,岡崎美晴,遠藤 圭子「チーム医療を実践している看護師が感じる連携・協働の困難」
参照:厚生労働省「チーム医療の推進について」
チーム医療による効果が実証しにくく導入しにくい
チーム医療による効果が実証しにくく導入しにくい点も、チーム医療が抱える課題です。
日本では、チーム医療の成果や評価を実施している医療機関が少ないです。そのため、チーム医療の有効性や具体的な取り組みなどのデータが十分に得られていません。
チーム医療をすることで効果が得られるのか、どういった方法で導入すればいいのかはっきりしていない状況だと、医療機関は一歩を踏み出せません。
なぜなら、チーム医療をするためには、人員確保やスタッフ教育などコストや手間がかかるからです。
余裕がない状態で、確かな効果が保証されていないチーム医療を実施するのはリスクが高いと言えます。
チーム医療の導入を進めるためには、チーム医療の効果や具体的な取組内容が必要となります。効果を実証するために、チーム医療に対する調査を進めていく必要があるでしょう。
参照:チーム医療推進協議会「チーム医療の課題」
専門職の人員確保
チーム医療の実現にあたって抱えやすい課題の3つ目は、専門職の人員確保です。
チーム医療には、さまざまな医療従事者が必要です。そのため、チーム医療を実施するためには、必要な専門職を確保しなければいけません。
しかし、医療・福祉業界は人材が不足しています。そんななか、専門職の人員を確保することは簡単ではありません。
加えて、臨床経験や資格などの条件を設けると、難易度がさらに上がるでしょう。
また、人員を確保できたとしても、教育体制や労働環境が整っていないと離職につながります。採用するだけではなく、長く勤めてもらうように変化させることも必要となります。
このように、チーム医療を実現するためには人員確保の難しさを乗り越えなければいけません。
参照:チーム医療推進協議会「チーム医療の課題」
参照:厚生労働省「社会保障を支える人材の確保」
課題を抱えるチーム医療の重要性とその理由

チーム医療はさまざまな課題を抱えていますが、これからの時代において、重要性は非常に高いと言えます。
チーム医療が重要となる理由には、下記2つが挙げられます。
- 高度化する医療を個別性をもって提供するため
- 地域で生活していく患者の増加
それぞれ詳しく解説します。
高度化する医療を個別性をもって提供するため
チーム医療が重要となってくるのは、医療が高度化していくなかで個別性をもって提供できるようになるからです。
今後の日本は、高齢者が増えていくとともに、医療の高度化と複雑化はますます進んでいくと言われています。医療が高度化していくと、それぞれの職種に求められるレベルも高まります。知識や技術を高めながら、これまで通りの対応をしていくのは負担が大きくなりかねません。
医療が高度化しても患者や家族のニーズに応えるためには、他職種との連携が重要となります。連携することで、それぞれの職種が個別性をもって専門性の高い対応ができ、高度化する医療にも対応できるようになるでしょう。
参照:厚生労働省「チーム医療の推進について」
参照:厚生労働省「看護を取り巻く状況が大きく変化」
地域で生活していく患者の増加
地域で生活していく患者が増加していくことも、チーム医療が重要となる理由です。
日本の高齢者の数は増えており、2025年には団塊世代が75歳以上になります。また、85歳以上の人口も2040年に向けて増加すると言われています。
高齢者が増加するなかで、自分の住み慣れた自宅や地域で生活を続けられるようにサポートする在宅医療への移行が進められています。
在宅医療を実施するためには、他職種の連携がとても重要です。
さまざまな職種が関わることで、住み慣れた地域での医療や介護、生活支援などの実現が可能となるのです。
入院や入所をせずに、長年住んできた自宅で生活していく患者を支えるために、チーム医療は必要不可欠でしょう。
参照:厚生労働省「社会保障を支える人材の確保」
チーム医療の課題解決策や効率向上の方法を紹介

今後の医療に重要となるチーム医療ですが、課題を解決しながら効率的に進めていくためにはどうすればいいのでしょうか。
ここでは、課題解決策や効率向上の方法を3つ紹介します。
- チーム医療に携わる医療職者の働く環境の充実
- 医療DXの推進
- チーム医療の人員のアウトソーシング
それぞれについて、詳しく解説します。
チーム医療に携わる医療職者の働く環境の充実
チーム医療の課題を解決し、効率的に進めていくためには、チーム医療に携わる医療従事者の働く環境を充実させる必要があります。
医療の高度化と複雑化が進んでいるなか、チーム医療を実現させるためには、医療従事者の離職は避けなければいけません。
医療現場の仕事は過酷で離職率が高く、実際看護師の離職率は年々増加傾向にあります。
離職させないためには、労働環境を改善する必要があります。労働時間の管理や手当を十分に支払うなどの取り組みをするようにしましょう。
また、マニュアルやプロトコルなどを活用して、治療や教育を標準化をすることで業務の効率化が期待でき、医療従事者の負担の軽減につながります。
参照:連合総研・同志社大学 「医療人材の確保・育成の課題Ⅱ」
医療DXの推進
医療DXの推進も、チーム医療の課題解決と効率化につながる方法です。
医療DXとは、医療や介護で発生する情報やデータをオンライン上で保存し、情報共有などを効率化する仕組みのことです。
カルテなど紙媒体で行っていると、医療従事者の負担増加や連携ミスにつながりかねません。正確な情報連携が重要となるチーム医療では、このような事態は避けなければいけません。
そのため、正確な情報共有と業務効率化が図れる医療DXを進める必要があります。医療DXは医療機関内外での正確な情報共有だけでなく、情報保護の観点からも進めるべき取組と言えます。
参照:厚生労働省「医療DXについて」
参照:内閣官房「医療DXのメリット」
チーム医療の人員のアウトソーシング
チーム医療に関わる人員をアウトソーシングする方法も、チーム医療の課題解決と効率性の向上につながります。
医療機関でアウトソーシングと聞くと違和感があるかもしれませんが、非常勤の人員をうまく活用することで効率的なチーム医療が実現できるでしょう。
人員のアウトソーシングとして、オンコール、往診代行サービス等があります。
在宅医療が進められている中、夜間休日も対応するとなると医療従事者の負担が大きくなり、離職につながりかねません。
オンコール、往診代行サービスを活用することで、24時間体制を分業することができ、日中帯でも夜間でも質の高い医療の提供が期待できます。
また、医療DXに取り組んでいるため患者情報の連携も正確に実施できます。
チーム医療を整えるメリット
チーム医療を整えることは、さまざまな医療現場で多くのメリットをもたらします。
- 医療の質が高まる
- 医療従事者の負担削減
- 患者の在宅医療の要望に対応できる
また、医師や看護師だけでなく、リハビリ担当者や薬剤師なども協力することでより円滑で効率の良い医療提供が実現します。
患者の多様なニーズに柔軟に対応できる体制づくりにもつながるでしょう。それぞれの詳細を確認していきます。
医療の質が高まる
チーム医療では、医師、看護師、薬剤師、リハビリスタッフなど多職種が一丸となって情報を共有し、患者の治療方針やケア内容を多角的に検討します。
それぞれの専門性を生かし合うことで、見落としのない質の高い医療サービスの提供が可能になります。
また、複数の視点から患者をサポートするため、合併症の予防や早期発見にもつながりやすくなるのです。
結果として、患者一人ひとりに合った適切な治療やケアを行えることが、医療の質の向上につながります。
医療従事者の負担削減
チーム医療の導入によって、医療従事者それぞれが自分の専門分野に注力しやすくなり、業務の効率化と分担が進みます。
従来、医師や看護師が多くの業務を一人で抱えていた場合と比べ、各職種が役割分担することで不要な負担が軽減されやすくなります。
たとえば、リハビリの指導や薬剤管理は専門職が担うことで全体の作業量が分散されます。
その結果、スタッフ間のストレスも減少し、バーンアウトや医療事故のリスク低下が期待できます。
患者の在宅医療の要望に対応できる
近年、患者の在宅医療や地域での医療ニーズが高まっています。
チーム医療が整っている環境では、医師だけでなく在宅看護師や訪問リハビリスタッフ、薬剤師、ケアマネジャーなどが連携して、在宅生活をサポートできます。
これにより、患者の個別の状況や家族の希望に迅速かつ柔軟に対応しやすくなります。
病院での治療だけでなく、退院後のケアや在宅での療養生活にもチームで取り組むことで、患者のQOL(生活の質)向上が図れます。
チーム医療の質を高めるためのポイント
チーム医療の成果を最大限に高めるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
- 他職種連携の教育体制を整える
- 各職種の役割を明確にしておく
- それぞれの職種の方が専門性を高めておく
これらのポイントに注意を払うことで、チームとして最大の力を発揮し、患者へより良い医療サービスを提供できるようになります。それぞれ確認していきます。
他職種連携の教育体制を整える
質の高いチーム医療を実現するためには、他職種が円滑に連携できるための教育体制づくりが必要です。
多職種合同の勉強会やケースカンファレンス、院内外の研修に積極的に参加することで、職種を超えたコミュニケーション力や協働力が養われます。
これにより、現場での情報共有のスピードや正確性が高まり、患者ケアの妥当性も向上します。
また、普段からお互いの専門性を尊重し、良好な人間関係を築くことも教育・訓練の一環として大切です。
各職種の役割を明確にしておく
チーム医療を円滑に進めるためには、あらかじめ各職種の役割と責任範囲を明確にすることが重要です。
お互いの担当業務が重複したり、逆に抜け落ちたりしないように、役割分担を明文化し、チーム全員で共有しておくことが不可欠です。
これにより、情報伝達のミスやトラブルを未然に防ぎ、スムーズな医療提供を実現します。
また、定期的に役割の見直しを行い、現場や患者のニーズに柔軟に対応できる体制を整えることも大切です。
それぞれの職種の方が専門性を高めておく
チーム医療の強みは、多様な専門知識と技術に基づいたアプローチにあります。
しかし、その強みを十分に発揮するためには、各職種が自分の専門性を常に磨き続ける必要があります。
定期的な研修や学会、最新の医療情報の取得などを通してスキルを高めておくことが大切です。
個々の専門性が高くなることで、チームの対応力や解決策の幅も広がり、結果的に患者に提供する医療のレベルが向上します。
今後の医療のためにチーム医療の実現を

チーム医療に関わる職種や、チーム医療が抱えやすい課題と重要性、チーム医療を効率化する方法について解説しました。
医療の高度化や高齢者が増加していくなかで、チーム医療は専門性の高さを発揮でき、質の高い医療を提供できるため重要です。
しかし、たくさんの医療従事者が関わるからこそ、人員確保が難しかったりお互いの理解不足が起きたりします。
チーム内でのコミュニケーションの強化、相互理解を深めるための継続的な教育とトレーニング、そして各職種の専門性を尊重しながら協働し、患者さんへの最適なケアを提供していきましょう。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。


関連記事RELATED







