准看護師が仕事を辞める理由10選!退職・転職を回避するための対策も併せて解説!
2025.04.30
2025.06.11
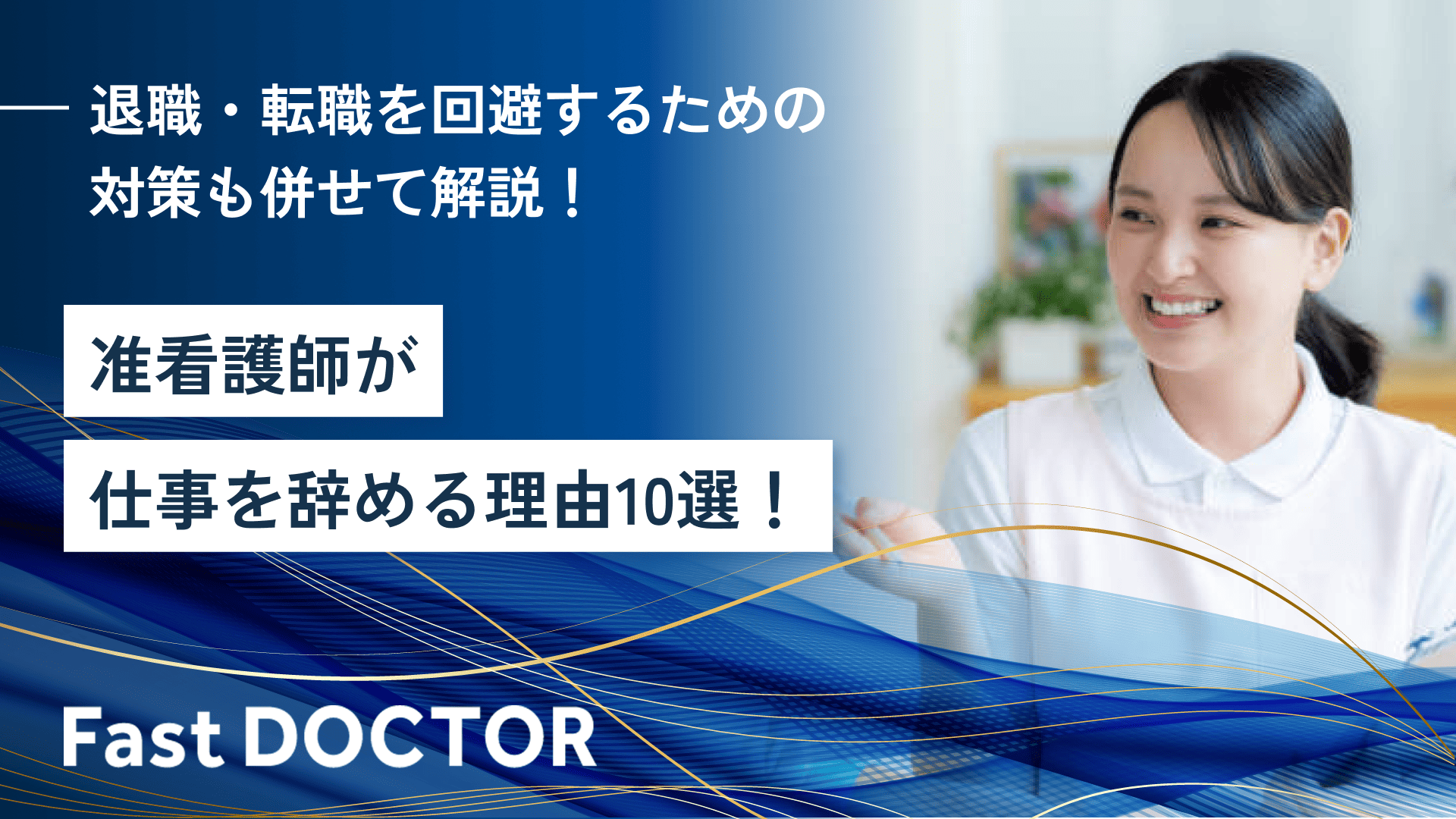
「准看護師が仕事を辞める理由が知りたい」
「准看護師の退職・転職を回避するための対策は?」
このような疑問をお持ちの医療機関も多いのではないでしょうか?
医療現場でさまざまな業務を担当する准看護師が仕事を辞めてしまうと、その他の方に業務負担が分配されるなど負担が増大します。
そのため、准看護師の退職・転職を防ぎ、働きやすい職場の構築は医療機関にとって重要です。
本記事では、准看護師が仕事を辞めてしまう理由や、准看護師の退職・転職を回避するための対策を紹介します。准看護師の離職にお悩みの医療機関は参考にしてください。
なお、ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
准看護師が仕事をやめる10個の理由
准看護師として働く中で、多くの人がさまざまな理由から退職を考えることがあります。准看護師が離職を考える代表的な理由を10選紹介します。
- 職場の人間関係
- 人手不足による業務量の多さ
- 夜勤がある
- 理想とのギャップが大きい
- 責任が重すぎる
- 医療事故への不安
- 残業代が出ない
- 仕事に給料が見合っていない
- 向いていないと感じる
- 他にやりたいことが見つかった
まずは、それぞれの理由の詳細を確認していきましょう。
職場の人間関係
看護の現場はチームワークが不可欠ですが、人間関係のトラブルは尽きません。
先輩や同僚との価値観の違いや、コミュニケーション不足、指導や指摘の仕方などで衝突が生じることがしばしばあります。
また、パワハラやいじめ、無視などの深刻な問題が発生することもあり、精神的なストレスが大きくなり退職を決意するケースも多いです。
人手不足による業務量の多さ
多くの医療現場では慢性的な人手不足が続いており、そのため准看護師一人あたりの業務負担が非常に大きくなっています。
定時で帰れないことはもちろん、他のスタッフの分までカバーしなければならず、休憩時間も十分に取れないことにもつながります。
体力的にも精神的にも限界を感じ、体調を崩してしまう不安から仕事を辞める人が少なくありません。
夜勤がある
看護の仕事には夜勤が付き物です。特にシフト制で夜勤が続くと、生活リズムが崩れやすく、体調を崩す原因になります。
夜勤による睡眠不足や疲労の蓄積は、健康への悪影響だけでなく、プライベートの時間の確保も難しくさせます。
夜勤が自分には合わないと感じることが、退職の大きなきっかけになる場合もあります。
理想とのギャップが大きい
准看護師を志したときの理想と、実際の現場とのギャップに悩む人は少なくありません。
患者さんに寄り添いながらケアをしたいと思っても、現実には忙しさから一人一人に十分な対応ができなかったり、事務仕事に追われることもあります。
思い描いていた「やりがい」や「貢献感」を得られないことが、辞めたい理由につながります。
責任が重すぎる
准看護師は医療の現場で多くの責任を担っています。
ミスが許されないプレッシャーや、患者さんの命を預かる重圧は、経験を重ねても慣れることはありません。
「何かあったら自分の責任」との思いで日々働き続ける中、精神的な疲労が大きくなり、責任の重さに耐えきれず退職を選ぶ方もいます。
医療事故への不安
医療現場での小さなミスが大きな事故につながることがあり、医療事故への強い不安を抱える准看護師も多くいます。
患者の安全を守るために常に気を張らなければならず、ミスを恐れて仕事が楽しめなくなることもあるでしょう。
医療事故のリスクと隣り合わせの状況から、ストレスが限界を迎え看護師を辞める選択をする人も少なくありません。
残業代が出ない
医療現場ではサービス残業が常態化している職場もあり、本来発生するべき残業代が支払われないケースもあります。
業務量が多くて長時間残らざるを得ないのに、その対価が得られないのは大きな不満につながります。
正当な賃金が支払われない状況に耐えきれず、辞めることを選択する人も多いです。
仕事に給料が見合っていない
准看護師の業務は責任や負担が大きいにもかかわらず、その労働に見合った給与が得られていないと感じる人が多いのが現状です。
昇給や手当が少なく、生活や将来設計に不安を感じることもあります。
努力や貢献が正当に評価されない職場環境に疑問を持ち、より条件の良い仕事を求めて退職を考える人も増えています。
向いていないと感じる
仕事を続けるうちに「自分にはこの仕事が向いていない」と感じる方もいます。
ストレスやプレッシャーに弱い、コミュニケーションが苦手、立ち仕事による身体的な負担が重いなど自身に看護師は向いていないと考える方は自分らしく働ける職場を探すために、思い切って転職や退職を決断する人も珍しくありません。
他にやりたいことが見つかった
働いているうちに、他にやってみたい仕事や挑戦したいことが見つかる場合もあります。
資格や経験を活かして医療とは異なる分野に飛び込んだり、自分の夢に向かって新たな勉強を始めたりといった前向きな理由での退職です。
ライフステージや価値観の変化に伴い、新たな人生を選ぶ人も多くいます。
このように、准看護師を退職・する決断はさまざまであるためそれぞれの理由に応じた対策が求められます。
准看護師の退職・転職が医療機関に与える影響
准看護師が退職や転職をすることは、医療機関にとってさまざまな影響を及ぼします。
- 人手不足による他の看護師の負担増大
- 夜勤の体制構築の困難さ
- 育成コストの無駄
- 医療の質の低下
特に現場では日常的な業務に大きな負担が生じるだけでなく、医療サービスの質にも関わる重大な問題です。
准看護師の退職や転職が医療機関に与える具体的な影響について詳細を確認していきます。
人手不足による他の看護師の負担増大
准看護師が組織を離れることで、現場の人員不足が深刻化します。その穴を埋めるため、残された看護師への業務負担が一気に増加することが多いです。
例えば、日勤や夜勤での業務量や患者対応の数が増えるだけでなく、精神的なプレッシャーも高まります。
このような状況が続くことで、他の看護師のモチベーション低下を引き起こすリスクがあります。
また、スタッフの疲労が蓄積されることにより、医療事故やミスの発生率が高くなるなど、負の側面が大きくなります。
夜勤の体制構築の困難さ
医療機関にとって夜勤の体制は患者の安全を守るうえで非常に重要ですが、准看護師が辞めてしまうと夜勤シフトを組むことがさらに困難になります。
特に中小規模の病院や地方の医療機関では、もともと夜勤スタッフが限られているため、一人でも抜けると夜勤体制が維持できなくなる可能性があります。
その結果、夜勤の頻度増加や急なシフト変更が起こりやすくなり、他のスタッフへの過度な負担や不満の発生につながります。
こうした状況は現場のチームワークにも悪影響をもたらし、医療の提供体制自体が不安定になるリスクを抱えます。
育成コストの無駄
医療機関は新たなスタッフを採用した後、一定期間をかけて実務を教えながら、職場に馴染ませるための育成を行います。
准看護師の育成には現場教育やOJTだけでなく、外部研修や資格取得支援などさまざまなコストと時間がかかっています。
しかし、せっかく育成した准看護師が短期間で退職・転職してしまうと、その投資が無駄になり、再び採用・育成コストを負担する必要が出てきます。
この繰り返しは経営上の負担だけでなく、既存スタッフの士気低下にもつながりかねません。
医療の質の低下
准看護師の退職や転職による人員不足は、結果的に病院やクリニックにおける医療の質低下を招く恐れがあります。
スタッフの数が減ることで、患者一人ひとりに丁寧なケアを提供する時間が減り観察やケアの質が下がってしまうリスクが高まります。
また、経験豊富な准看護師が抜けると現場には知識や技術に乏しい職員ばかりが残り業務全体の効率や安全性も損なわれます。
このような事態が続けば、患者からの信頼喪失やクレーム増加につながりかねません。
准看護師の退職・転職を防ぐために医療機関ができる対策
准看護師が長く働き続けられる環境を整えることは、医療機関にとって大切な課題です。
離職や転職を防ぐためには、職場環境や待遇、サポート体制に配慮した具体的な対策が求められます。
- 一人ひとりの成長をサポートする環境を作る
- 手当ての増加など待遇面を良くする
- フォロー体制を手厚くする
准看護師を支えるために医療現場で取り入れるべきポイントを解説します。
一人ひとりの成長をサポートする環境を作る
准看護師にとって、キャリアアップやスキルの習得は大きなモチベーションとなります。
そのため、個々のレベルや将来の目標に合わせた研修制度や、勉強会の開催など、成長をしっかり支援する環境作りが重要です。
また、定期的な面談を通じて仕事の悩みや目指す姿を共有し、中・長期的なキャリアステップを一緒に考えることも大切です。
こうした取り組みは「自分を大切にしてくれる職場」という信頼につながり、定着率の向上に直結します。
手当ての増加など待遇面を良くする
給与や手当てなどの待遇面が不満で転職を考える准看護師も少なくありません。
夜勤手当や資格手当、住宅手当などの各種手当てを見直し、地域の相場や他院と比べて遜色のない水準に整えることが重要です。
さらに、賞与や昇給制度を明確にし、努力や勤続年数に見合った評価を行うことで、安心して働ける環境を実現できます。
経済的な安定は職員の精神的な安定にもつながり、長期的な勤務意欲の維持に大きくつながります。
フォロー体制を手厚くする
准看護師が安心して働き続けるためには、日常業務での悩みやトラブルにもすぐに対応できるフォロー体制が不可欠です。
先輩看護師や管理職が定期的に声をかけ、業務や人間関係の悩みに寄り添いフォローできる体制を整えてましょう。
また、業務が過剰になっていないかを見守ることも大切です。
小さな悩みも放置せず職場全体で気にかけることが、信頼関係の構築や離職の抑制につながります。
准看護師自身で取れる対処法
准看護師として働く中で、職場でのストレスを感じる方は少なくありません。しかし、自分自身でできる対処法を知り実践することで、日々の業務の中でもより良いコンディションを保つことが可能です。
ここでは、准看護師が自ら取り組める具体的なストレス対策について紹介します。
- 十分な休息をとる
- 完璧を求めすぎない
- 悩んだ際は1人で抱え込まない
それぞれ確認してストレスマネジメントに活かしてください。
十分な休息をとる
准看護師は、夜勤や長時間勤務によって疲労が蓄積しやすい職種です。
体調の管理を怠ると、ミスやケガにつながるリスクも高まるため、仕事が終わった後や休日にはしっかりと休息をとることが大切です。
時間があれば仮眠をとる、質の良い睡眠を意識する、趣味やリラクゼーション、家族との時間を大切にするなど、自分なりのリフレッシュ方法を見つけて取り入れましょう。
休息を意識することで、心身のバランスを保ち、業務にも前向きに取り組むことができます。
完璧を求めすぎない
医療現場では一人ひとりの責任が重いため、どうしても「ミスをしてはいけない」というプレッシャーを感じやすくなります。
しかし、人間は誰しも失敗するものです。自分に対して過度な完璧主義を求めることで、ストレスや自信喪失、心の負担が増してしまうこともあります。
大切なのは、自分の成長や努力を認めることです。困難を感じた場合は先輩や同僚にアドバイスを求めたり、できることから一つずつ取り組むことが理想です。
完璧を求めすぎないことで、心の余裕を持ち、前向きに業務を続けることができます。
悩んだ際は1人で抱え込まない
仕事上で悩みや不安を感じたとき、つい自分だけで解決しようと頑張ってしまうことがあります。
しかし、悩みや負担を1人で抱え込むことは、心身の不調やバーンアウトの原因になりかねません。信頼できる同僚や先輩、上司に相談することで、新たな視点や解決策を得られることがあります。
また、職場内だけでなく、家族や友人などに話を聞いてもらうのも効果的です。
早めに相談することで、気持ちが軽くなり、前向きに仕事に取り組むことができるでしょう。
働きやすい職場環境構築が医療の質を高める
准看護師が能力を最大限に発揮し、患者さんにより良いケアを提供するためには、個人の努力だけでなく、職場環境の整備が欠かせません。
コミュニケーションが活発で、サポート体制が整った職場では、スタッフ一人ひとりが安心して業務に取り組めるため、仕事への満足感も高まります。
働きやすい環境は離職率の低下やスタッフの成長にもつながり、最終的には医療提供の質向上にも直結します。
管理者や職場全体で職場環境の改善を意識し、スタッフが安心・安全に働ける環境を目指しましょう。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

関連記事RELATED







