在宅医療のオンコール分担方法や課題は?医師・看護師の離職を防ぐポイントも合わせて解説!
2025.04.30
2025.06.11
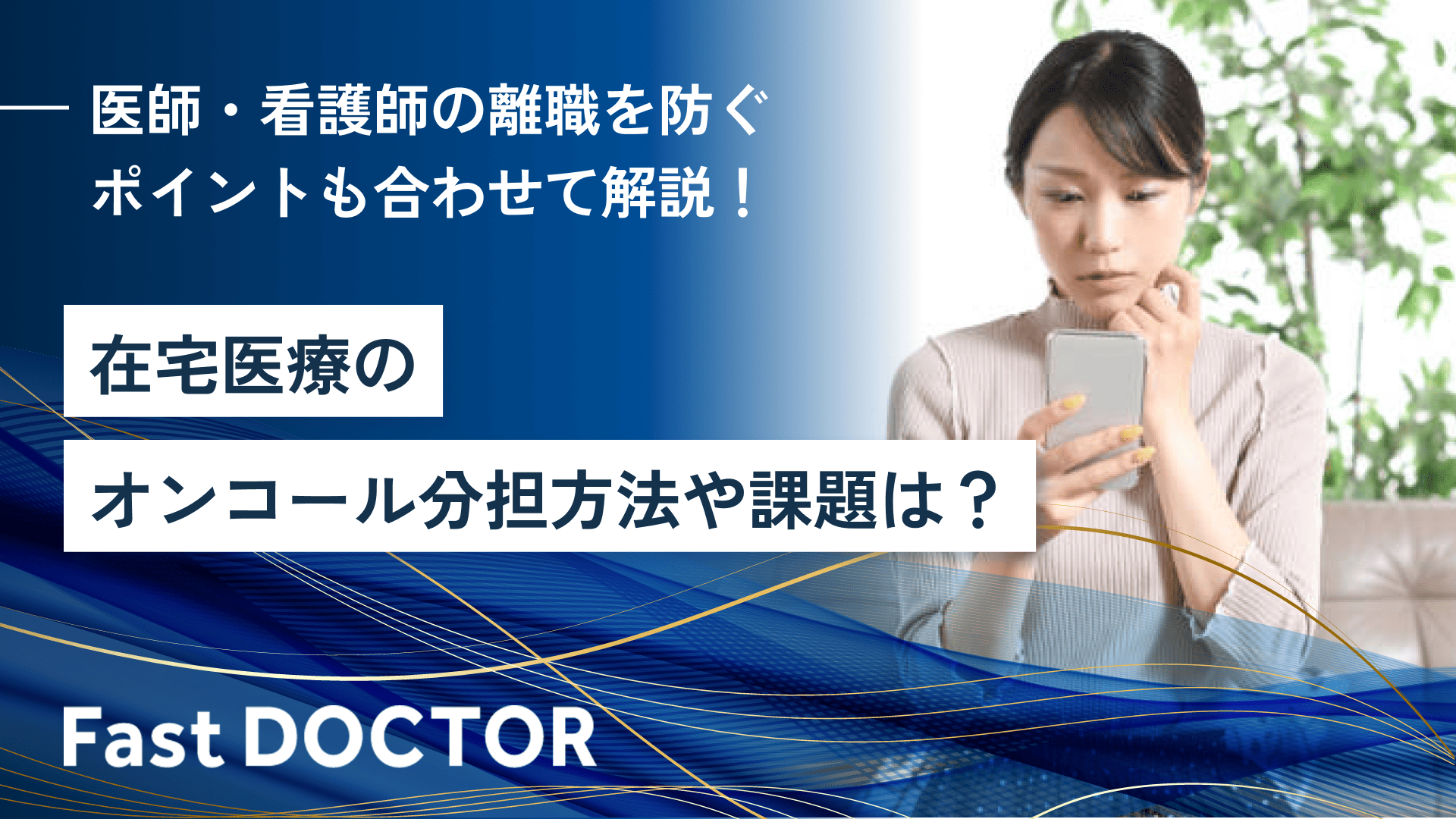
「在宅医療のオンコール対応の分担はどうしてる?」
「オンコールによる医師・看護師の負担の削減法は?」
「おすすめのオンコール代行会社が知りたい」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
夜間・休日のオンコールに対応しいてる医療機関にとって、医師や看護師へ与えるオンコール対応の負担に悩みを抱えるケースはよく見られます。
オンコールによる負担が続くと、医師や看護師にストレスがたまり離職につながることも少なくありません。
本記事では、一般的な医療機関の在宅医療のオンコール分担方法や課題への対処法を紹介します。参考にしてください。
なお、ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
在宅医療のオンコール当番の分担は医療機関ごとで異なる
在宅医療において、夜間や休日などの急な対応が必要となる「オンコール当番」の分担方法は、医療機関ごとにさまざまです。
各施設の規模やスタッフ数、患者数や地域性によって体制がとられています。
ここでは、オンコール体制の代表的な分担方法について紹介します。
院長1人体制
小規模なクリニックが在宅医療を提供する場合、院長1人ですべてのオンコール対応を担うケースが見られます。
この体制では、患者や家族からの急な連絡にも院長自身が直接対応してくれるため患者からすると安心感があります。
意思決定のスピードや高い信頼性は強みですが、オンコールによる負担が大きく、院長のプライベートな時間確保や体調管理が課題になることもしばしばです。
医師数人で分担
複数名の医師が在籍する医療機関では、オンコール当番を曜日や日数で分担してて対応しているケースも見られます。
当番表を作成して一人に負担が集中しないように調整されるのが一般的です。
医師同士でサポートし合える環境は、業務の継続性や医師個人の負荷軽減において効果的です。
ただし患者情報の共有や、緊急時の引き継ぎ方法を明確にしておくことが重要となります。
看護師が当番を決めてファーストコールを受け取る
医師だけでなく、看護師がファーストコールを担当し、必要に応じて医師に連絡する体制も一般的です。
看護師が初期対応を行うことで、医師の負担を軽減し、迅速な対応やトリアージが可能になります。
当番制を採用し、看護師間でシフトや役割分担を明確にしている医療機関も見られます。
看護師の判断力や経験が求められる場面も多いですが、チーム全体で効率的なオンコール体制の構築が可能となります。
在宅医療のオンコール体制構築の重要性
在宅医療においてオンコール体制の整備は以下の観点からも非常に重要です。
- 患者の体調急変時に迅速な対応が取れる
- 患者と家族の安心感を与えられる
患者が自宅で安心して生活できるためには、急な体調変化や不測の事態にも迅速に対応できる仕組みが不可欠です。
医療従事者が24時間体制で対応できるよう準備することで、患者やその家族の負担を大きく軽減し質の高い医療を提供し続けることが可能となります。それぞれ確認していきます。
患者の体調急変時に迅速な対応が取れる
在宅医療では、患者が自宅というリラックスした環境で治療を続けられる一方、急な容態変化が発生した場合にはスムーズな対応が求められます。
オンコール体制を構築しておけば、深夜や休日でも専門スタッフが連絡を受け、必要に応じて現場への訪問やアドバイスが可能です。
迅速な応急処置や適切な判断により、重篤な事態への進行を防ぎ、患者の命を守る重要な役割を果たします。
また、医療機関への搬送が必要かどうかの的確な判断もできるため、不要な救急搬送の抑制にもつながります。
患者や家族に安心感を与えられる
在宅で医療を受ける患者やその家族にとって、何かあったときにすぐ相談や対応が受けられる体制が整っていることは大きな安心材料となります。
夜間や休日、医療機関が閉まっている時間帯でも、オンコール体制により専門の医療スタッフにつながる窓口があれば、不安を和らげることができます。
また、日常的なケアにおける疑問や悩みにも即座に対応できるため、在宅療養生活の継続やQOL(生活の質)の向上にもつながるでしょう。
このようなサポート体制が、患者・家族ともに安心して在宅医療を選択できる基盤となります。
在宅医療のオンコール体制構築の課題
在宅医療におけるオンコール体制は、患者の急変や緊急時に迅速な対応ができるという利点があります。
しかし、その一方で医師や看護師にさまざまな負担や課題が生じている現状もあります。
- 医師や看護師の精神的・身体的負担の増加
- 医師や看護師の採用が難しくなる
- 医師や看護師の定着率の低下
- スケジュール調整の困難さ
それぞれの課題の詳細を確認していきます。
医師や看護師の精神的・身体的負担の増加
オンコール当番の日は、日中の業務終了後であっても緊急時には急な電話対応や呼び出しを受け、すぐに対応しなければなりません。
そのため、常に気を張った状態が続き、精神的なストレスが増す要因となります。
また、夜間や休日にも対応を迫られることで十分な休息が取れず、身体的な疲労も蓄積しやすくなります。
これが慢性的になると、バーンアウトや健康障害のリスクも高まります。
医師や看護師の採用が難しくなる
オンコールによる負担の大きさは、医師や看護師の新規採用を困難にする要因のひとつです。
働き方改革が進む中で、プライベートな時間や生活の質を重視する志向が高まっており、負担の多い職場環境は敬遠されがちです。
また、経験の浅い医療従事者にとっては、緊急対応に対する不安や責任の重さも心理的なハードルとなります。
そのため、採用活動において求める人材の獲得が難しくなる点も在宅医療のオンコール体制構築の課題です。
医師や看護師の定着率の低下
オンコールによる心身の負荷が続くことで、医師や看護師の離職率が高まり、定着率に悪影響を及ぼします。
持続的な負担やワークライフバランスの崩れは、職務満足度の低下につながります。
実際、オンコールの負担を理由に退職を選択するケースも少なくありません。
このような人材流出は、職場に残るスタッフへの更なる負担増につながり、悪循環を生む原因となります。
スケジュール調整の困難さ
オンコール体制では、限られた人数で担当シフトを回さなければならないため、スケジュール調整が非常に難しくなります。
個々のスタッフの希望やライフスタイル、体調などを考慮する必要があり、シフトに柔軟性を持たせるのは容易ではありません。
また、急な欠員が出た場合には、代替要員の手配も困難です。このような調整の難しさが、より一層現場に負担とストレスをもたらしています。
在宅医療のオンコール体制構築の対策
在宅医療の現場においては、患者様の急変や夜間の対応が求められることが多く、医療スタッフにかかる負担が大きくなりがちです。特にオンコール対応では、医療スタッフの心身の健康への配慮が課題となります。
これらの負担を軽減し、質の高い在宅医療を提供するためには、さまざまな対策を講じることが必要です。
- オンコール代行の導入も検討する
- 緊急訪問時の直行直帰が可能な体制を構築する
- オンコール対応のマニュアルを作成しておく
- オンコール対応をしてくれる方への待遇を改善する
- 休暇に関する福利厚生を充実させる
それぞれの対策を確認して取り入れてください。
オンコール代行の導入を検討する
オンコール業務が医療スタッフの負担になるのを防ぐためには、外部のオンコール代行サービスの導入も有効な手段です。
夜間や休日のコールを専門のオペレーターが一次受付し、内容に応じて適切な医師や看護師に判断を委ねることで、スタッフの拘束時間を減らせます。
こうした代行サービスの導入により、医師や看護師の勤務外のプライベートな時間を確保しやすくなり、ワークライフバランスの向上につながります。ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。
低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となるためご相談ください。
緊急訪問時の直行直帰が可能な体制を構築する
緊急時の訪問対応を効率的に行うため、オンコール担当者が自宅から直接患者宅へ向かい、そのまま現場から帰宅できる直行直帰の体制を整えることも重要です。
これにより、医療拠点への立ち寄りが不要になり移動時間の短縮になるほか、スタッフの負担を最小限に抑えることができます。
また、緊急時でも迅速な対応が可能になるため、患者やご家族の安心感にもつながります。
直行直帰の運用ルールや記録方法について、事前にしっかりと決めておくことが大切です。
オンコール対応のマニュアルを作成しておく
オンコールの対応には、医師や看護師の判断が迅速かつ適切であることが求められます。
そのため、いざという時に迷わず対応できるよう、業務フローや応対方法を明記したマニュアルを作成しておくことが不可欠です。
マニュアルには、対応すべき症状や緊急性の判断基準、記録方法、連絡体制などの詳細を盛り込み、スタッフ間で情報を共有しておきましょう。
定期的に見直しや情報の共有を行うことで、誰が担当しても一定の質で対応できる体制づくりが可能になります。
オンコール対応をしてくれる方への待遇を改善する
オンコール業務は心身ともに大きな負担を伴うため、担当者の待遇を見直しインセンティブや手当を充実させることも重要です。
オンコール手当や深夜勤務手当の支給、時間外労働の賃金調整などを検討・明確化することでスタッフのモチベーション向上につながります。
また、頑張りへの評価や表彰制度を設けることも現場の士気を高めるために有効です。
待遇改善により、オンコール対応への心理的なハードルを下げ、安定した体制の構築が期待できます。
休暇に関する福利厚生を充実させる
オンコール対応の業務負担を考慮し、リフレッシュを目的とした特別休暇や有給休暇の取得促進など、休暇に関する福利厚生の充実を図ることも大切です。
代休の取得ルールやシフト調整に柔軟性を持たせることで、スタッフが安心して休める環境を整えましょう。
また、休暇をしっかり取ることで心と体の健康が保たれ、質の高い安定した医療サービス提供にもつながります。
働きやすい職場環境を作るためにも、福利厚生の見直しを定期的に行うことが求められます。
在宅医療のオンコールに関するよくある質問
オンコールの電話が鳴る頻度はどれくらいですか?
オンコール中に電話が鳴る頻度は、患者数や患者さんの病状、また地域や診療所によって大きく異なります。
一般的には、患者が多かったり重症度が高い在宅診療所では、毎晩数件の電話が発生することも珍しくありません。
一方で、患者数が少なく、安定した方が多い場合には、週に1、2回程度の連絡にとどまるケースもあります。
年間や夜間・休日ごとの集計データを診療所ごとに確認することで、おおよその傾向を把握できます。
オンコールの手当はどれくらいですか?
オンコール勤務に対する手当の金額は、医療機関や地域、職種によって異なります。
看護師の場合、1回あたり数千円程度の待機手当が一般的で、実際に出動した場合には、別途手当が支給される場合が多いです。
医師の場合は、待機手当に加え、コール対応や出動のたびに日当やインセンティブが加算されるケースも見られます。
オンコールの手当は雇用契約書や就業規則などで事前に確認しておくことが大切です。
オンコールの業務内容を教えてください
在宅医療のオンコール業務は、患者やご家族からの電話対応が中心となります。
体調の急変時の相談や服薬・医療機器などのトラブルへの助言、必要に応じて自宅への急な往診や訪問を行うことが業務内容となります。
オンコール待機中は、スムーズに連絡が取れるようにすることが必須です。
在宅医療のオンコール体制を整えて医師・看護師の負担を減らそう!
在宅医療の現場では、24時間体制の対応が求められるため医師や看護師への負担が大きくなりがちです。
しかし、オンコール代行を導入することでオンコール体制を構築することで、緊急時にも迅速かつ適切な対応が可能となりスタッフそれぞれの負担を軽減することができます。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。
低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

関連記事RELATED







