夜間オンコール体制の見直しが重要な理由とは?体制を整えて働きやすい職場環境を作ろう!
2025.04.30
2025.06.11
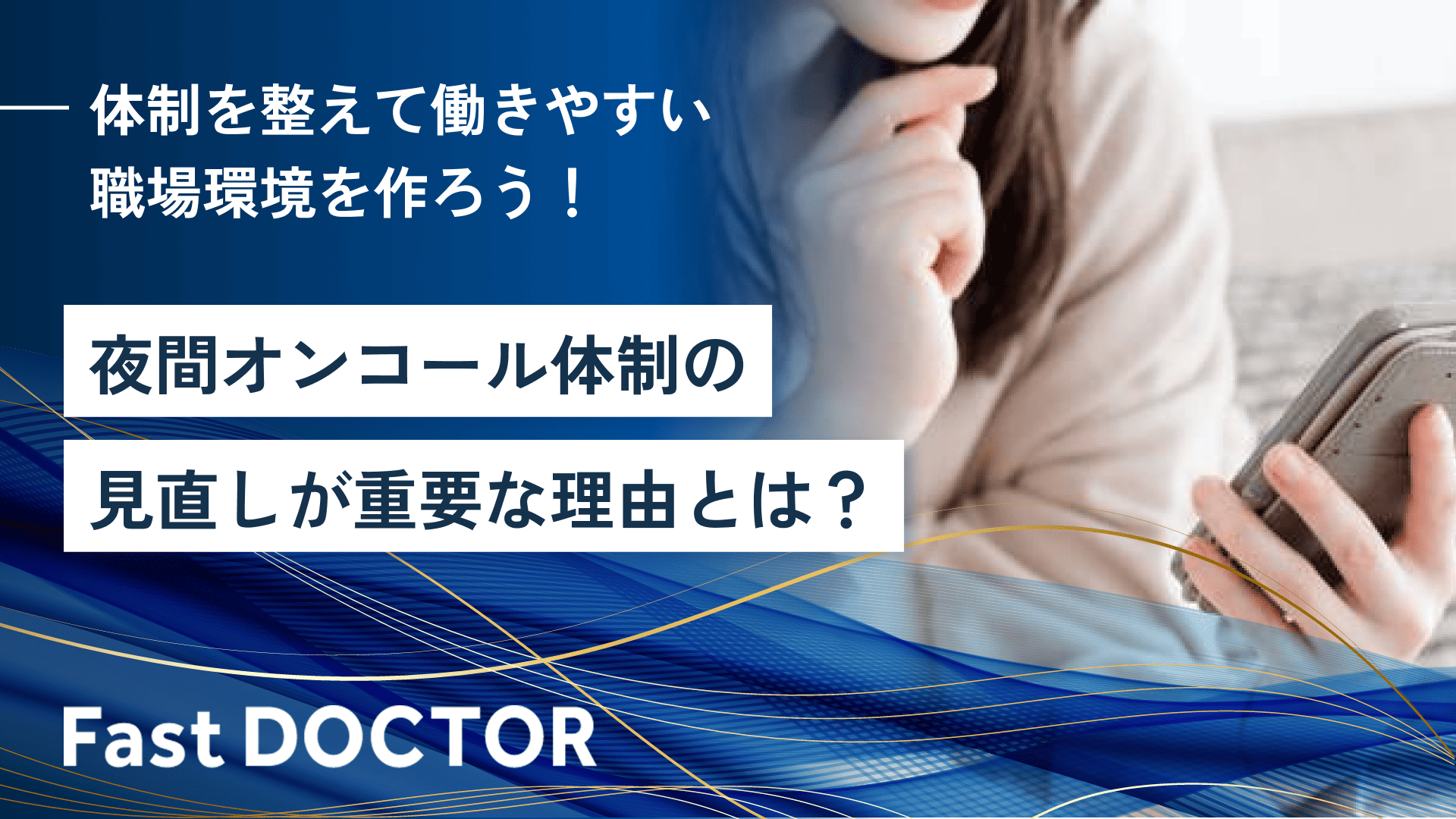
「夜間のオンコール体制は見直しが必要?」
「具体的にどのように体制を整えればいいの?」
「夜間のオンコールで医師や看護師がストレスを感じる原因は?」
このような疑問をお持ちの医療機関も多いのではないでしょうか。
夜間オンコールの対応は「自宅にいても気が休まらない」など医師や看護師の負担となります。
本記事では、夜間オンコール体制の見直しの重要性や具体的な対処法を紹介します。オンコールの体制構築にお悩みの医療機関はぜひ参考にしてください。
なお、ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
夜間オンコール体制の見直しの重要性
夜間オンコール体制は、急な患者対応や緊急事態に備えるため医療機関にとって不可欠な仕組みです。
しかし近年、慢性的な人手不足や医療従事者の負担増加が問題となっており、従来のままでは持続可能な体制を維持するのが難しくなっています。
こうした背景から、既存の夜間オンコール体制を見直しすることが急務となっています。
以下では、夜間オンコール体制の見直しが重要な理由を3つ紹介します。
人手不足で満足に体制を構築できない医療機関が多い
多くの医療機関で、スタッフの人手不足により夜間のオンコール体制を十分に構築できない現状があります。
特に地域病院や中小規模のクリニックでは、医師・看護師の人数が限られており、夜勤やオンコール業務が特定の方に偏ってしまうケースが少なくありません。
そのため、一部のスタッフに極端な負担が集中したり、最小限の人員で運用せざるを得ない状況が続いています。
結果として、医療の質や安全性が損なわれるリスクも高まります。
医師・看護師の負担増加
夜間オンコール体制の維持は、医師や看護師一人ひとりに大きな負担を強いる場合があります。
平日の日勤に加えて夜間の電話や呼び出し対応を求められるため、十分な休息を取ることができず、慢性的な疲労やストレスを抱えるスタッフが増えています。
また、突発的な対応が必要な分、精神的な緊張やプレッシャーも大きくなりやすく心身の健康に悪影響を及ぼす可能性も懸念されています。
こうした状況は、医師や看護師の働く意欲の低下や医療の質の低下にもつながりかねません。
医師・看護師の離職のリスク
夜間オンコールの負担が大きいままだと、医師や看護師の離職リスクが著しく高まります。
肉体的・精神的な負担が蓄積されることで、やがてバーンアウト(燃え尽き症候群)に陥るケースも見受けられます。
また、家庭やプライベートとの両立が難しくなる場合も多く、ワークライフバランスを求めて他院への転職や職種転換を希望するスタッフも増えてしまいます。
一人でも貴重な人材を失うことは、医療機関全体にとって大きな損失であるため、早急な対応策や体制の見直しが欠かせないのです。
夜間オンコールで医師・看護師がストレスを感じる原因
夜間オンコールは医療機関によって避けられない勤務形態ですが、多くのスタッフが精神的・肉体的なストレスを感じています。
緊急時の対応や不規則な勤務だけでなく、期待される役割や責任の大きさが重圧となり、日常生活にも影響を与えることがあります。
夜間オンコールで医師・看護師がストレスを感じる5つの原因を紹介します。
- 休んだ気にならない
- 自宅での待機が必要
- 飲酒ができない
- 翌日も通常勤務
- 責任が重い
休んだ気にならない
夜間オンコールは自宅で待機することができますが、いつ電話がかかってくるか分からないため完全に休息を取ることができません。
常に電話や呼び出しに備えて神経を張り詰めて過ごすため、仮にオンコール対応がなかったとしても心理的な緊張状態が続きます。
このため、睡眠も浅くなりやすく翌朝に「しっかり休めた」と感じにくいのが現状です。肉体的な疲労だけでなく、精神的な蓄積疲労の原因にもなります。
自宅での待機が必要
オンコール勤務中は自宅であっても自由に外出できないという制約があります。
緊急連絡がいつ来るかわからないため、出かけることや遠出をすることが困難になり、プライベートの過ごし方が大きく制限されます。
また、家族や友人との予定も立てづらくなるため、プライベートの満足度が下がりストレスの原因となります。
飲酒ができない
夜間オンコール中は、万が一の呼び出しに備えてアルコールの摂取が禁止されます。
これは業務上当然のことですが、仕事終わりやリラックスタイムにお酒を楽しみたい人にとっては、大きなストレス要因となります。
気分転換が難しく、日常のストレス発散方法が制限されることで、精神的負担がより増大します。
また、アルコールに頼らずにストレスコントロールをしなければならない難しさも付きまといます。
翌日も通常勤務
夜間のオンコール待機が明けてもそのまま通常勤務があるため、十分な休息を取ることができず疲労が蓄積しやすくなります。
呼び出しが頻繁だった場合はもちろん、呼び出しがなかった日でも緊張状態でまとまった睡眠が取れていないため、日中帯の業務で集中力や判断力の低下を感じやすくなります。
このような悪循環が、早期のバーンアウトや業務パフォーマンスの低下につながることも懸念されています。
責任が重い
オンコール中は医療現場での緊急対応を一任される場合が多く、一つひとつの判断が患者の生命や治療に直接影響します。
そのため、強いプレッシャーや責任感を感じざるを得ません。
たとえ十分な知識や準備があっても、突発的な状況や予想外の展開に備える心的負荷は大きく、オンコール担当者の精神的ストレスとなっています。
こうした重責が継続的にのしかかることで、メンタルヘルス不調のリスクも高まります。
夜間オンコール体制を見直す際のポイント
夜間オンコール体制を見直す際には、現状の課題を把握し、スタッフの負担軽減や業務効率化を図ることが重要です。
単なる体制変更に留まらず、最新のサービスやツール、福利厚生の充実など多角的な視点から体制の見直しを図ることでより良い労働環境を整えることができます。
以下に具体的な見直し方法を4つ紹介します。
- オンコール代行サービスの活用
- シフトの最適化により当番の負担を減らす
- オンコール対応をしてくれる方への待遇を改善する
- 休暇に関する福利厚生を充実させる
それぞれ確認して体制見直しに役立ててください。
オンコール代行サービスの活用
近年では、オンコール対応を専門の代行サービスに委託する医療機関も増えています。
これまで院内の医師や看護師で対応していたオンコールや出動を外部機関に委託することで、夜間帯のオンコール対応によるスタッフの疲弊を防ぐことが可能です。
オンコール代行サービスは医療や介護の現場で発生する緊急コールの初期対応を担い、必要時には出動にも対応している事業者もあります。
自施設のニーズに合ったサービスを選び、導入することでこれまでの夜間オンコールの負担削減につながります。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。
低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となるためご相談ください。
シフトの最適化により当番の負担を減らす
オンコール当番が一部のスタッフに偏ると、心身の負担やモチベーション低下につながります。
シフトの最適化を行うことで、平等な負担分担が可能になります。
たとえば、オンコール回数や業務内容に応じて公平にシフトを割り当てる仕組みや、公正なローテーション制を導入してください。
また、夜間の出動があった際は次の日に代替要員を配置する体制を整えることもポイントです。
オンコール対応をしてくれる方への待遇を改善する
オンコール対応にあたるスタッフの待遇を見直し、金銭的な手当やインセンティブを設けると、業務に対するモチベーション向上や長期的な定着につながります。
夜間帯の手当ての見直しや電話対応件数に応じて報酬が発生する制度などを検討してみましょう。
待遇改善は、現在働く医師や看護師の夜間オンコールへ対するモチベーションだけでなく採用面での応募者の増加にもつながります。
休暇に関する福利厚生を充実させる
オンコール体制を担うスタッフが十分な休養を取れるように、休暇制度や福利厚生の充実も欠かせません。
例えば、オンコール当番後は必ず休暇を取得できる仕組みや、有給休暇の柔軟な取得促進、リフレッシュ休暇の導入などが挙げられます。
こうした制度を設けることで心身ともにリフレッシュでき、離職防止や職場の雰囲気改善につながります。
医療機関のオンコールの現状
日中だけでなく夜間や休日にも患者対応が求められる医療機関では、多くの医師や看護師がオンコール当番を担当しています。
オンコールは医療従事者の負担となる一方、地域医療の継続や緊急事態への迅速な対応に不可欠な仕組みです。
最後に医療機関のオンコールの現状を紹介します。
- 病院の常勤勤務医のうち2/3以上はオンコールを担当
- オンコール当番の内容
- オンコール待機の手当
それぞれ確認していきます。
病院の常勤勤務医のうち2/3以上はオンコールを担当
多くの病院では常勤医師のうち約2/3以上がオンコール業務を担当している状況です。
これは、医師数が限られていることや診療科による人員の偏在が大きな要因とされています。
特に専門科の医師が少ない地域や中小規模の病院では、限られた医師で夜間や休日の緊急対応を回さなければならず、一人ひとりの負担が大きくなりがちです。
オンコール待機は、地域医療の安全・安心に寄与する一方、勤務医の疲弊や人材流出といった問題も招いています。
オンコール当番の内容
オンコール当番は、夜間や休日など勤務時間外に自宅や待機室で待機し、患者からの連絡があれば速やかに対応することが求められます。
実際の業務は電話での医療相談から入院患者の急変対応、救急外来での診療や手術の緊急呼び出しなど多岐にわたります。
オンコールでの対応は重大な判断を短時間で下さなければならないケースも多く、精神的なプレッシャーを伴います。
オンコール待機の手当
オンコール待機に対する手当は、勤務先の病院や地域によって大きく異なります。
多くの医療機関では、呼び出しの有無にかかわらず、待機時間自体に対して一定額の手当が支給されます。業種ごとの一般的なオンコール待機の手当相場は以下の通りです。
また、電話対応だけでなく実際に出動して業務を行った場合は別途手当が加算されることもあります。
夜間オンコール体制を見直して働きやすい職場環境を整えよう!
医療現場の働き方改革が進む中、夜間オンコール体制の見直しは医療従事者の負担軽減や職場環境の改善に直結する重要なテーマです。
オンコールの頻度や担当の割り振り方法、手当の水準を見直すことで、医師や看護師の健康を守り長期的に安定した医療提供体制を維持することにつながります。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。
低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひ相談ください。

関連記事RELATED







