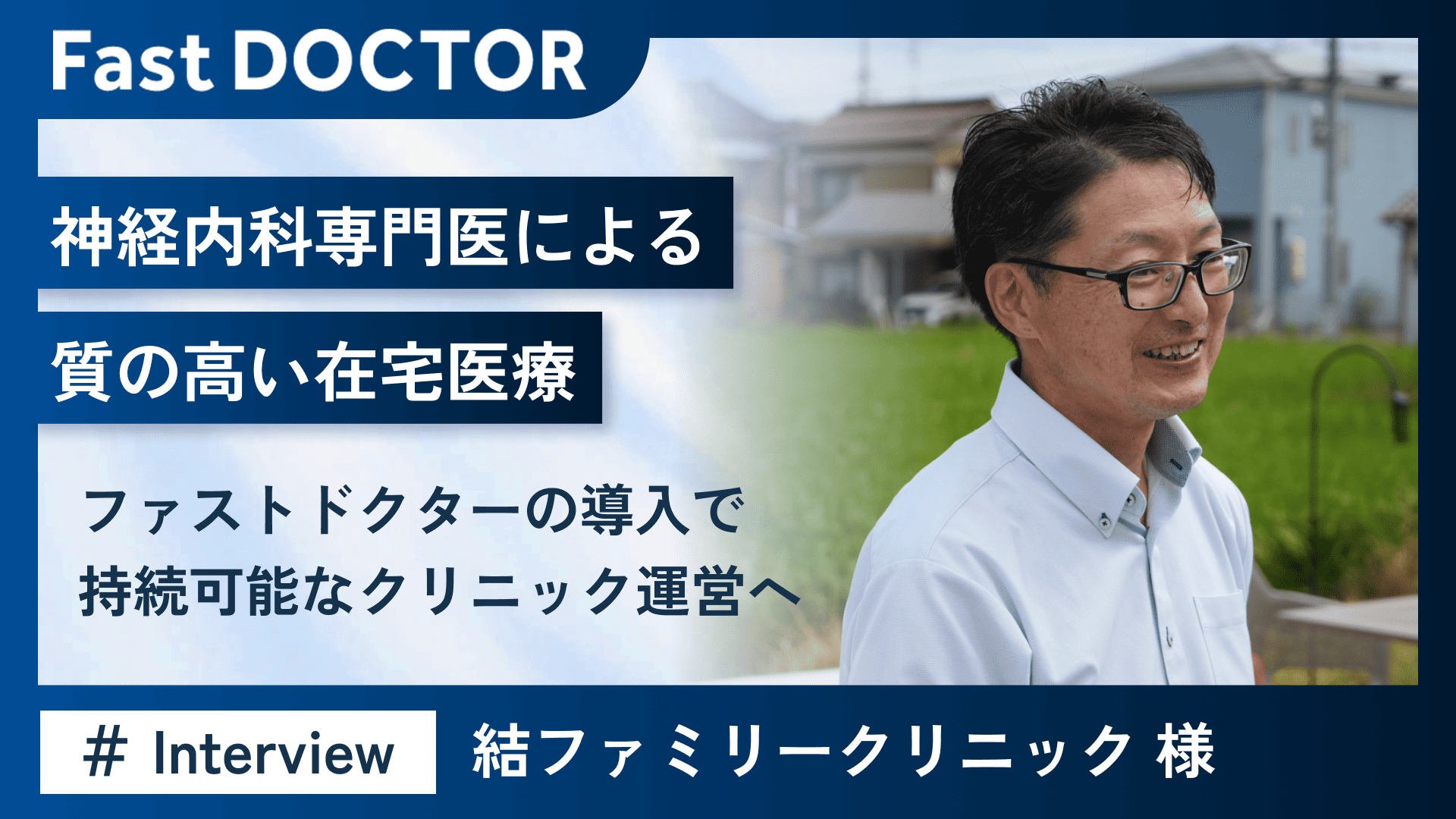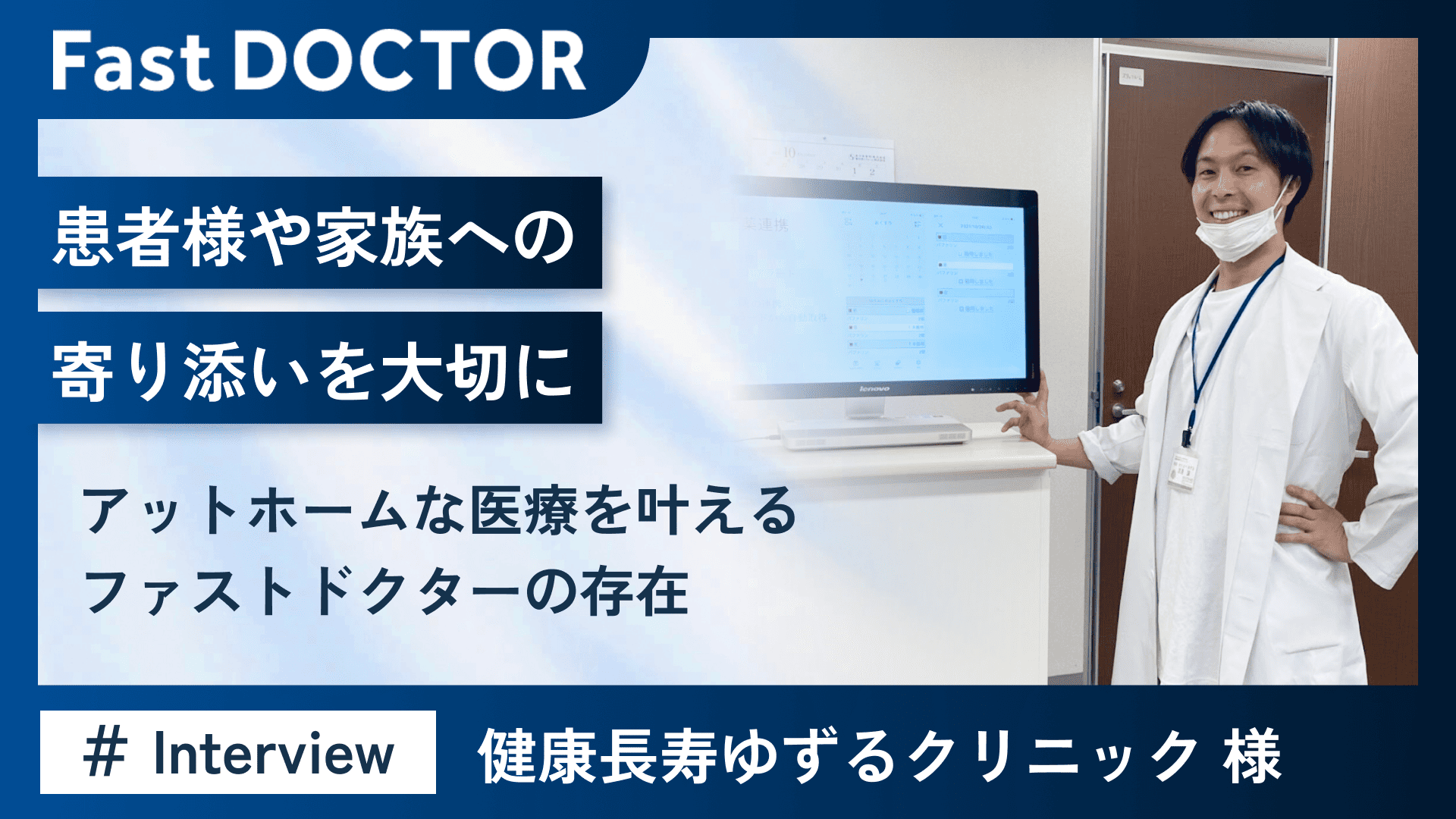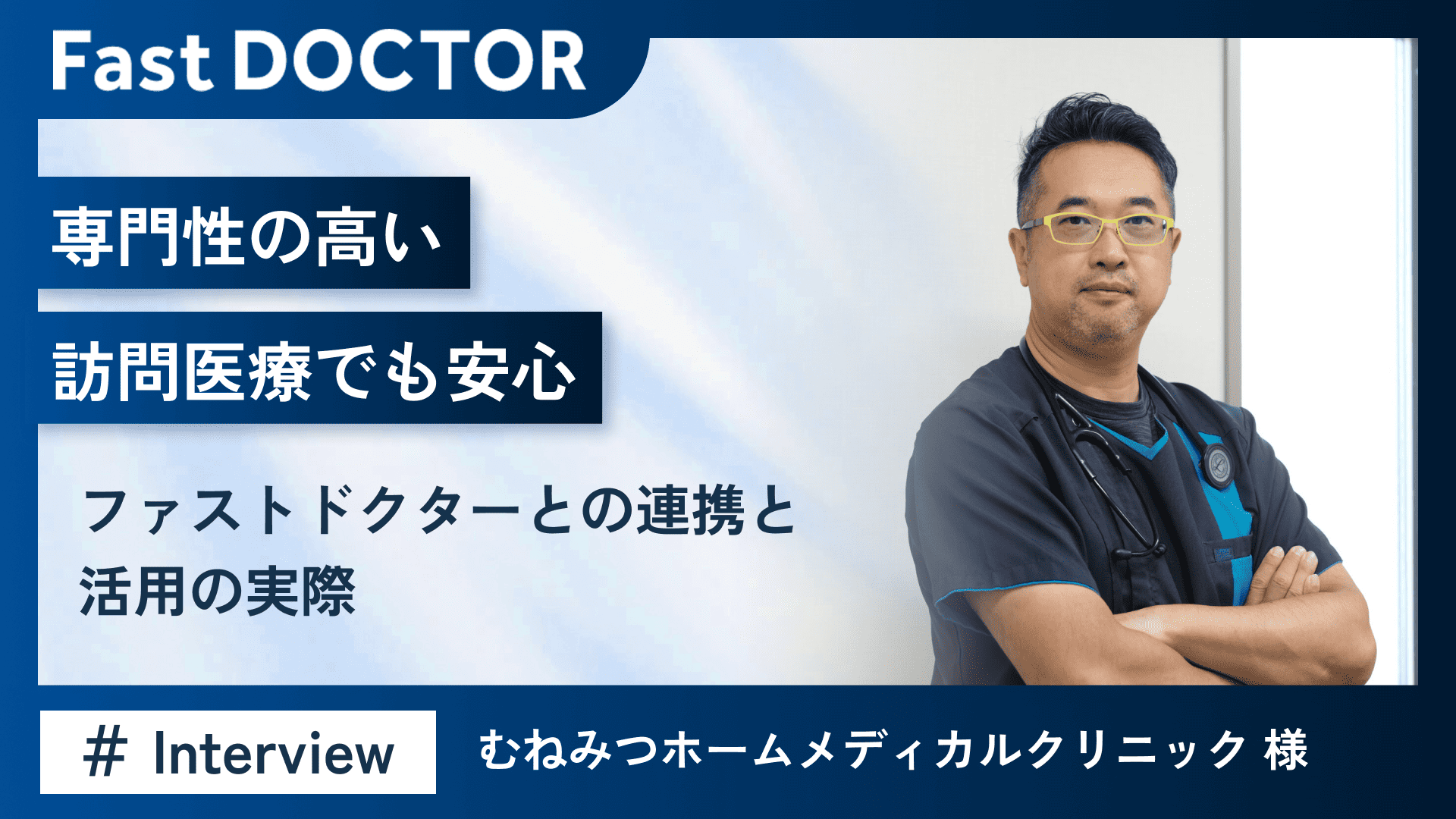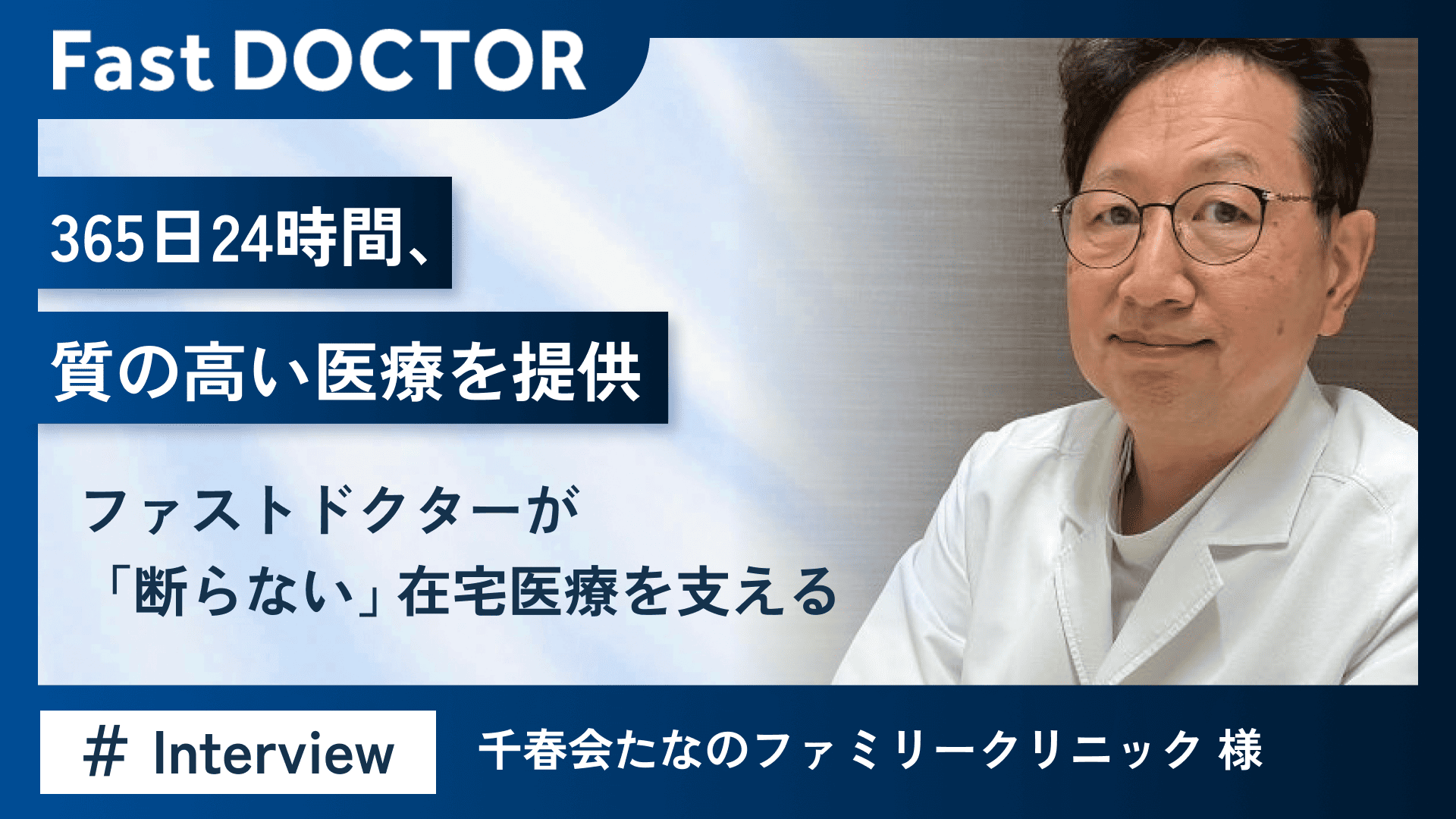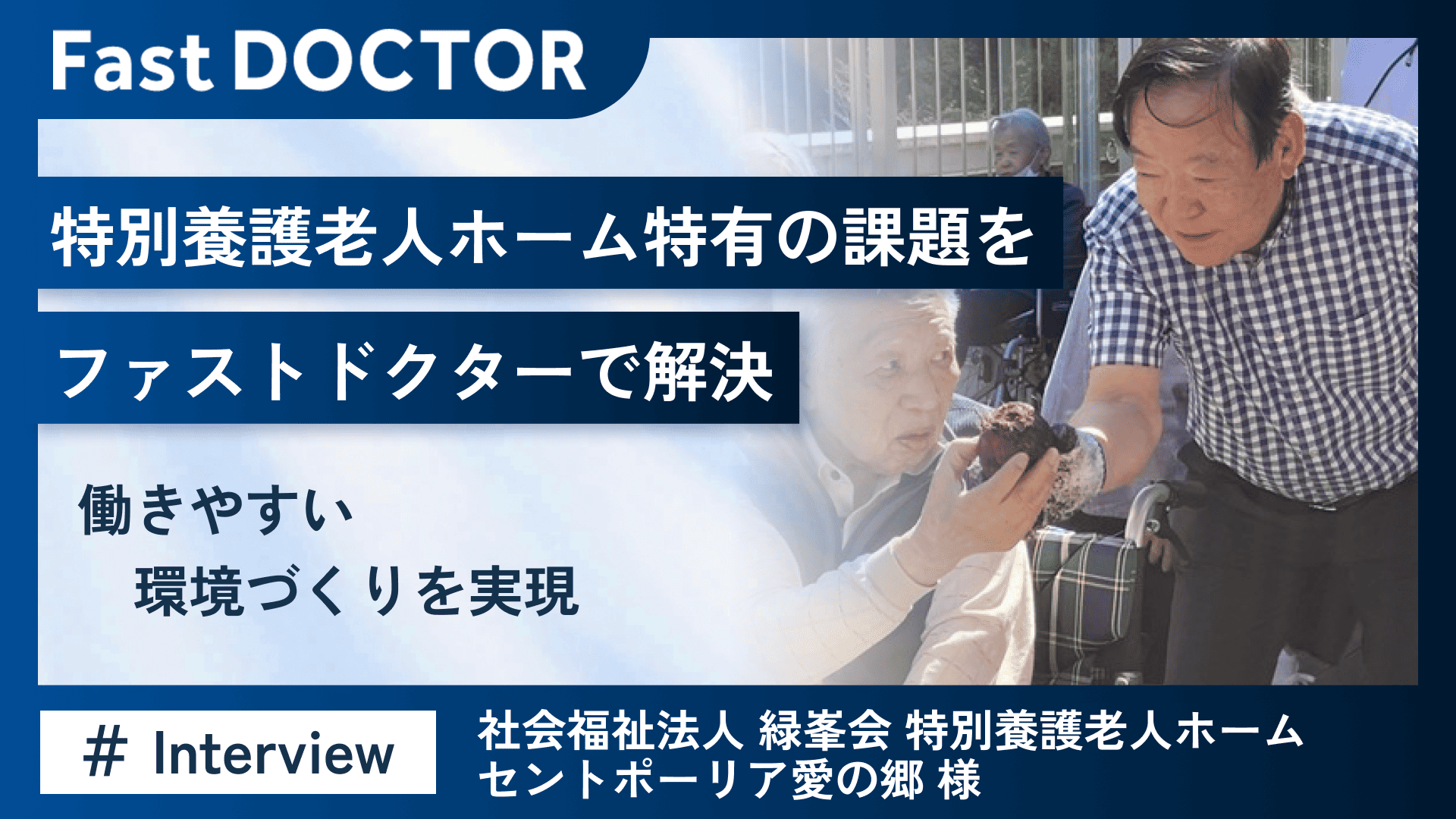守りの訪問診療から脱却~看護師の医療判断をサポートし負担軽減に貢献~
2024.02.05
2025.08.13
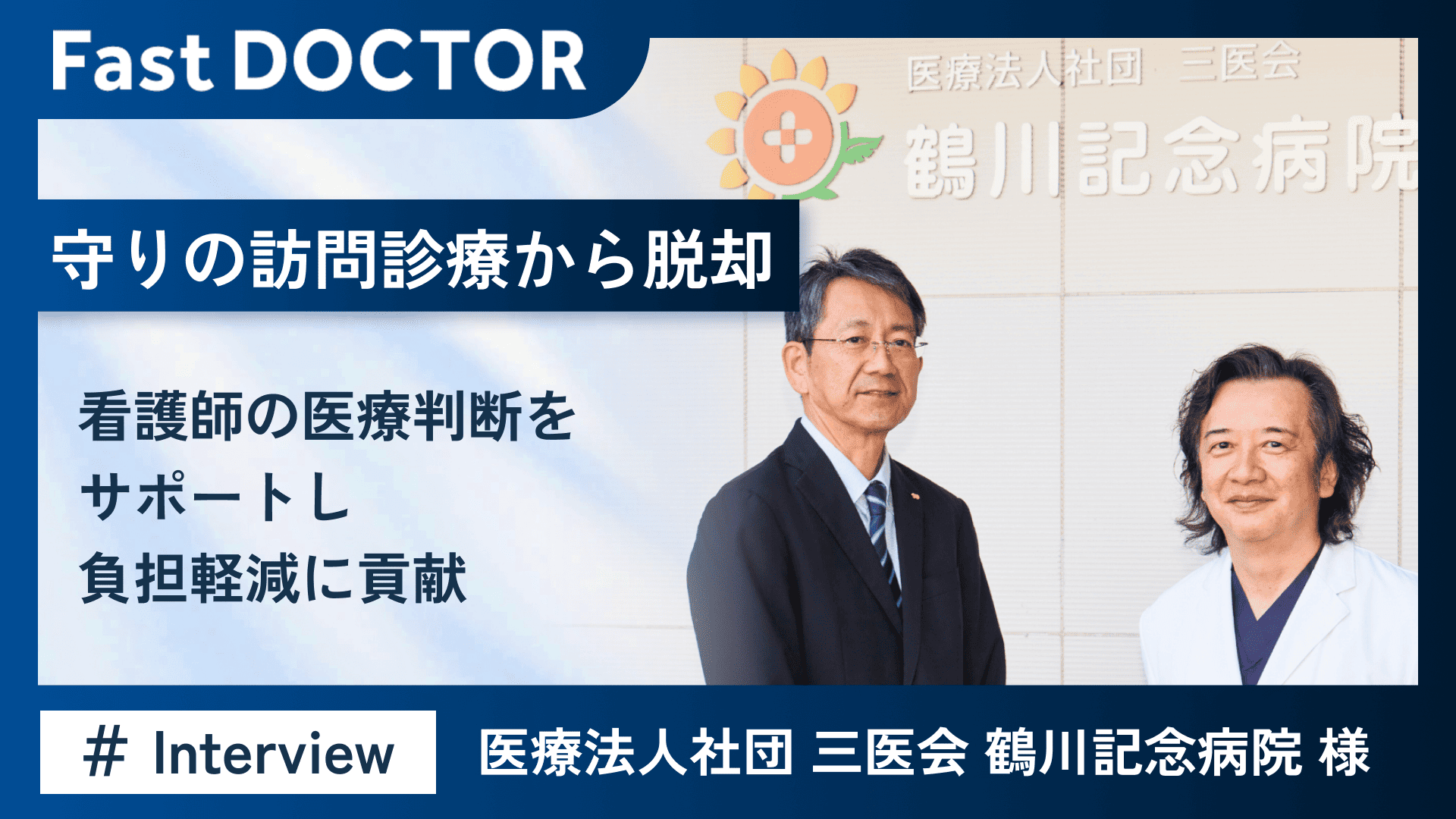

この記事の著者
医療機関プロフィール
| 医院名 | 医療法人社団 三医会 鶴川記念病院 |
| 住所・アクセス | 東京都町田市三輪町1059-1 小田急線「鶴川駅」より送迎バス・神奈川中央交通バス・フェリシアこども短期大学行「妙福寺前」 下車 徒歩5分 東急田園都市線・JR横浜線「長津田駅」より送迎バス・三輪循環バス(日・祝運休) |
| 在宅訪問診療にて対応可能な疾病・処置 | ・かかりつけ医としての日常的な健康管理 ・褥そう(床ずれ)治療 ・慢性期疾患(高血圧、糖尿病などの)治療 ・認知症治療 ・インスリン使用などの在宅注射管理 ・脳卒中などの継続的加療 ・在宅成分栄養管理(胃瘻等) ・癌の緩和ケア ・終末期ケア ・在宅中心静脈栄養管理(IVH) ・膀胱留置カテーテル管理 ・在宅酸素管理(HOT) ・人工呼吸器管理 ・各種予防接種 ・その他内科全般治療 ※検査(レントゲン・CT・超音波・心電図など)については必要時当院外来で対応 |
| 在宅診療部の従業員数 | 医師:常勤2名、非常勤12名 看護師:4名 |
| HP | https://www.tsurukawakinen.or.jp/ |
医療法人社団 三医会 鶴川記念病院では、オンコールに対応する医師の人材管理に課題がありました。24時間365日の運営管理を必要とする同院では、緊急往診の安定したリソース確保を目的にファストドクターの導入を決定し、提供する在宅サービスの安定性向上に成功しました。
今回は、医療法人社団 三医会 鶴川記念病院(以下、鶴川記念病院)病院長 舩津到さま、事務部長 金子信之さま、在宅支援室 管理者(師長)橋本勝美さまに、ファストドクターの導入に関してのお話を聞きました。

Q鶴川記念病院は美しい自然の中にありますね。
鶴川記念病院 病院長 舩津到さま(以下、舩津さま):
鶴川記念病院では、この豊かな緑がある環境のなかで、患者さま一人ひとりが安心して最適な医療を受けていただくことを大切にしております。
当院は2010年7月に開院した、障害者病棟・医療療養病棟・地域包括ケア病棟からなる総180床の病院です。院内機能は、外来(内科・小児科・リハビリテーション科)訪問診療、訪問看護などの構成になっています。
全職員が一丸となり、住み慣れたこの地域での「自分らしい暮らし」を望む全ての皆さまに、医療・看護を中心とした最善のサービスを提供していく。そして、このエリアの地域包括ケアの中心的存在になるべく、日々努力を重ねています。その一環で前身である鶴川厚生病院を退院後、通院困難な患者さまに対し在宅医療を始めました。
Q訪問診療はどのような体制で運営をなさっているのでしょうか?
在宅支援室 管理者(師長)橋本勝美さま(以下、橋本さま):
現在、当院の訪問診療は「在宅サービス」という枠組みのなかに位置付けています。(2023年11月末現在)
 注釈:在宅サービスの全体像【出典】鶴川記念病院 在宅サービス
注釈:在宅サービスの全体像【出典】鶴川記念病院 在宅サービス
橋本さま:
1995年に開始した「訪問診療」を起点に、「訪問看護」「デイサービス」などのサービスを順に拡充してまいりました。私は、在宅医療を運営する「在宅支援室」に2008年に配属され、2015年から管理者(師長)を務めています。
当院の往診体制は、看護師が患者さまからの連絡を受けるところからスタートします。そして、夜間や休日は、その日のオンコール担当医師に状況を伝えて往診をしてもらうフローでした。
事務部長 金子信之さま(以下、金子さま):
オンコール担当医師のシフト体制は、大学病院から派遣される訪問診療の非常勤医師や、病棟担当の非常勤医師に声をかけて行っていました。当院の場合、医師・看護師ともに24時間365日のシフト調整が発生するので、人材管理担当者の苦労は多くございます。オンコール医師に関しても、特有の課題や悩みがありました。
Qオンコール医師特有の悩みとはどのようなことでしょうか?
橋本さま:
「医師の事情による不意の出来事」が挙げられます。具体的には、「自身が勤務している医療機関の仕事が終わらない」「電話に気づかない」などです。シフトの提出を1カ月前にお願いしていたので、なかには「自分で立てた予定を忘れていた」というケースも発生していました。
医師への電話がいっこうにつながらない時は、患者さまをお待たせしているなかで、「どのように判断をしていいのか…」と苦悩したこともあります。
舩津さま:
あと、当院から「お願い」をしている場合が多いので、その日その医師のコンディションに左右されることもあります。
懇願されて受けた仕事と、自ら望んで引き受ける仕事では、自然と向き合う姿勢に差が生じてしまうものです。日々激務に追われ、長時間勤務を行った後ではなおさらではないでしょうか。
先に橋本が述べた例を含め、決して悪意があるわけではない。すばらしい能力を持つ医師も、ひとりの人間です。そう思うと理解はできるのですが、だからといって患者さまへご迷惑をかけてはいけない。頻繁ではないですが、ある種の葛藤が生まれていたこともありました。
このような出来事を経験しながら、オンコール医師の慢性的な人材不足は課題として残り続けていました。そんな時に、たまたま往診を行う『ファストドクター』を知って興味を持ったのが、コロナ禍に入って少し経過したころだったと思います。
 注釈:鶴川記念病院 病院長 舩津到さま。2009年病院長に就任。常に時流や地域の状況にアンテナを張り、最適な医療の実践を行うために全職員を牽引している。
注釈:鶴川記念病院 病院長 舩津到さま。2009年病院長に就任。常に時流や地域の状況にアンテナを張り、最適な医療の実践を行うために全職員を牽引している。
Qファストドクターに興味を持った理由をお聞かせください。
舩津さま:
たまたま見たテレビ番組で、ファストドクターの往診の様子が取り上げられていて、「このような医療サービスがあるんだ」と初めて知りました。
当時の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、まだまだ実態不明の段階で、医療業界は未知のウイルスによる脅威に直面している最中でした。その状況下で人材を集め、継続的にサービスを提供することは容易ではないだろう・・・と思っていました。
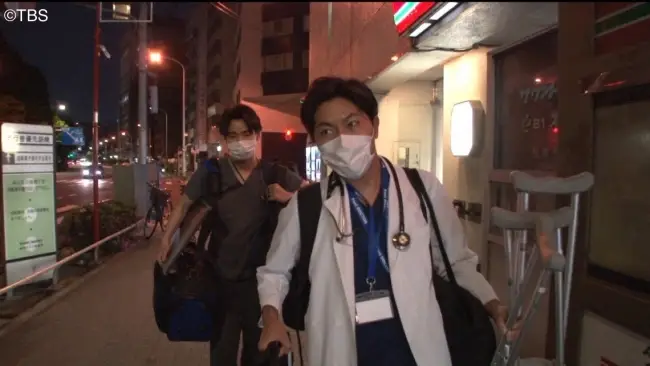 注釈:2019年5月放送TBSテレビ「ビビット」の、ファストドクター1日密着取材時の様子。この他にも、複数のテレビ局からの取材を受けている。
注釈:2019年5月放送TBSテレビ「ビビット」の、ファストドクター1日密着取材時の様子。この他にも、複数のテレビ局からの取材を受けている。
舩津さま:
それからしばらくたって、医療関連の総合展示会の企画で、ファストドクター創業者の話を聞く機会がありました。その時に、「コロナ禍という混乱のなかで、“医者としての己がどれだけ世の役に立てるか”という志を持って参画する人が多い」と話していました。それを聞いて、真摯な姿勢で携わる人が多いのだろう…と感心し、興味を持っていました。
その後に、金子から「ファストドクターというものがありまして…」と、提案される流れにつながっていきます。
▼ファストドクターのサービス内容について知りたい方はこちらをご確認ください
Qお二方が異なる角度からファストドクターを知ってくださったのですね。
金子さま:
私はファストドクター運営側からアプローチを受け、お話しを伺ったのがきっかけでした。
先にご説明した通り、当院では訪問診療での課題がありました。それでも、地域の皆さまのご要望はあったので、しっかりと医師が往診をする体制を確立したいという方針でおりましたが、当時の方法では、患者さまの希望に100%お応えすることは厳しい状況でした。
その課題が、ファストドクターの導入で解決できるのであれば望ましい。当院の在宅サービス発展のためには必要だと感じたので、話を聞いたうえで採用したかたちです。
 注釈:鶴川記念病院 事務部長 金子信之さま。人事管理や財務などの経営面から、地域の皆さまへの貢献度向上を目指して日々従事している。
注釈:鶴川記念病院 事務部長 金子信之さま。人事管理や財務などの経営面から、地域の皆さまへの貢献度向上を目指して日々従事している。
Qファストドクターのリソース活用を開始してから変化はありましたか?
橋本さま:
夜間や休日の往診回数が増加して、今まではお応えできなかったニーズに対応できるようになりました。そして、看護師が行う判断・対応の選択肢が広がったと思っています。
ファストドクターを利用した現在の流れは、まず患者さまからのファーストコールを「在宅支援室の看護師」が受けます。その後、往診が必要だと想定される場合はファストドクターへ依頼をするフローで行っています。
以前は、体調不良を訴える患者さまに対して、わざわざ来院していただき、受診や入院をお願いすることもしばしばありました。これは、症状に対して看護師が判断を迷うケースや、オンコール担当医師のリソース不足などが要因でした。ファストドクター導入後は、患者さまに負担をかけることなく、最適な判断・対応ができるようになったと思います。
舩津さま:
「電話をしてもつながらない」「折り返しのご連絡を失念してしまう」などの不安要素が排除できたわけです。ファストドクターの医師は必ず待機をしているので、管理者は安心できるし、「医師が必ずいてくれる」ことは看護師にとっても大きなメリットです。
キャリアがある優秀な看護師でも、医療的な判断を迷う時はあります。患者さまの生命に関わることですし、プロだからといって完璧に正しく遂行できる自信がある人は少ないと思う。その不安をファストドクターの医師が支えてくれるようになったので、精神的な負担は軽くなりますよね。
▼ファストドクターのサポート医師について知りたい方はこちらをご確認ください
Qファストドクターは看護師の安心材料にもなったのですね。
橋本さま:
そうですね。そして何より「安定した対応」に安心感を持っています。ファストドクターから「到着予定時間」のご連絡を毎回いただくのですが、今まで一度も予定時間を逸脱せずに往診をしていただいています。
自院で運営していた時は医師によってばらつきがあったので、患者さまに正確な情報を伝えることが難しい状況でした。今では、ファストドクターの安定した対応を信頼していますので、自信をもって到着予定時間をお伝えすることができています。
金子さま:
「人材」と「安定」の両方を担保できることは、大きなメリットです。以前はオンコール待機中の時間を含めて、医師の勤怠管理を行う必要がありました。定期的にアンケートを取って、「この先生は当直があるから、あと何日しか当院で勤務ができない」などの情報を加味して人材配置を行わないといけなかった。ファストドクターを使っていればこれらの管理は不要になります。安定した人材確保とともに、業務削減にもつながっています。
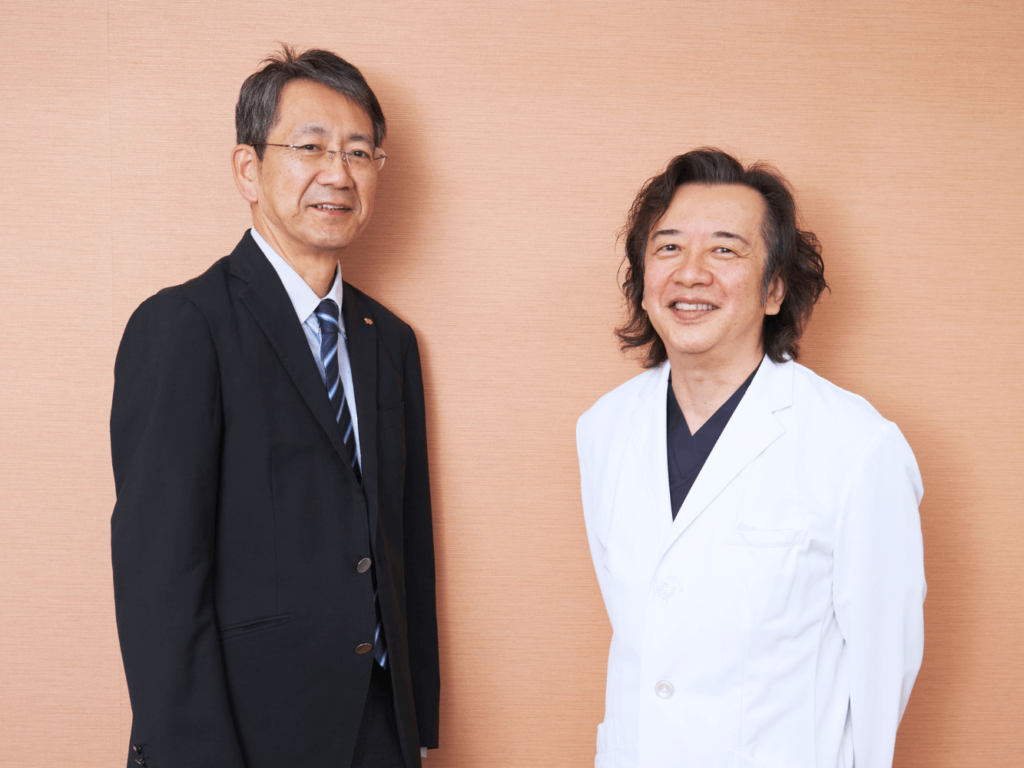
Qとはいえ、以前は課題だった医師の対応についての不安はなかったのでしょうか?
舩津さま:
その心配はしていませんでした。先に述べた通り、ファストドクター創業者のコロナ禍中エピソードを聞いて、不誠実な人間がいるとは思えなかったからです。
人体への影響も不透明ななか、感染リスクを顧みず自らの意志と使命感で挙手した人が集まったサービスですよ。誠実な方が多いと思っていましたし、もし運悪くトラブルになるケースがあったとしても、仲介するファストドクターへ相談すればいい。どちらにしても当院の負担は少ないです。
橋本さま:
ファストドクター導入前一番不安であったのは「情報共有」の部分でしたが、こちら側の要望を細かく確認していて、全て問題なくクリアしてくれています。
医師からの報告記録を見る限り、期待している水準通りの対応をしていただいておりますし、初めて往診対応になった患者さまに対して、じっくり対話をしてくれた医師もいました。ファストドクターは、システムも整っていてマニュアルもきちんとされているのが伝わってくるのも安心です。
▼ファストドクターのサポート体制について知りたい方はこちらをご確認ください
Q今後についてお聞かせください。
舩津さま:
以前は、オンコール担当医師にさまざまな「お願い」をしながらの運営だったので、比較的「守りの訪問診療」でした。ファストドクターを導入することで、そこからの脱却はできたかなと思っています。
信頼できるリソースがあれば、鶴川記念病院の「在宅サービス」としての選択肢が広がります。そういう意味でも、患者さまのさまざまなニーズに対応しやすい土壌づくりができたのではないでしょうか。
高齢化社会が進み、これから在宅サービスのニーズは増えていくでしょう。そこに国も予算を投下する流れでもある。自ら望んで往診に携わる、志の高い医師を抱えるファストドクターとともに、この地域の地域包括ケアをより良いものにしていきたいです。


この記事の著者
関連記事RELATED