三次救急とは?一次救急や二次救急との違いや体制構築のためのポイントを詳しく紹介!
2024.08.06
2025.05.26
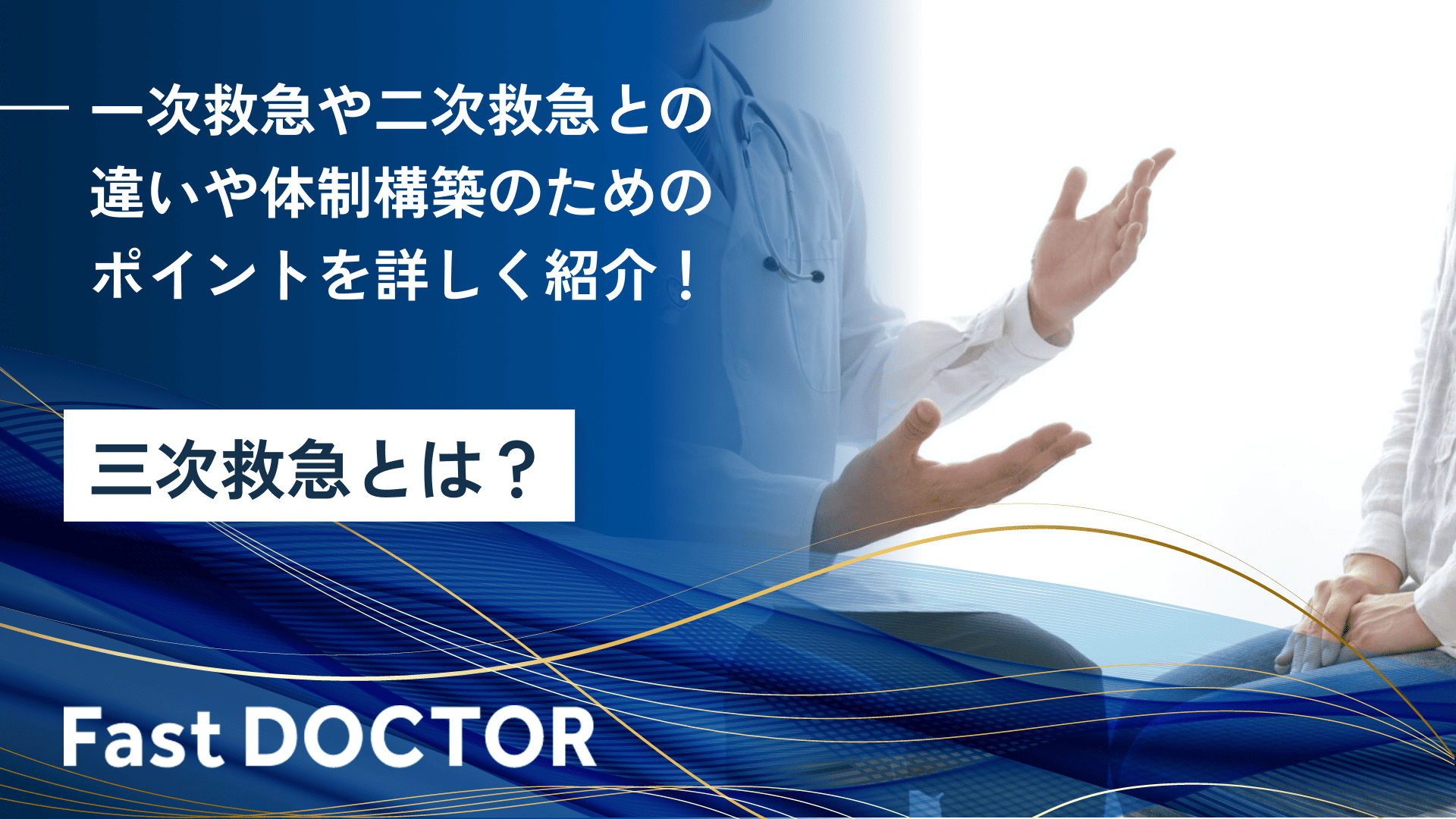

この記事の著者
「三次救急に対応するための体制構築は難しい?」「三次救急のための医療体制構築のポイントは?」
このような悩みを抱えている医療機関も多いのではないでしょうか。
三次救急は、重篤患者に対する医療を行うため高度な専門性を持つ医師の確保や24時間体制などが必要な医療体制です。
本記事では、三次救急に関する基礎知識から医療体制構築のための対策を紹介します。三次救急の指定を受けるための体制構築にお悩みの医療機関はぜひ参考にしてください。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
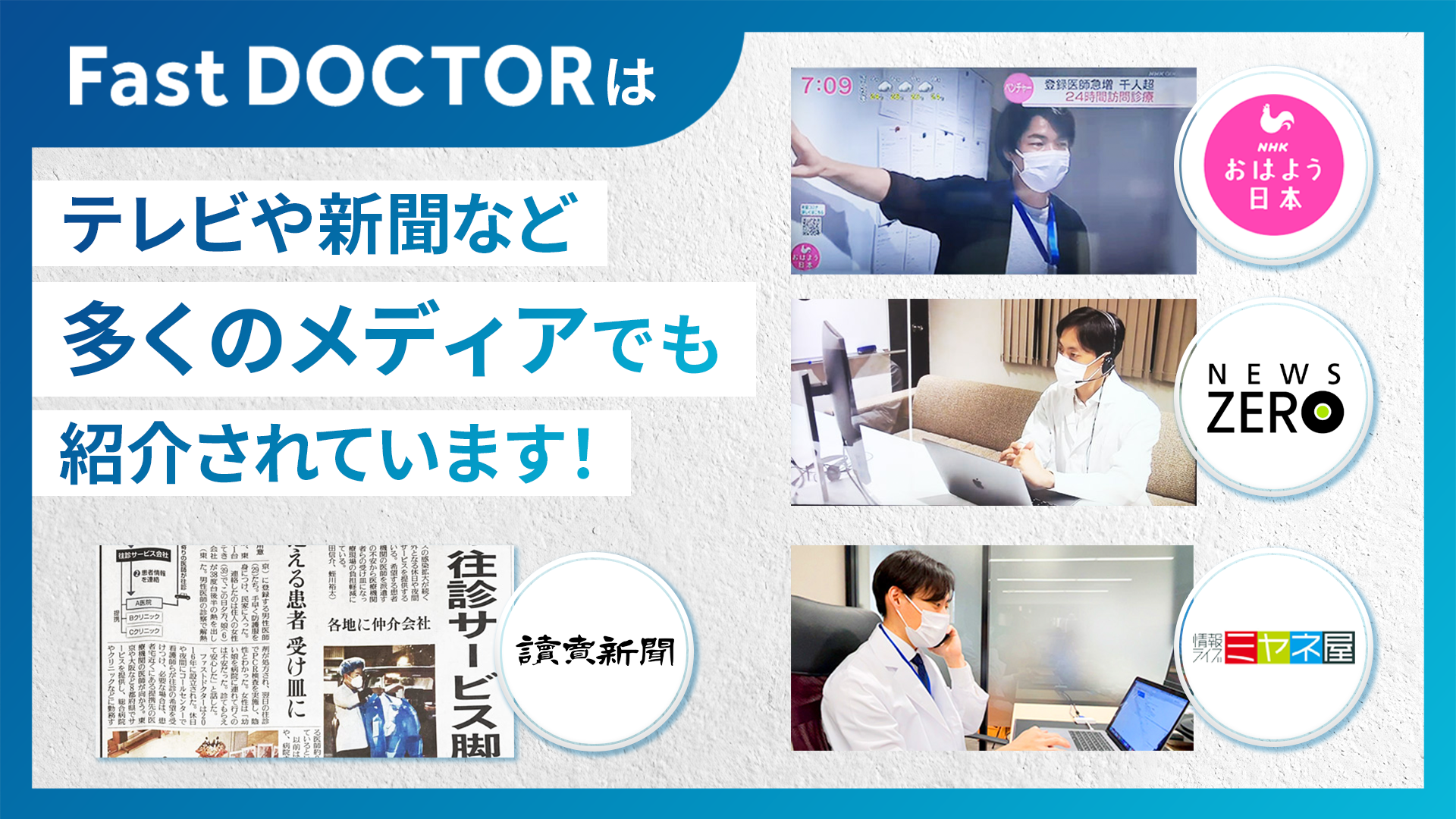
三次救急とは?

三次救急とは、生命に関する重篤な症状の患者に対応する救急体制のことです。
救急医療には一次救急、二次救急、三次救急がありますが、三次救急は救急医療の最後のとりでとなっており原則24時間体制で必ず患者を受け入れることになっています。
まずは、三次救急の基礎知識として以下の2つを紹介します。
- 三次救急の設置要件
- 三次救急医療機関の設置状況一覧
それぞれ確認していきます。
三次救急の設置要件
三次救急の医療体制は、救命救急センターにおいて提供されています。そのため、「救命救急センター」=「三次救急」と捉えてよいでしょう。
三次救急には以下の通り設置要件が決められています。
| 責任者が直接管理する20床以上の専用病床や、集中治療室(ICU)があること併設病院を含む施設が耐震構造であること緊急手術ができるよう、必要人員の動員体制を確立しておくこと(参考:厚生労働省「救命救急センター及び二次救急医療機関の現状」) |
三次救急を提供するためには、施設や人員の確保など体制を整える必要があるのです。
三次救急医療機関の設置状況
厚生労働省は三次救急を提供する救命救急センターを以下の通りまとめています。
(参考:厚生労働省「救命救急センター設置状況一覧」)
救命救急センターに加え、地域救命救急センターや高度救命救急センターも含めると三次救急を提供する施設は全国に300施設以上あります。
現在は、およそ人口42万人に対して1ヶ所、救命救急センターや地域救命救急センターが整備されている計算となります。
一次救急、二次救急との違いとは?

救急医療は、患者の重症度や緊急性に応じて一次救急・二次救急・三次救急と段階に応じた体制が確立されています。
三次救急と一次救急・二次救急の違いを理解するためにそれぞれ確認していきましょう。
一次救急は自力で受診できる比較的軽症な患者への対応
一次救急は、自力で医療機関に訪れて診察を受けられる比較的軽症な患者への対応となります。
休日や夜間などで近くの医療機関が営業をしていない時間帯で重症ではないものの診察を先送りできない患者に医療を提供します。
入院や手術をともなわないため、患者は診察を受けた後に車やタクシーなどで帰宅します。
二次救急は入院や手術が必要な患者への対応
二次救急は、手術や入院が必要な患者に対応する救急医療です。
二次救急を提供するためには、24時間体制で患者を受け入れる体制が必要となります。
一般的に救急車を呼んだ場合は、二次救急を行う医療機関に搬送されます。
三次救急の体制構築が難しいと言われる理由

三次救急は設置要件が定められており、多くの医療機関で体制構築が課題とされています。ここでは、三次救急の体制構築が難しいと言われる主な理由を2つ紹介します。
- 重篤患者に対して24時間体制での高度な医療提供が求められる
- 医療スタッフの心理的なストレスが高まる
それぞれ確認していきます。
重篤患者に対して24時間体制での高度な医療提供が求められる
三次救急は、重篤患者に対する高度な医療知識をもった医療スタッフを24時間体制で構築しなければなりません。
三次救急を行う医療機関は、日中帯の外来や入院患者へのケアなどさまざまな業務に対応している場合がほとんどです。
そのため、それぞれの業務に医療スタッフを配置しながら三次救急に向けて体制を構築する必要があります。
医師不足が叫ばれる現代で、さまざまな業務を行うなかで三次救急の体制も構築していくことは困難です。
医療スタッフの心理的なストレスが高まる
三次救急は生命に関わる重篤患者に対応しなければならないため、医療スタッフの心理的なストレスが高まりやすくなります。
重篤患者のなかには、重度の外傷や大量出血など外見に変化が生じている患者も少なくないため、重篤患者の状態にショックを受けてしまい精神的に負担がかかる場合があります。
その結果、医療スタッフの離職者が増加してしまい、体制構築が難しくなるのです。
三次救急の体制構築には人手の確保が必須

三次救急は、24時間の医療提供や専門性の高い医師の配置など体制構築のために人手の確保が必要です。
しかし、三次救急に対応するための人手確保がうまくいかない医療機関も少なくありません。
人手不足のまま三次救急に対応していると業務負担により、医療スタッフはさらにストレスが高まり離職につながる恐れがあります。
医療業務の代行サービスの利用で体制構築
三次救急に向けた体制構築には、代行サービスの利用がポイントです。
医療機関で提供しているさまざまな医療サービスを代行会社に依頼することで、医療スタッフ1人ひとりの業務負担の改善につながり三次救急の体制構築が可能となります。
夜間のオンコールなど外注化できる医療業務を代行会社に依頼することで、医療スタッフの業務負担改善や医療スタッフの人員確保ができ三次救急に向けた体制構築が可能となるでしょう。
三次救急に対応した体制構築を進めよう!

本記事では、一次救急や二次救急と三次救急の違いや体制構築のポイントを紹介しました。
三次救急は24時間体制の医療体制や重篤な患者に対応するための専門性の高い医師の配置など体制構築が必要となります。
人手不足に悩みを抱える医療機関は医療業務の代行サービスを利用することで、医療機関内の業務負担の削減につながります。その結果、三次救急に向けた人員の確保につながり、体制の構築が可能となるでしょう。
質の高い医療提供ができるように、三次救急に対応した体制構築を進めましょう。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
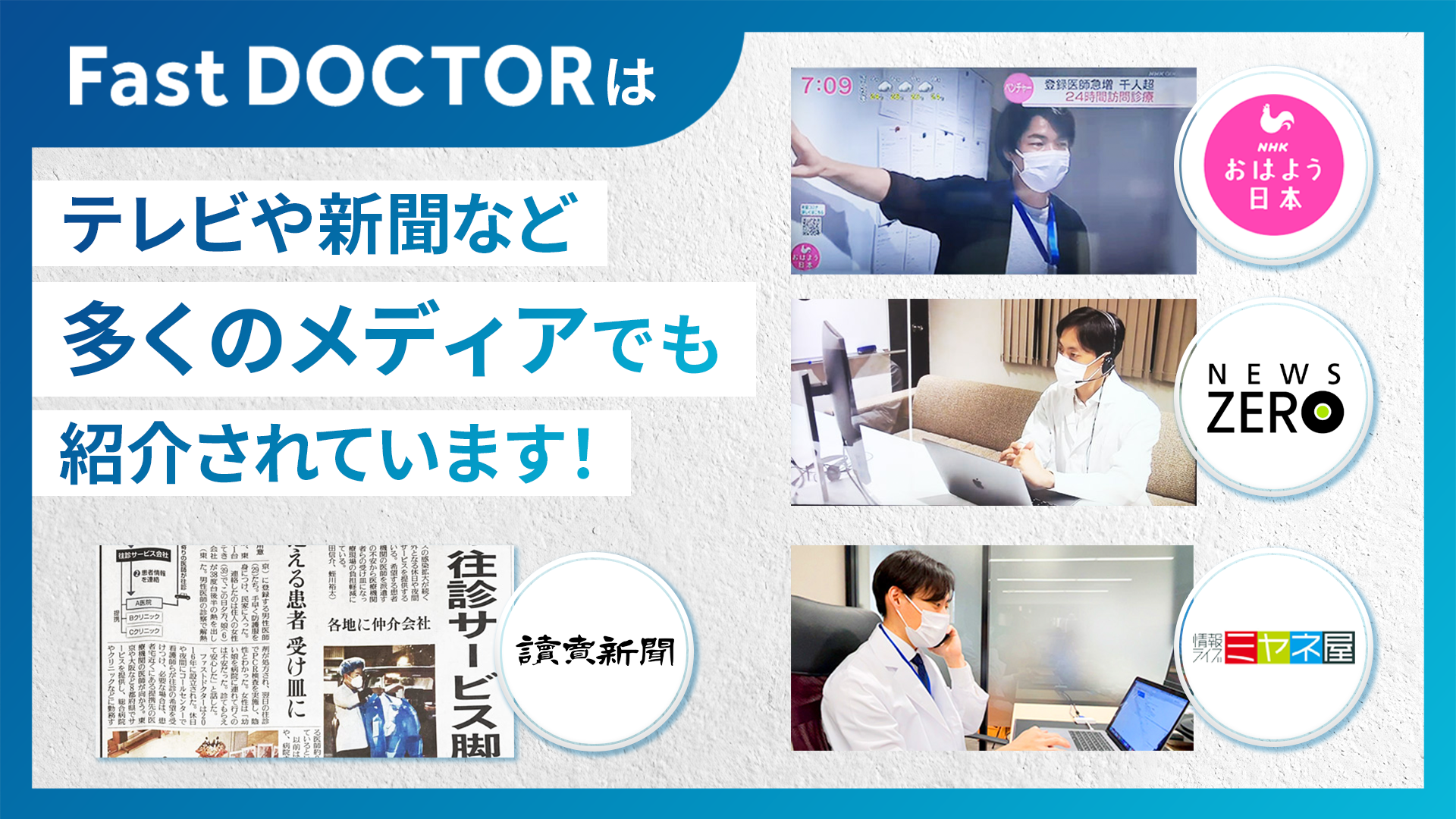


関連記事RELATED







