医療業界における人手不足の現状|5つの原因や解決策などを徹底解説
2024.08.06
2025.05.26


この記事の著者
「医療業界の人手不足の原因はどこにある?」「人手不足に対する解決策が知りたい」
上記のような悩みを抱えている人は少なくないでしょう。
医療業界の人手不足は、慢性化していると言われていますが、少子高齢化やウイルス感染症の影響などによって医療需要は今後も高まっていくため、早期解決が求められています。
人手不足を解消するためには、その原因を把握して正しい対策を打つ必要があるでしょう。
そこで本記事では、医療業界の人手不足に関する現状や原因を厚生労働省のデータを用いて分析し解決策について解説します。
人手不足で悩んでいる医療機関の方は、ぜひ参考にしてください。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
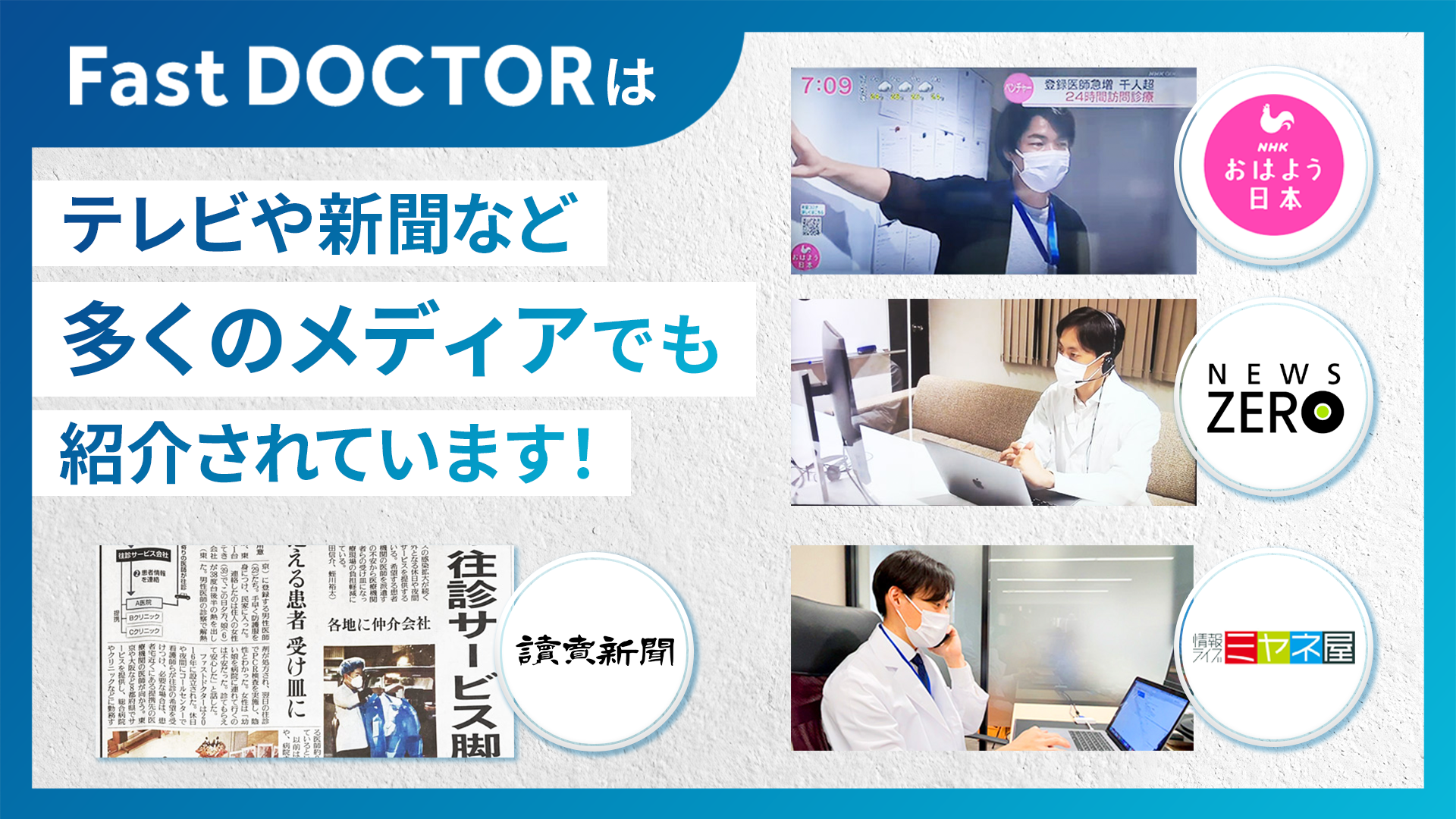
厚生労働省のデータからわかる医療業界の人材不足問題の現状

本項では、医療業界における人手不足について、厚生労働省が発表している一般職業紹介状況(職業安定業務統計)のデータを基に詳しく解説します。
厚生労働省のデータからわかる医療業界の人材不足問題の現状は大きく分けて、以下の2つです。
- 医師や看護師の人材不足が深刻化している
- 医療業界全体の離職率が増加している
医師や看護師の人材不足が深刻化している
厚生労働省によると、2023年の看護師(保健師・助産師含む)の有効求人倍率は、1.81倍です。
参考:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和5年6月分)について」
有効求人倍率は、一般的に1より数値が大きいと「人手不足」、1より小さいと「人余り」とみなされます。
つまり有効求人倍率1.81倍とは、募集に対して半分か、それ以下の人数しか応募がないということです。
これにより、医療スタッフの人材の供給が追いついていないため、人手不足が進んでいると分かるでしょう。
医療業界全体の離職率が増加
医師や看護師の人手不足には、医療業界全体における離職率の増加が大きく関わっていることが、厚生労働省の発表によりわかっています。
厚生労働省の資料によると、令和2年中の医療・福祉業界における離職率は14.2%であり、この数値は全業種でトップクラスの離職率です。
また公益社団法人日本看護協会によると、正規雇用看護職員の離職率は11.6%、既卒採用者の離職率は16.8%と高い傾向にあります。
つまり、人材育成に注力しても離職してしまう人も、他業界と比較すると多いという実態があるため、人手不足問題は一向に解消されなくなってしまいます。
医師や看護師が人手不足問題に陥っているのはなぜ?

前述の通り医療業界では他業界より離職率が高く、特に医師や看護師は問題になっています。
医療業界が人手不足問題に陥るのには、主に以下3つの理由が挙げられます。
- 医療技術向上による専門性の高い人材への需要増加
- 勤務形態が変則的
- 業務負担が重い
医療技術向上による専門性の高い人材への需要増加
近年では医療技術の向上により、高度な医療技術を身につけた専門性の高い人材への需要が高まっています。
需要増加の理由は少子高齢化の影響に伴い、急性期医療や介護医療、訪問看護の需要が増加していることが挙げられます。
結果、専門性を有する医療スタッフの需要増加が、医師または看護師の人手不足の原因の一つに挙げられます。
勤務形態が変則

人手不足問題が医療業界で起こる原因には、「勤務形態が変則的」が挙げられます。
例えば、夜勤を行う看護師は3交代制・2交代制のシフトが組まれる場合が多く、結果として医療従事者自身の生活リズムが不規則になりがちです。
特に子育てをされている方や介護をしている方は、夜勤が難しくなるため、日勤中心のシフトを希望する場合も少なくありません。
夜勤の看護師が減少すれば、それだけ夜間帯に働く医療スタッフ1人あたりの負担が増えます。
そのため、仕事とプライベートの両立が取れず離職を考える人もいるでしょう。
また夜勤時は、日勤よりも看護師の配置が少ないため、ナースコールに対して少人数での対応になる場合がほとんどです。
救急患者の受け入れや容態が急変した患者の対応によっては、休憩時間を短縮せざるを得ない場合もあります。
業務負担が重い
ほかにも、医療現場で人材不足が発生する原因には、「業務負担が重い」という理由が挙げられるでしょう。
医療現場では、夜勤があったり患者の急変対応をしたりするため、勤務時間が不規則で健康に支障をきたす可能性があります。
また、救急搬送患者を受け入れた場合は、他の患者への対応が遅れる場合もあり、毎日バタバタしている状況にストレスを感じて離職してしまう方が少なくありません。
さらに、患者への薬剤投与や看護ケアなど、患者の健康や命に関わる業務が多くあるため、ミスは許されません。
結果、業務の幅広さや責任の重さが離職の原因につながり、医療現場は人手不足に陥る傾向があるのです。
人手不足が進行すると起こり得る弊害

医師や看護師の人手不足が解消されない場合どうなるのでしょうか。
人手不足により起こりうる弊害は、主に以下の2つが挙げられます。
- 医療サービスの品質低下
- キャリアアップの難航
医療現場に影響を与える弊害を理解することで、人手不足に対し適切に手を打てるでしょう。
医療サービスの品質低下
医療現場の人手不足が進行すると医療サービスの品質が低下するといった弊害が考えられます。
厚生労働省が2008年に発表したデータでは、病床あたりの看護師数が多くなるほど患者の安全性が高まるとされています。
つまり、医療現場の人手不足は、業務負担の増加による医療ミスや重大な医療事故を引き起こす原因となり、患者に安全な医療を提供できなくなるでしょう。
キャリアアップの難航
人手不足が進行する医療現場では、キャリアアップが難航するという弊害が考えられます。
理由は、人手不足が原因で医療スタッフの業務が増え、キャリアアップのための勉強時間が取りにくくなる傾向があるからです。
スキルを身につける時間が確保できないと、希望する診療科への異動が難しくなり、キャリアアップも難航するでしょう。
医療業界における人手不足の対策・解決策

医療業界の人手不足を解決するといっても、実際にどのような取り組みがあるかわからないケースは少なくありません。
ここでは、医療業界における人手不足の対策・解決策として、以下の4つを紹介します。
- 福利厚生や労働時間などの労働環境を改善
- 賃金の向上
- キャリアアップの支援体制の充実
- ITツールを使用した業務の効率化
各対策・解決策を参考に、ぜひ人手不足に向けてできることがないかを検討してみましょう。
福利厚生や労働時間などの労働環境を改善
人手不足問題を解決するには、スタッフを雇う医療機関側が、福利厚生の見直しや労働環境の改善を行うことが重要になります。
福利厚生の充実(以下に例示)は、看護師のモチベーション維持や離職率低下につながります。
- 特別休暇の設置
- 院内託児所の設置
- 時短勤務の導入
福利厚生や労働時間などの労働環境を整えることで、働きやすい現場となり、定着率の向上につながります。
これにより、ライフスタイルの変化を理由にキャリアを諦めなければならなかった医師や看護師も、長く働き続けられるでしょう。
賃金の向上
夜勤手当や残業手当など給料を増やすことにより、業務負担と報酬のバランスを取りやすくなります。結果として医師や看護師のモチベーションの向上が期待できます。
そもそも有効求人倍率の高い現状のなか、低い賃金の医療機関を選択する人は多くありません。
賃金の向上は既存の医師や看護師の定着率アップのほか、新規採用の看護師の確保にもつながるでしょう。
キャリアアップの支援体制の充実

人手不足を理由に、医師や看護師の業務は年々激務化しており、その結果、新人育成を行うのが厳しい状況です。
人手不足が続くと、新人看護師にも責任の重い業務を担当させることになってしまうため、不安を抱える人もいるでしょう。
そのためキャリアアップの支援体制を充実させることは、医療機関全体のサービスを向上させるために重要です。
代表的なキャリアアップの支援対策は、主に以下のようなものがあります。
- 資格取得支援
- eラーニングの導入
- キャリア養成支援制度の導入
スキルが身に付けば希望診療科への異動など、キャリアアップも可能になり、モチベーションの向上にもつながるでしょう。
ITツールを使用した業務の効率化
医療現場にITツールを導入すれば、業務の大幅な効率化が可能です。
ITツールを使用した業務の効率化には、以下のようなものがあります。
- カルテ記入や病棟管理などの業務をデジタル化
- 医療ロボットなどの機器を導入
紙カルテから電子カルテに切り替えることで業務量を大幅に削減でき、入力ミスを減少できます。
また、医療ロボットやAIの活用により、医師や看護師の業務負担が軽減できれば定着率が向上し、人手不足問題の解決策になるでしょう。
医療業界の人手不足に関するよくある質問

医療業界の人手不足に関するよくある質問を整理しました。それぞれ詳しく見ていきましょう。
医療業界の人手不足はいつから始まっているのでしょうか?
看護師に関する有効求人倍率(2017〜2021年)は、1.91倍〜2.33倍と2倍前後を推移しています。職業計と比較して高い倍率となっており、その時期から医療業界の人材不足が始まったと考えられます。
下表は、2017〜2021年における「保健師、助産師、看護師」の有効求人倍率と、職業計での有効求人倍率の推移をまとめたデータです。
| 保健師・助産師・看護師 | 職業計 | |
| 2017年10月 | 2.33 | 1.41 |
| 2018年10月 | 2.28 | 1.49 |
| 2019年10月 | 2.23 | 1.45 |
| 2020年10月 | 1.91 | 0.97 |
| 2021年10月 | 2.11 | 1.06 |
日本は超高齢社会に突入してなお高齢者人口の増加が進んでおり、看護師の需要は今後も高まるでしょう。
看護師の需要が高まる一方で、供給が追いついていないため、人手不足は続くと予測されています。
そのため、福利厚生や賃金などの改善やITツールの導入がより一層、重要になるでしょう。
医療現場の人手不足の問題点はどこにあるのでしょうか?
問題点としては、医療ミスや医療事故につながる危険性が挙げられます。
先述の厚生労働省が発表した資料からもわかるように、病床あたり看護師数が多ければ多いほど、患者の安全性は高くなるのです。
そのため、人手不足が進行すると、医療サービスの質が低下したり、重大なミス・トラブルを招く危険性が高まります。
医療業界の人手不足は慢性化しており早急に対策が必要
本記事では、医療業界における人手不足に関する内容を解説しました。
結論からいうと、人手不足の対策として、労働環境の改善やIT導入による業務効率化を行うことが必要です。
一度、現状の労働環境を把握することでスタッフの業務負担における原因が見つかる可能性があります。
人手不足に陥っている医療機関は、原因を追求し、改善できるように労働環境を改善したりITツールを使用したりなど、現場スタッフの負担を軽減できる工夫を行いましょう。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
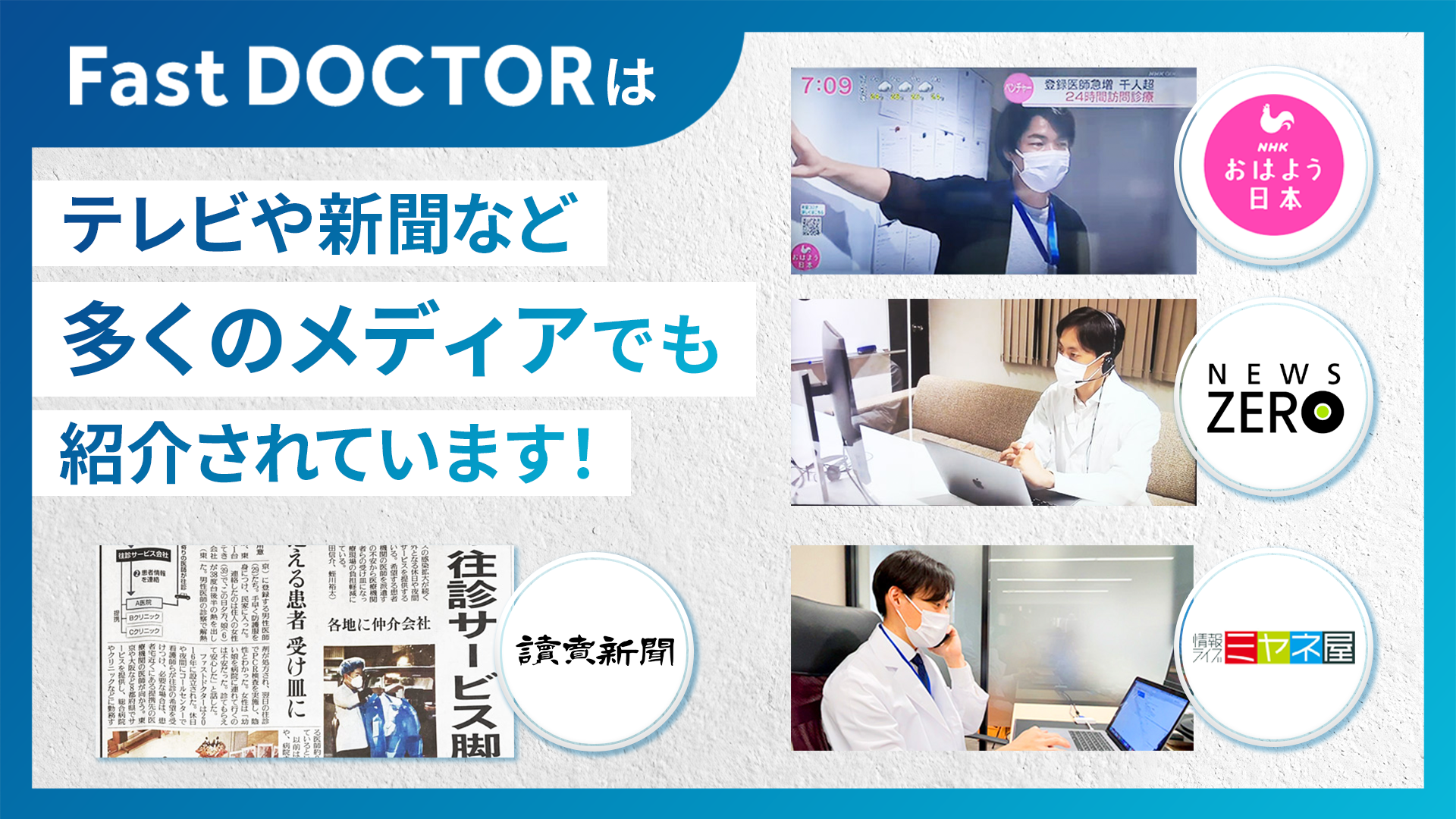


関連記事RELATED







