医師が知っておくべき「看取りの手順」と在宅医のあり方
2024.08.06
2025.05.26
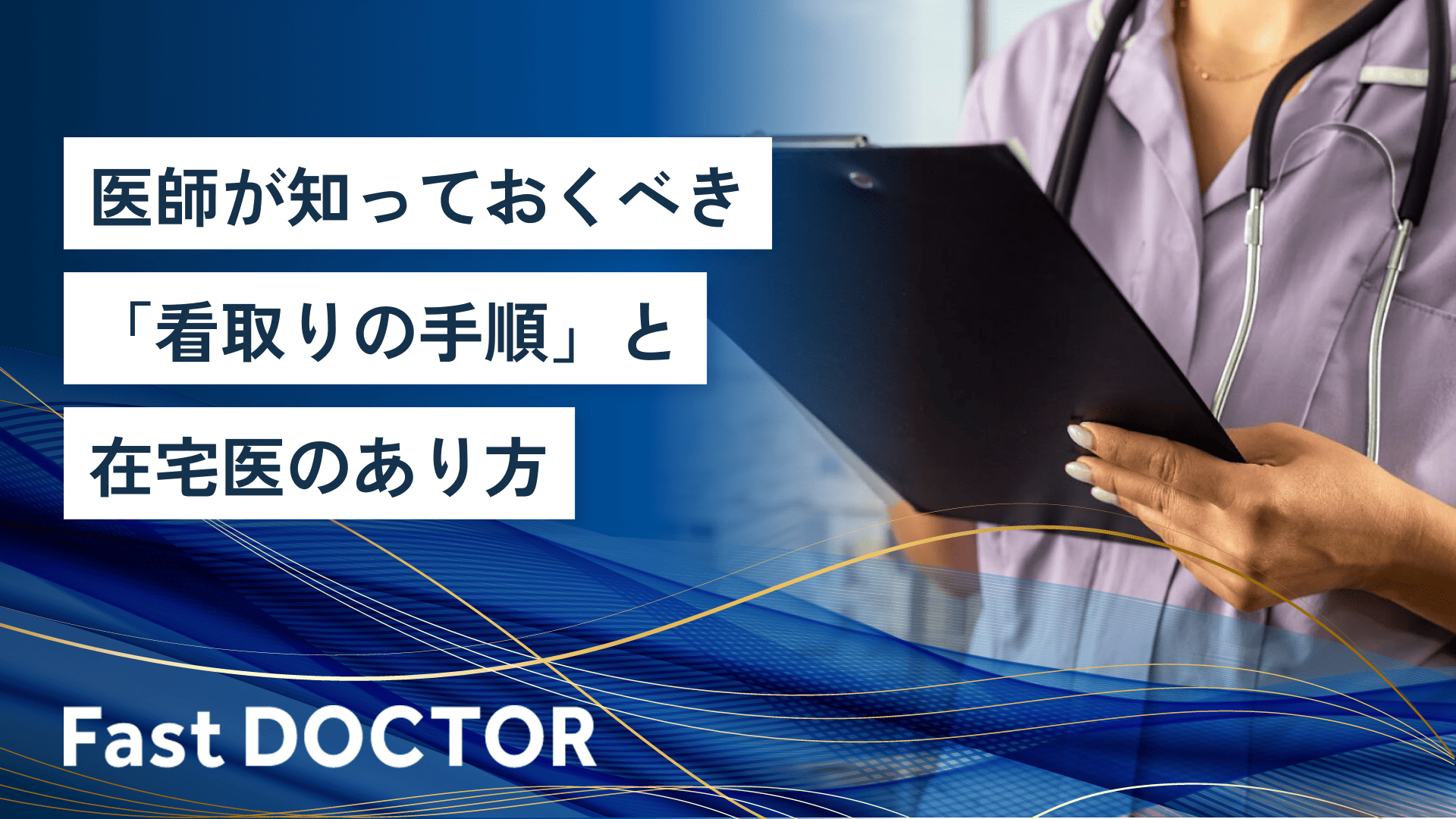

この記事の著者
「看取りの際、死亡確認を家族にどう伝えたらいいか」「死亡診断の際の家族に対する声かけやマナーは?」
看取りに立ち会う際にこのような悩みをお持ちの医療従事者の方もいらっしゃると思います。
本記事では、看取りの際の立ち居振る舞いや医師が家族に対して心がけるべきことを、厚生労働省の看取りガイドラインを参考に解説します。
患者が在宅で最期を迎えることを希望されていた場合の看取りの手順も解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
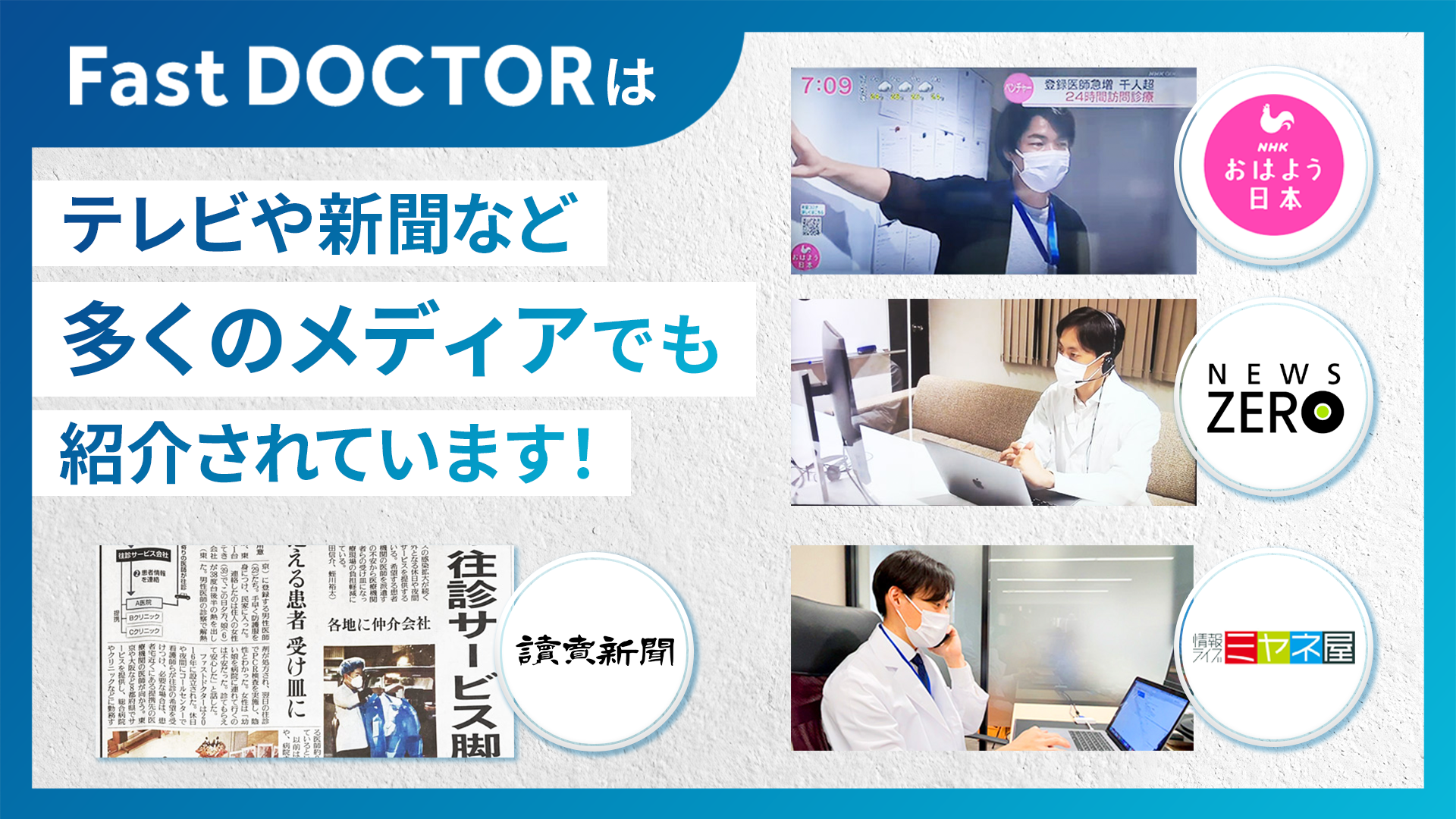
厚生労働省の看取りガイドラインとは

看取りに関して明確な指標がないという課題を解決するために、平成19年に『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』が厚生労働省によって作成されました(平成30年改訂)。
ガイドラインでは、患者の合意を前提にしたうえで、人生の最終段階における医療のあり方を医療・介護従事者に向けて解説しています。
本記事ではこのガイドラインの内容を要約し、看取りの手順や段取りをわかりやすく解説します。
参考:
・厚生労働省|人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン
看取りに対して意思決定をする状況判断とは

人生の最終段階における意思決定においては患者本人の意向が最優先ですが、病状や進行状況によっては患者と意思疎通できない場面も起こりえます。
人生の最終段階においては、以下のように状況別に看取りの段取りや適切な医療ケアを考える必要があります。
- 本人の意思確認ができる場合
- 本人の意思確認ができない場合
本人の意思確認ができる場合
本人の意向を尊重するのが基本です。医療従事者の知識が必要となった場合、医療チームが患者の状態を判断しながら、最適なケアを施します。
また、本人の意思を確認できていても、容体が急に変化する場合もあるため、本人の意思が確認できなくなった場合の対応について家族と話し合っておくことが大切です。
本人の意思確認ができない場合
看取り前の意思確認では、患者の病状により本人と意思疎通が取れない場合があります。
その場合、家族や親族など患者に近い存在である方が本人の意思を推定しながら段取りを決定します。
家族の判断で決定する場合、医療ケアに関わる相談に対して医療従事者がアドバイスを行い、家族の判断を尊重するように心がけましょう。
また、患者に家族や親族がいない場合には、過去の事例をもとに、患者にとって最善と考えられる看取り方を医療チームが推定し決定します。
看取りの方針について複数の専門家からなる話し合いの場を設置する場合もある
治療プロセスを決定するとき、必ずしもスムーズに進まないことも考えられます。
- 本人または家族と、医療・ケアチームの意見が合意しない場合
- 家族の意見がまとまらない場合
上記の場合には、複数の専門家により話し合いの場を設置し、医学的妥当性を踏まえてベストな提案をしたうえで、本人や家族に最終判断をしてもらいましょう。
複数の専門家とは、国が行う「本人の意向を尊重した意思決定のための研修会」の修了者や、担当医以外のカンファレンス参加者などが挙げられます。
医師が看取りの時に配慮すべき3つのマナー

看取りの前後には、家族への精神的なケアを最重要に考えることが医師に求められており、主に以下の3つが重要な項目として挙げられます。
- 患者の家族が悲しむ時間を大切にする
- 患者の家族へねぎらいの言葉をかける
- 患者の家族の負担になる言動は避ける
看取りの際に、家族に対して医師が不適切な行動をとってしまわないように、それぞれのポイントを確認しましょう。
患者の家族が悲しむ時間を大切にする
患者が亡くなったからといって、淡々とやるべきことを進めるのはNGです。
医師には、書類の整理などの事務的な役割以外に、家族に精神的なケアを行うことが求められます。
また、死亡確認後の手続きの段取りに関して、書類の手続きを進めるタイミングについて、看取り前に親族との面談であらかじめ決めておくとよりスムーズに対応できます。
患者の家族へねぎらいの言葉をかける
家族に別れの時間を設け、必要に応じて医師から家族の方へねぎらいの言葉をかけてあげましょう。
家族の方は、生前の様々な対応について自身の選択が本当に正しかったのかという迷いや後悔を抱くことが少なくなく、また、看病や介護で疲労を感じていた方の場合は、さまざまな感情が込み上げてくることもあるでしょう。
家族の心が安らぐ言葉をかけることによって家族にとっても納得感のある看取りになります。
患者の家族の負担になる言動は避ける
家族の方の気持ちを少しでも和ませるために、無理して言葉を絞り出す必要はありません。
特に、ネガティブな意味合いが含まれる話題は持ち出さないようにしましょう。
家族の方も過去の選択に後悔することも多いため、最善の選択であったとフォローする姿勢や言葉かけが医師に求められます。
【状況別】医師が家族に対して心がけるべきこと

遺された家族へのケアも医師にとって重要な仕事だと解説しましたが、ケアの方法は状況によってさまざまです。
- 看取りの準備段階
- 死亡確認前の立ち会い
- 死亡確認時
- 死亡確認後
ここからは、状況別に患者や家族に対するケアの方法や心がけるべきことを解説します。
看取りの準備段階
家族がきちんと患者とお別れの瞬間を迎えることができるよう、わかりやすい言葉で説明をすることが大切です。
患者の状態や予後は、本人や家族を前にして言いづらい部分もありますが、医療従事者として正確に現状を伝えましょう。
今後考えられる医療ケアや、最悪の場合の対応などをあらかじめ説明することで患者や家族に安心感を与えると同時に、トラブルの回避にもつながります。
死亡確認前の立ち会い
亡くなる直前は、患者と家族の最後の時間となります。
家族にとって悔いの残らない看取りとなるように、医師・ケアチームは家族の時間を最優先し、静かにその時を見届けましょう。
患者や家族の質問や呼びかけには、医療従事者として的確な受け答えをしつつ、自分から進んで話しかけることは控えましょう。
また、信仰している宗教などによって、看取りの瞬間に求めることが異なるので、看取り方を事前に確認することが重要です。
死亡確認時
お別れの時間を邪魔しないようにプライベートな空間を作り、明確な言葉で患者が亡くなられたことを伝えましょう。
また、家族が介護を親身にされていた場合には、ここでねぎらいの言葉をかけましょう。
家族が望む場合には、死亡確認後は必要であれば医療チームは部屋から一度退出して、家族だけの時間を大切にします。
ここでも、医師から言葉をかけられることを求められていない方もいらっしゃるので、質問や相談を投げかけられた場合のみ言葉をかけるなど、必要に応じて対応しましょう。
死亡確認後
看取り後の手続きなどは、あらかじめ家族の方と決めた段取りに沿って、医師が率先して行いましょう。
家族は患者との別れを頭では理解していても、実際に亡くなられた後は気が動転していることがほとんどです。
事前に看取り後の段取りを準備していても、今後どのように進めていけばいいのかわからなくなってしまう方もいらっしゃいます。
葬儀サポートや家族の方の精神面のサポートが必要な場合には、適切な機関の連絡先の共有も必要です。
在宅医療での看取り方

近年、余命を宣告されてからの時間を自宅で過ごしたいと希望される方も増えています。
病院や施設で過ごすのではなく、在宅医療で家族と最期の時間を過ごしたい方の看取りの段取りを解説します。
在宅医療で看取りを行う際のポイントには主に以下の3つが挙げられます。
- 本人と家族の希望や思いを確認
- 今後の準備事項を相談
- 在宅看取り時の連携・対応
本人と家族の希望や思いを確認
看取りの際の選択肢として、万全のケアが可能な医療機関で行うか、住み慣れた環境で最期の時を迎えるか、といったことが考えられます。
医療ケアチームは、それぞれのメリット・デメリットを正確に説明したうえで患者とご家族に確認しましょう。
特に、24時間対応の医療機関であっても、容体が急変した際に必ずしも担当医が駆けつけられない場合があることについて、事前に理解を得ておく必要があります。
今後の準備事項を相談
患者・家族の希望で在宅での看取りをする場合には、今後の準備や相談事項をきちんと話し合っておくことが大切です。
- これから起こり得る症状と、それに対する治療やケア
- ファーストコールを誰にするか(看護師や医師など)
- 主治医が外出等で不在の場合の対応
- 看取りが夜間・休日になる場合の対応
これから起こりうる症状のケアが在宅医療で可能であるか、などの医療チームからしか提供できない情報は必ず説明しておきましょう。
容体が急変した時に対応可能な人員を確保できていると、患者や家族に安心感を与えられます。
在宅看取り時の連携・対応
在宅医療での看取りは、医師・ケアチーム・家族との連携が重要となってきます。
看取りのタイミングが予想はできても、実際にいつ看取りの時が来るかはわかりません。
看取りが24時間どのタイミングで訪れても対応できるよう、医師だけでなく、ケアチームも含めて密な関係を築き、いつでも連携が取れる状態にしておくことが重要です。
厚労省が看取りのガイドラインを作成・改訂した背景

前述の通り「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」は厚生労働省によって平成19年に作成され、その後平成30年に改訂されています。
看取りに関するガイドラインが作成された背景や改定が行われた理由を紹介します。
ガイドラインが作成された理由
人生の終末期における医療の選択や方針については、長年にわたり医療現場での重要な課題として扱われてきました。1987年以降、厚生労働省はこの問題に関する検討会を複数回開催し、議論を重ねてきました。
その一方で、国として具体的なガイドラインを制定することに対しては慎重な姿勢を取り続けていました。その背景には、「終末期医療に対する国民の意識の変化」や「患者一人ひとりの状況や周囲の環境が多様であること」が影響していました。
現在のガイドラインが作成された背景としては、2007年に至り、患者と医療従事者の間で合意できる「終末期医療のあり方」が確認され、いよいよ基本的なガイドラインが策定が進められることとなったのです。
ガイドラインが改訂された理由
平成27年3月に、終末期医療に関する意識の変化を背景に、「終末期医療」という用語が「人生の最終段階における医療」に改められました。
これは、個人の価値観や生き方を最大限に尊重する医療の提供が求められるようになったためです。加えて、平成19年に制定されたガイドラインから10年が経ち、高齢化が進む中で在宅や施設での看取りや療養の需要が増加し、それに対応するための地域包括システムの整備が進みました。
また、同時期は海外にて「Advance Care Planning(ACP)」と呼ばれる、本人と医療チームや家族が人生の最終段階における医療・ケアについて前もって繰り返し話し合うプロセスが普及しつつありました。このような背景から、日本でもそのような取り組みが注目されガイドラインの改訂が進められたのです。
ガイドラインの改訂の3つのポイント
このような背景を受けて、平成30年には「人生の最終段階における医療の普及・啓発に関する検討会」が行われガイドラインの内容が見直され、新たな解釈が追加されることになりました。具体的な変更点は以下の3つです。
|
1)個人の意思は、時間とともに変わり得るものであるという認識のもと、繰り返し医療やケアの方針について話し合うことが重要であるとされました。 2)本人が自らの意思を表明できない状況に備えて、本人の意向を理解できる信頼できる家族などを選定し、その人たちと繰り返し協議することの必要性が強調されました。 3)医療提供場所を病院だけでなく、介護施設や在宅など多様な環境でのケアを含む内容へと拡充することが求められました。 |
さらに、ガイドラインは「人生の最終段階における医療・ケアに携わる医療・介護従事者がその段階にある本人や家族を支援するための指針」であることが示されました。
改訂後のガイドラインでは個人や家族との対話を繰り返し行うことを通じて、個々の尊厳を保ちながら人生の終焉を迎えるための医療・ケアの重要性が強調されています。
事前に看取りの際の段取りについて親族と話し合うことが重要

本記事では、看取りに対する状況判断や医師が家族の方に対して心がけるべきことを紹介しました。
看取りは、患者と家族がお別れをする最期の時となるため、安らかな環境を提供することが求められます。
医療チーム側は過度な干渉や言葉遣いには注意して、医学的な観点から的確に求められる情報を伝えましょう。
また、最近では在宅で看取りを希望される方も増えているので、緊急時にサポートできる体制を整えておきましょう。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
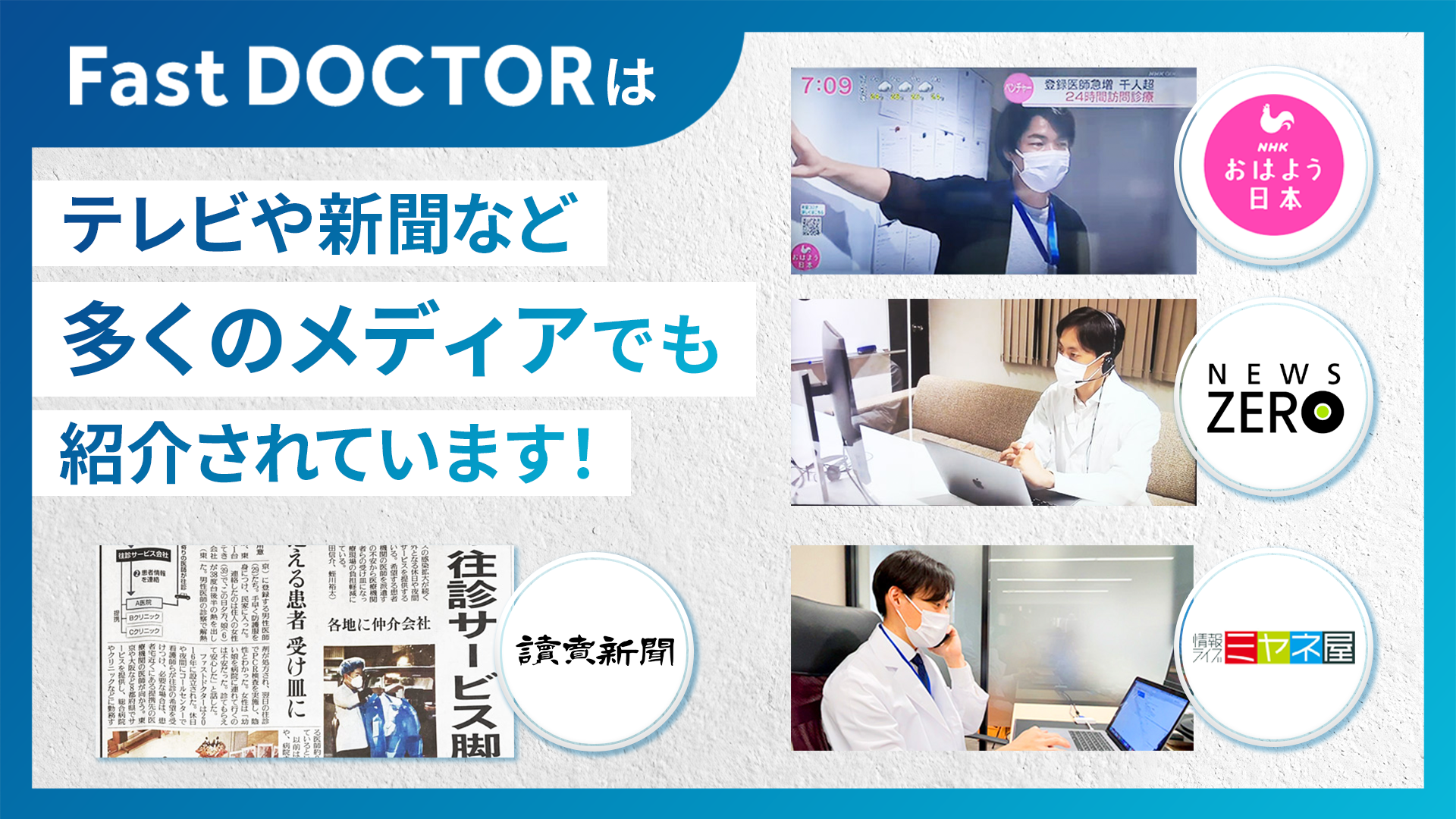


関連記事RELATED







