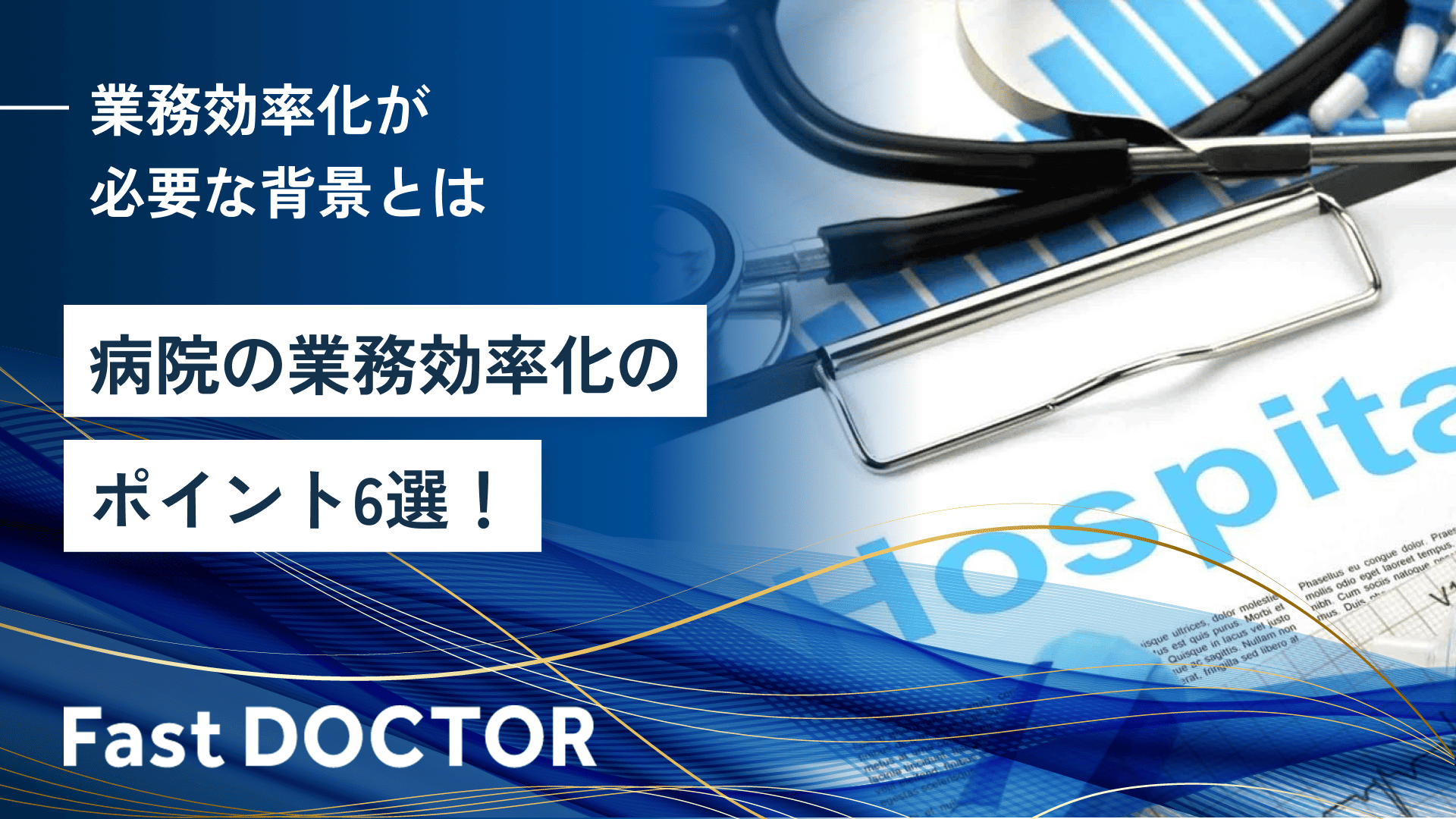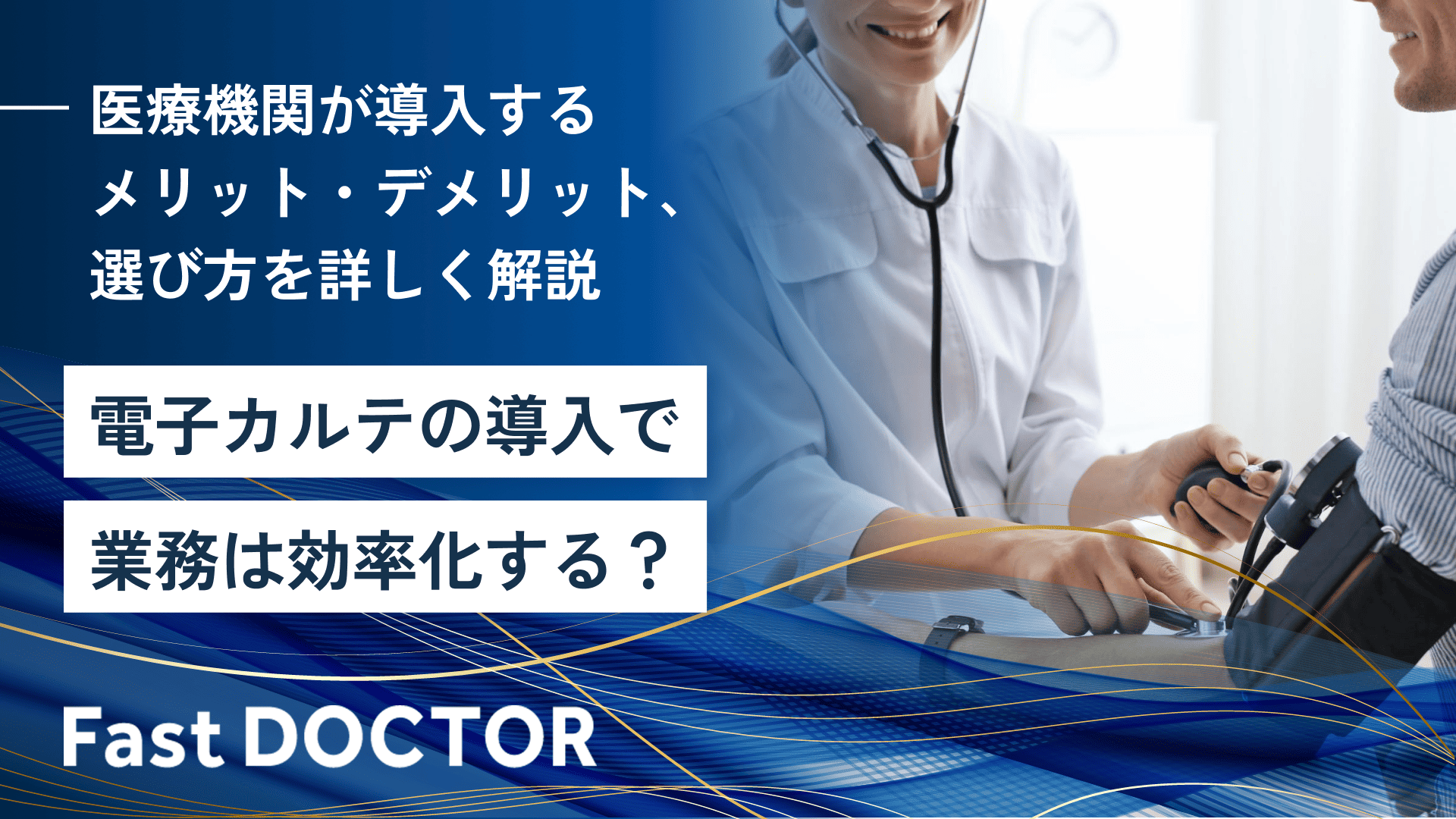病院・医療のDX化とは?業界の課題やDXを導入する5つのメリットを徹底解説
2024.08.08
2025.05.26
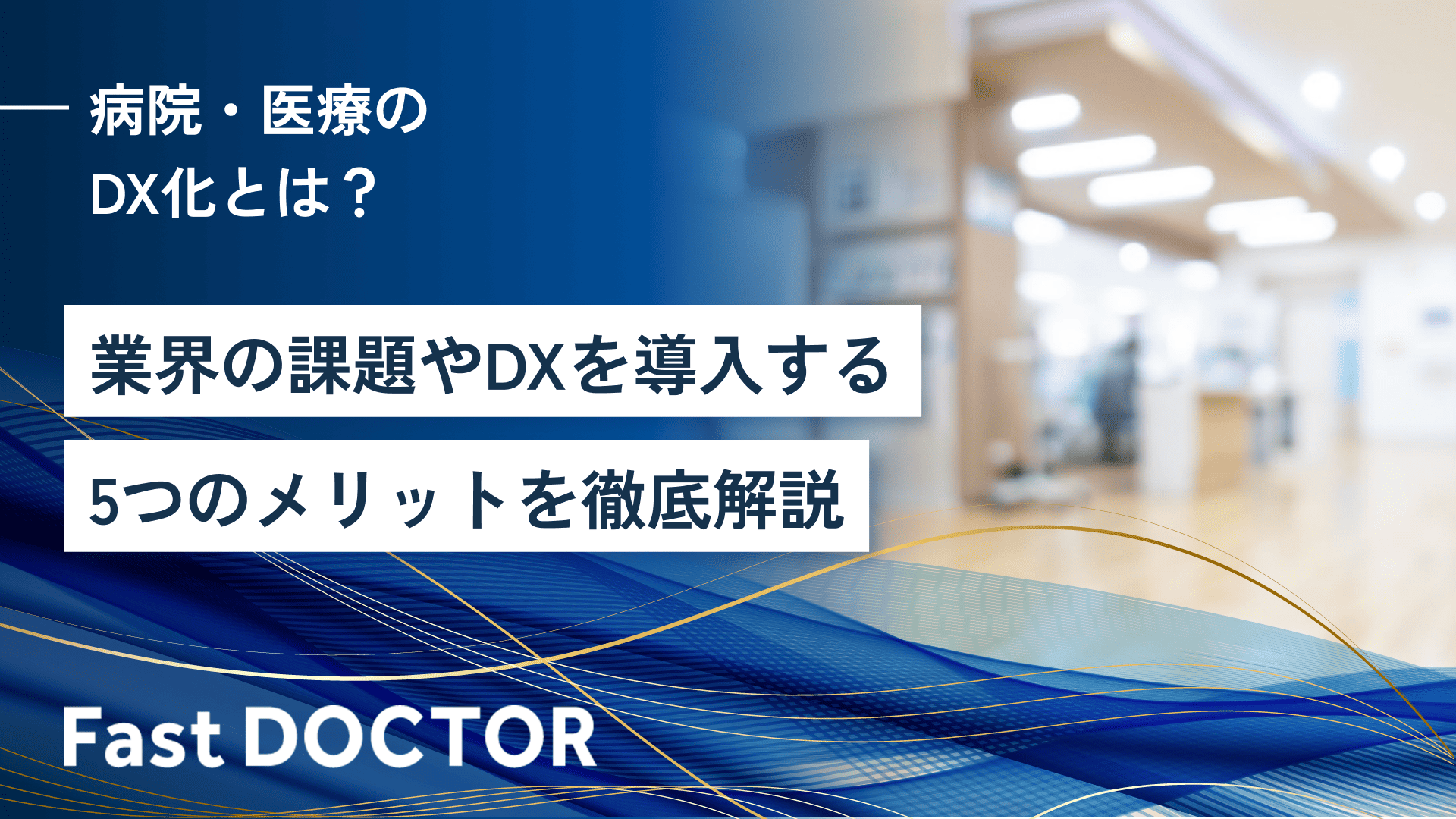

この記事の著者
「病院・医療のDX化を進めるメリットは?」
「医療をDX化するとどんな影響がありますか」
上記のような悩みを持っていませんか。病院・医療のDX化とは、最新のデジタルテクノロジーを利用して業務効率化を図ることです。
DX化を進めるには大きなコストがかかりますが、長期的に見て現場スタッフの負担軽減や品質向上にも期待できるでしょう。
DX化を検討する際はまず現状の課題を把握し、導入するメリットやデメリットに対する理解が必要です。
そこで本記事では、病院・医療のDX化がどのようなものかをご紹介し、業界の抱える課題やDXを導入するメリットなどを解説します。
DX化を進めたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

病院(医療業界)で進むDX化とは
病院(医療)のDX化とは、保険や医療・介護に関するデジタル技術を活用し、疾患の予防やより良い医療と介護の実現を目的として社会・生活を変えることです。
例えば、DX化の一例として医療記録の電子化が挙げられます。患者情報や診察記録を電子的に管理することで、情報共有が迅速かつ正確に行えます。
さらに、DX化によって医療機関の業務効率化にも寄与します。予約システムや在庫管理の自動化など、様々な業務におけるプロセスの最適化が可能です。
このように、デジタル技術を活用していくことで、業務効率化を図れるようになり、結果的により良い医療サービスを提供できるようになります。
DX化の前に病院(医療)の現状や課題把握が必要
DX化を進める際には、まずは医療機関の現状や抱えている課題の把握が必要です。
ここでは医療機関が抱えている代表的な課題として、以下の4つを解説していきます。
- 病院で働く看護師の人材不足
- 地域によって医療格差が二極化
- 2025年問題
- 長時間労働
病院で働く看護師の人材不足
病院で働く看護師の人材不足は、医療業界が抱えている課題です。
厚生労働省によると、令和3年の医療・福祉業界の離職率は13.5%となっています。
他業界と比較して見ても離職率は高い傾向にあり、看護師の人材不足はさらに進行していくと考えられています。
また、厚生労働省が令和5年2月に発表した資料によると、医療業界の未充足求人数は約72%と医療業界全体で人材不足が顕著な状況です。
参考:厚生労働省
看護師が不足すると、一人あたりの業務量が多くなり、医療・看護のチェック体制が十分に整備できなくなってしまいます。
また、業務環境が悪化するだけなく、患者の受け入れ態勢の脆弱化にもつながるため、病院で働く看護師の人材不足は、早急に対応すべき課題といえます。
地域によって医療格差が二極化
地域によって医療格差があることも、医療業界が抱えている課題の1つです。
人口が多い・増えている地域は医療機関が充実しているのに対して、人口の少ない・減少している地域は医療機関の数が減少傾向にあります。
例えば、平成18(2006)年に財政破綻を宣言した北海道夕張市では、入院用ベッド数が20以上ある「病院」が1つもない状況であることが報告されています。
過疎化の進む地域では、都心部よりも先進的な医療テクノロジーを導入した施設数が限られてしまうでしょう。
住む地域によって受けられる医療に差が生まれるのは、医療業界全体で抱えている課題の1つです。
2025年問題
2025年は、団塊の世代と呼ばれる人々が後期高齢者である75歳を迎える年であり、超高齢化社会が進み人材不足が深刻化するとして「2025年問題」と呼ばれています。
例えば、医療費や介護費の増加、対応できる人材が不足するなど、さまざまな問題が挙げられています。
2025年問題は医療業界で大きな課題とされており、各医療機関でも患者を受け入れる体制を整える必要があります。
長時間労働
医療業界は、慢性的な長時間労働を課題として抱えています。
特にカルテや問診表の作成、処方箋の発行、物品の購入手続きなどを人力(アナログ)で行っている医療機関は、スタッフの労働時間が長くなる傾向にあります。
医療業界全体でもDX化による業務効率改善の動きは始まっており、1999年にカルテの電子化が認められ、2006年にはレセプトのオンライン請求が義務化されています。
業務のアナログ運用によって長時間労働が増えており、職場環境の悪化や患者の受け入れ態勢にも影響するため、早急に改善すべき課題の1つといえるでしょう。
病院(医療)でDX化を導入するメリット
病院(医療業界)でDX化を導入するなら、メリットについて知っておく必要があります。
ここではDX化における主なメリットとして、以下の5つを見ていきましょう。
- 患者個人の健康増進に寄与
- 書類の電子化により業務効率の向上
- 患者の待ち時間を削減
- 非対面で診察が可能
- BCPの強化
患者個人の健康増進に寄与
DX化を導入することで、患者個人の健康増進への寄与が期待されています。
これは生涯にわたる保健医療データが、患者自身で把握できるようになるためです。
例えば、患者が記憶していない検査結果やアレルギー情報などが可視化できるようになり、患者自身が自分の健康状態を把握しやすくなります。
さらに、医療情報の共有が円滑化・迅速化できるため、患者一人ひとりがより適切な医療を受けられるようにもなります。
書類の電子化により業務効率の向上
電子化が進むことによって、業務効率が向上するのもDX化のメリットです。
紙媒体で管理していると、情報共有の効率低下、記入ミス、紛失などのリスクが伴います。
人間がやる作業である以上はミスがつきものですが、電子化・ペーパーレス化が進むことで情報の検索性向上、共有環境の改善やヒューマンエラーの防止策としての効果も期待できるでしょう。
患者の待ち時間を削減
病院や医療機関のDX化を進めれば、患者の待ち時間の削減が期待できます。
DXを活用したシステムにより、患者は事前にオンラインで予約を行えるようになり、受付時の混雑が軽減されます。
今まで対面で行ってきた業務を遠隔で対応したり同時に対応できたりすることで、患者が病院内で待つ時間を短縮できます。
非対面で診察が可能
医療機関のDX化を進めれば、非対面での診察が可能になります。
オンラインや遠隔地からの診察ができるようになれば、感染リスクを抑えながら診察できるでしょう。
さらに、近くに医療機関がなくても医療サービスを受けられるのは大きなメリットです。
医療機関不足や医療の過疎化に悩まされる地域に対しても、DX化は有効的な手段の一つといえるでしょう。
BCPの強化
BCPとは、災害をはじめとした緊急事態における企業や団体の事業継続計画のことをいいます。
医療データを紙や自社サーバーのみで保管していると、大規模な災害が発生した際にデータを紛失したり、アクセスできなくなるかもしれません。
DX化によってクラウドサービスを活用できるようになれば、クラウド上で医療データを全て管理でき、世界中どこからでも医療情報にアクセスできます。
また、データの紛失や改ざんの予防にも効果的であるといえるでしょう。
病院でDXを導入する際のデメリット
病院でDXを導入する際は、メリットだけではなくデメリットも発生します。
ここではDX化の代表的なデメリットとして、以下の2つを紹介します。
- 情報漏洩のリスク
- 導入コストの負担
情報漏洩のリスク
病院DXを導入する際は、情報漏洩のリスクを理解しておかなければなりません。
今まで紙で運用していた情報をデータ化するため、管理方法によっては今まで以上に誰でも閲覧しやすい環境となってしまいます。
情報漏洩を防ぐためには、セキュリティ面の対策も考慮する必要があるでしょう。
また、クラウド上での情報の扱い方についても医療機関内で共有できる体制を整える必要があります。
導入コストの負担
DX化には、導入コストの負担が発生する点を理解しておきましょう。
例えば、新たなパソコンを用意したり、システム構築をしなければならず、それらに伴うツールの使い方を職員に周知する必要があります。
また、補助金制度も政府によって用意されてはいますが、利用する際の手続きが面倒だったり、条件が設けられているケースもあります。
ただし、導入時のコストがかかったとしても、長期的に見れば全体のコスト削減につながる場合があります。
病院(医療)DX化が進まない状況を改善する手順
病院(医療)DX化が進まない状況を打破するためには、病院DXを進める手順を理解しておく必要があります。
ここではDX化のためにやるべきこととして、以下の3つを解説していきます。
- 病院内の課題を把握
- DX化の優先順位を確定
- 導入の確定・オペレーションの構築
どんなDX化を進める場合でも上記は重要な工程であり、病院DXを進める場合は必ず実践すべきポイントです。
病院内の課題を把握
病院DXを進める際は、まず各医療機関内の課題を把握することから始めましょう。
本質的な課題を明確にしなければ、必要なツールや機能がわからないままになってしまい、効果的なDX化が進みません。
一方で、もし現場で大きな問題が見えていなくても、以下に該当する場合はDX化の恩恵を得やすい業務となりますので率先して取り組みたいところです。
- 手動で行っている定例業務
- システム間の連携を手動で行っている業務
- 報告書作成、部門間共有が必要な業務
一度上記の観点から、業務効率改善ができる箇所を洗い出してみるのもいいでしょう。
DX化の優先順位を確定
病院内の課題を把握できたら、次は課題解決を進める優先順位を確定する必要があります。
優先順位を決めずにDX化を進めようとすると、改善による影響が小さい業務からDX化を推進してしまう可能性もあり、効率の悪い進め方になってしまいます。
代表的なDX化事例としてあげられるのは、以下の通りです。
- 電子カルテ:診察内容・処方薬情報をデジタル化し、レセプト業務の効率化や他機関との連携をスムーズにできるようにする
- 予約システム:診察をWEB予約できるようにすることで電話応対の頻度が減り、受付・事務業務を効率化できる
- 自動発注システム:医療器具や消耗品などが規定個数以下になった際に自動発注することで、在庫確認や発注書の作成・送付の手間を削減
特に優先順位の決定が進まない場合は、日常業務のデジタル化から進めるようにしましょう。多くの従業員が携わる部分であれば、導入の理解や協力も得やすくなります。
導入の確定・オペレーションの構築
優先順位を確定させたら、いよいよ抱えている課題の解決につながるソリューションを検討する必要があります。
導入の際は初期費用や年間利用費だけでなく、システムを利用するスタッフを育てるための教育コストおよび運用工数もチェックしましょう。
また実際に導入が確定したら、選んだソリューションを随時効果測定する必要があります。
最初からすべてうまく運用できるケースは非常にまれであるため、オペレーションの見直し・構築を繰り返すのが大切です。
医療・病院のDX化事例
医療機関や病院でDXを導入した事例は数多くあります。実際の導入事例を知ることで、現場での活用イメージを持ちやすくなるでしょう。
ここからは実際の導入事例として、以下2つの事例をご紹介します。
- 医療・病院DX化事例①:厚生労働省
- 医療・病院DX化事例②:大学病院
医療・病院DX化事例①:厚生労働省
厚生労働省は2021年10月20日より、マイナンバーカードに保険証機能を付与する「保険証利用」を本格的に開始しました。
参考:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
保険証利用の開始によって、初診の医療機関にも薬剤情報をはじめとする各種情報が共有されます。
アレルギーが出る薬や現在服用している薬などを把握できるため、薬の飲み合わせが悪くなるリスクを軽減可能です。
さらに高額療養費制度を利用する際に必要な「限度額適用認定証」がなくても支払い免除されるため、医療サービスの利便性向上が期待できるでしょう。
医療・病院DX化事例②:大学病院
大学病院では、オランダに本社を置く電気機器関連機器メーカーとの共同研究開発のもと、2018年4月から「遠隔集中治療患者管理プログラム(eICU)」の運用を始めました。
参考:昭和大学病院
eICUを使えば、複数の病院や病棟にいるICU患者の状態や生体情報・検査結果情報などを、ネットワークを利用して遠隔にある支援センターに集められます。
eICUの導入によってICUの不足を解消したり、専門医や医療従事者の負担軽減効果を得られるようになります。
医療・病院のDX化で業務の効率化が期待できます
本記事では医療・病院のDX化について解説しました。医療・病院のDX化は、現状抱えている課題の解決や、業務効率化を進めるのに効果的です。
ただし、導入する際はメリットばかりではありません。課題の本質を分析し、導入デメリットに対する対処方法も合わせて検討する必要があります。
導入にコストや組織の改善が必要になるため、導入ハードルは高い場合がありますが、長期的に大きな恩恵を受けられる場合があります。気になる方は一度専門家や各事業者に相談してみることをおすすめします。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。



関連記事RELATED