国が進める地域医療構想とは?地域医療の抱える問題を解決するために医療機関にできること
2024.08.23
2025.05.26
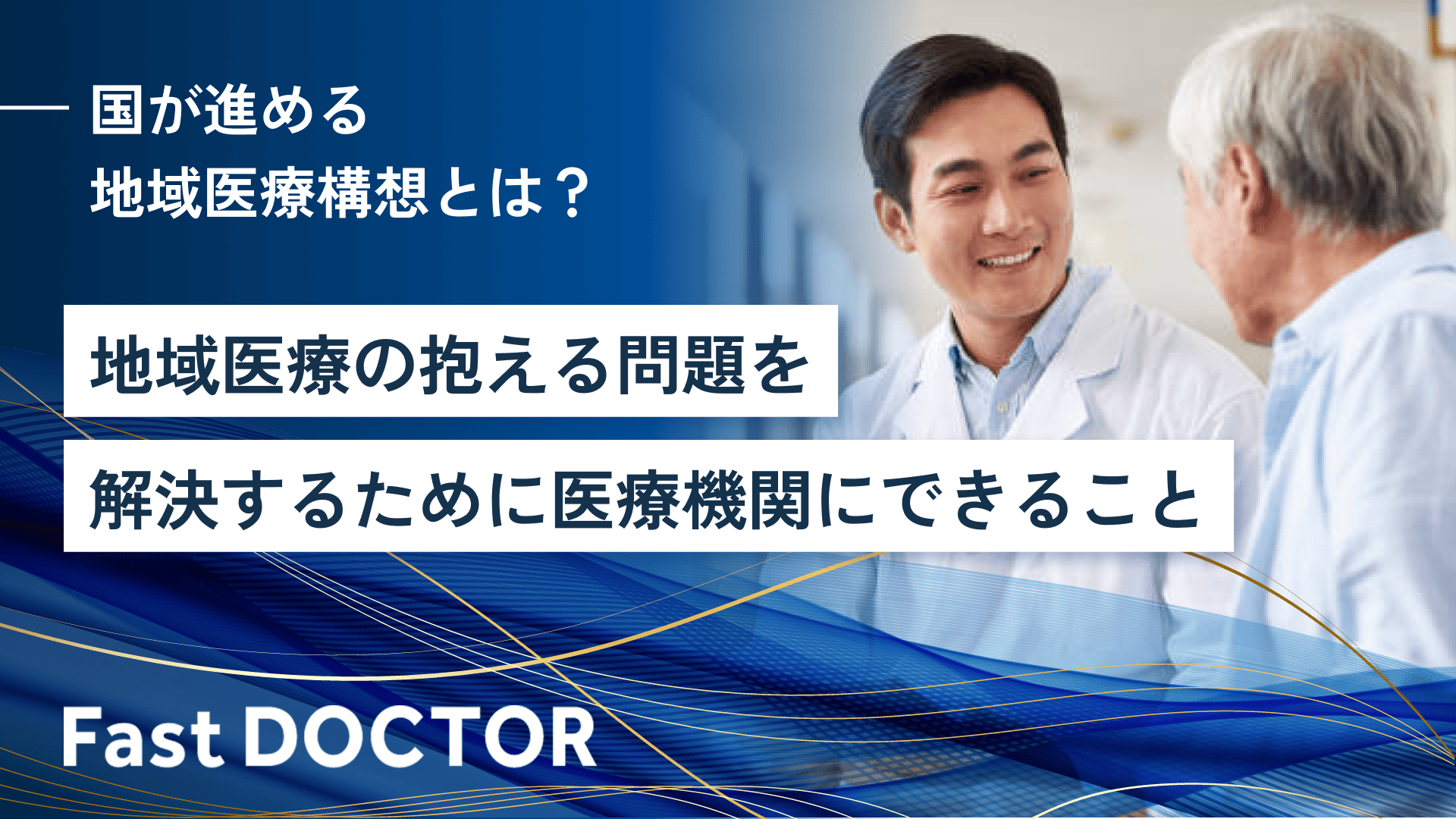

この記事の著者
地域医療構想を実現するためには、医療機関と都道府県が主体となって地域の状況を踏まえて機能分化・連携を進めていく必要があります。そのために、地域医療の課題や国の支援などの情報を把握したほうが良いでしょう。
本記事では、地域医療の現状や課題、地域医療の質を向上させるために医療機関ができることなどについて解説します。
地域医療の質の向上のために必要な情報や医療機関ができることが知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
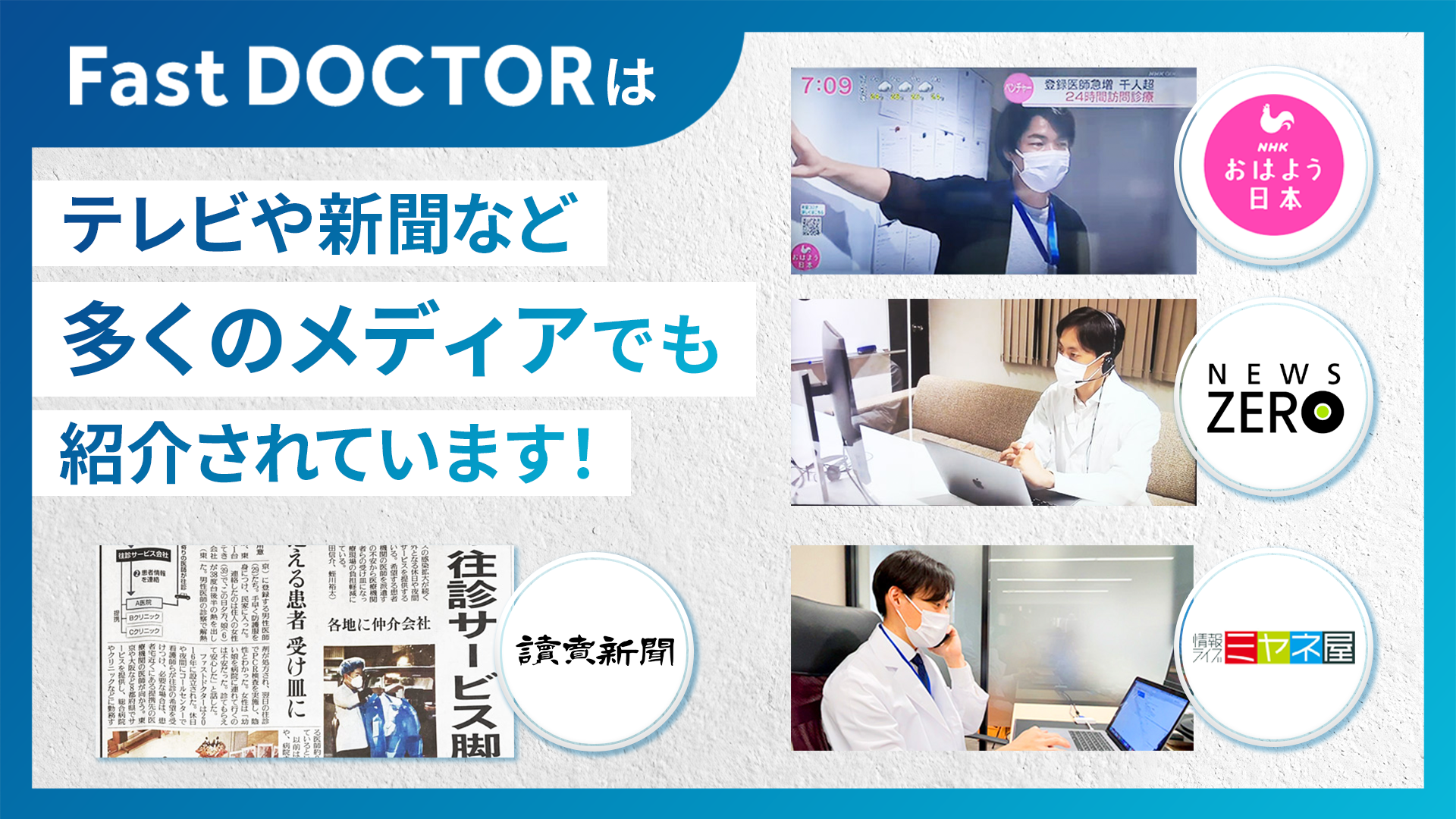
地域医療構想の基本と目的
地域医療構想の基本と目的について、以下2つに分けて解説します。
- 地域医療構想とは
- 地域医療構想が推進される理由
地域医療構想とは
地域医療構想とは2025年に必要となる病床数を確保するために、医療機関の機能分化・連携を進めて効率的に適切な医療を提供できる体制を整える取り組みのことです。
地域医療構想を実現するための医療機関の機能分化・連携は、地域での協議を実施しながら医療機関が自主的に取り組む必要があります。都道府県の役割は、地域医療構想を達成するために地域医療構想調整会議を設置し、地域の状況を踏まえて機能分化・連携を進めることです。
基本的には、医療機関と都道府県が主体となって取り組みますが、国は地域医療構想が推進されるように以下6つの支援を実施しています。
- 地域別の病床機能等の見える化
- 都道府県の取組の好事例の周知
- 医療機関の機能転換・再編等の好事例の周知
- 地域医療構想の取組を進めるための支援策の周知ツール
- 都道府県等の取組に関するチェックリスト
- モデル推進区域(仮称)におけるアウトリーチの伴走支援
地域医療構想が推進される理由
日本の少子高齢化が進み、団塊世代が75歳以上となる2025年には医療と介護の需要が高まると予測されています。2025年に、良質で適切なサービスが提供できる体制を整えるために、地域医療構想が推進されています。
地域医療構想が創設されたのは、2014年の医療法改正です。その後、2017年には地域医療構想ガイドラインが通知されました。2018年の医療法改正時には、地域医療構想の実現のため知事権限が追加され、2022年には地域医療構想の進め方についての通知が行われ、PDCAサイクルによって地域医療構想が推進されました。
このように、2025年までに地域医療構想が実現するよう、医療法改正などが進められています。
参照:厚生労働省「地域医療構想に関する主な経緯や都道府県の責務の明確化等に係る取組・支援等」
経営のために知っておきたい|地域医療の現状と課題
医療機関を経営するにあたり、地域医療の現状と課題を知る必要があります。ここでは、以下2つの現状と課題について解説します。
- 地域ごとの医療サービスの差
- 地域医療が直面する主な問題点
地域ごとの医療サービスの差
医療は平等に提供されるべきですが、地域ごとに医療サービスに差が生まれているのが現状です。
人口10万人に対する医師の数を都道府県別に見てみると、最も多いのが徳島県(338.4人)で最も少ないのは埼玉県(177.8人)でした。徳島県と埼玉県では、医師の数に約1.9倍もの差が生まれています。
加えて、都道府県別の1人当たりの医療費を見てみると、最も高いのが高知県(445,624円)で、最も低いのが埼玉県(310,621円)でした。高知県と埼玉県では約1.4倍の差があります。
このことから、医師の数が異なると提供する医療の量に差が生まれるといえるでしょう。
また、地域ごとに医療サービスに差があると、地域医療構想の推進にも差が生じる可能性があります。地域医療構想をどの地域でも進めていくために、国は重点支援区域を設定して複数の医療機関が医療再編や連携を進められるように技術的支援と財政的支援を行っています。2024年7月時点で選定された重点支援区域は13道県21区域です。
重点支援区域の他に、再編検討区域も存在します。再編検討区域は、重点支援区域の申請の要否を判断するまでの支援を受けられる区域です。あくまでも判断するまでの支援のため、技術的支援は必要な範囲のみで実施されます。
参照:厚生労働省「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」
地域医療が直面する主な問題点
地域医療が直面する主な問題点には、以下が挙げられます。
- 医療従事者の不足
- 医療資源の不足
- 医療機関の赤字経営
- 患者の圏外流出 など
これらの問題点は全てつながっており、1つでも問題点が発生すると負のループを作り出してしまう恐れがあります。
医師や看護師が不足した場合、必要な医療が提供できず患者が適切な医療を受けられる医療機関へ移ってしまいます。患者がどんどん圏外流出すると、収入が減り医療機関の経営が危ぶまれるでしょう。
医療機関の経営が赤字になると、医療資源の確保も難しくなり医療資源の不足につながります。
加えて、医療従事者の不足によって1人あたりの負担が増えると退職者が現れ、さらに人手不足が深刻化します。人手不足になると必要な医療の提供ができなくなり……と悪化の一途をたどることになるでしょう。
参照:厚生労働省「地域住民が圏域で必要な医療を受けられる課題 主な取組」
地域医療の質を向上させるには?医療機関にできること
地域医療の質を向上させるために医療機関ができることとして、以下3つがあります。
- 地域医療介護総合確保基金など支援金や補助金の活用
- 地域医療を支えるための人材確保
- 医療ICTの推進
それぞれについて、解説します。
地域医療介護総合確保基金など支援金や補助金の活用
医療機関が地域医療構想に取り組めるように、国は以下のような支援金や補助金を提示しています。
| 支援金・補助金 | 概要 |
| 地域医療介護総合確保基金 | ・消費税増収分などを活用した財政支援制度<対象事業>・ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業・地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業・居宅等における医療の提供に関する事業・介護施設等の整備に関する事業(地域密着型サービス等)・医療従事者の確保に関する事業・介護従事者の確保に関する事業・勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 |
| 税制上の優遇措置 | ・医療介護総合確保法に基づく医療機関の再編によって取得した不動産の登録免許税・不動産取得税を軽減する特別措置 |
| 病床再編等の促進のための特別償却制度 | ・地域医療構想調整会議で決まった対応方針に基づいて病床の再編などを実施した際に取得した建物に対して、特別償却が可能・特別償却は取得価格の8% |
| 地域医療構想に係る優遇融資 | ・医療機関を対象とした建築・運転資金に関する優遇融資 |
医療機関だけのお金では改善させていくのに限界があります。地域医療介護総合確保基金などの国が提示している支援金や補助金を活用しながら資金を確保し、人材育成や施設設備の徹底などさまざまな運営・整備を行っていきましょう。
厚生労働省「再編計画の認定に基づく地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置」
地域医療を支えるための人材確保
地域医療の質を向上させるためには、地域医療を支えるための人材確保が必要です。
人材が不足していると、医療従事者1人の負担が大きくなり離職者が増える恐れがあります。また、マンパワー不足で患者に提供する医療の質が低下してしまう可能性もあります。
医療の質の低下は患者離れの原因にもなり、患者が離れていくと収入がなくなり経営難に陥りかねません。赤字経営になってしまえば地域医療の質の向上は難しくなるでしょう。
人材を採用するにあたってコストはかかるものの、地域医療の質の向上に向けて医療機関を運営していくためには、人材は必要不可欠です。地域医療を支えるためにも人材を確保することが、医療機関にできることの1つです。
医療ICTの推進
地域医療の質を向上させるためには、人材確保だけでは限界がある場合があります。そのため、人材確保に加えて医療ICTの推進も検討していきましょう。
医療ICTには、電子カルテや遠隔医療、AI診断支援ツールなどが含まれます。電子カルテを導入すれば業務効率化やスムーズな情報共有につながります。
また、遠隔医療を提供することで、へき地や過疎地域など医療格差が大きい地域にも適切な医療が届けられ、地域医療の質は向上するでしょう。
しかし、医療ICTの導入にはイニシャルコストやランニングコストがかかるため、導入が難しいという医療機関もあるでしょう。その場合は、地域医療連携推進法人制度の活用がおすすめです。
地域医療連携推進法人制度とは、地域医療構想を達成するための選択肢の1つで、複数の医療機関の機能分担や業務の連携を推進する法人の認定制度です。
地域医療連携推進法人制度で連携した医療機関とは、病床再編や医師などの共同研修、医薬品などの共同購入が可能となります。そのため、1つの医療機関だけでは導入できなかった医療ICTの推進も協力して進められる可能性があります。
地域内で複数の医療機関が連携し医療ICTを推進していくことで、平等に適切な医療を提供することに期待できるため、地域医療の質は向上するでしょう。
地域医療構想の実現のために国が実践している支援の例
地域医療構想の実現のために国が実践している支援例を2つ紹介します。
- 地域別に病床機能等の見える化を実施
- 医療機関の機能転換・再編等を行う
地域別に病床機能等の見える化を実施
地域医療構想の実現のため、国は地域別に病床機能等の見える化を実施しています。
地域別の病床機能等の見える化として、厚生労働省のホームページには以下のデータが掲載されています。
- 都道府県の病床数等
- 構想区域の病床数等
- 構想区域の医療機関の病床数、診療実績等
上記データからは、都道府県や構想区域の病床数の状況や2025年の病床数の見込み量や必要数が把握できます。また、全国の構想区域の医療機関の病床数や診療実績なども確認可能です。
自分たちの医療機関や地域だけでなく他の地域のデータを見ることで、地域医療構想調整会議での分析や議論に役立てられるでしょう。
参照:厚生労働省「2025年に向けた地域医療構想の取組の更なる推進に向けた国の支援」
医療機関の機能転換・再編等を行う
医療機関の機能転換・再編等の好事例の周知も国は行っています。
たとえば、医師不足で救急医療の体制維持に課題があるなかで市立病院と2つの民間病院を再編した構想地域の例があります。この例では、急性期を担う病院と回復期・慢性期を担う病院に機能を分化させることができ、さらに連携強化のために医療機関を併設しました。結果、急性期と回復期・慢性期の連携強化が実現しました。
このように機能転換・再編等の背景や内容、成果などが具体的に見られるため、自分たちの医療機関や構想区域の地域医療構想の実現の参考になるでしょう。
好事例は厚生労働省のホームページに掲載されているので、地域医療構想の実現の参考にしてください。
参照:厚生労働省「重点支援区域における地域医療構想の取組(一般財団法人三友堂病院の取組)」
地域医療の質を向上させるためにできることをやっていこう
地域医療構想が推進される理由や地域医療の現状と課題、地域医療構想実現のために医療機関ができることなどについて解説しました。
地域医療構想は、団塊世代が75歳以上になる2025年に向けて、医療機関の機能分化・連携を進めて効率的に適切な医療を提供できる体制を整える取り組みのことです。
地域医療構想を実現するために、医療機関は地域によって医療サービスに差があることや地域医療が直面する問題を知っておく必要があります。それらを踏まえたうえで、地域医療の質向上のために、国の支援を活用したり人材確保をしたりなどできることを行っていきましょう。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
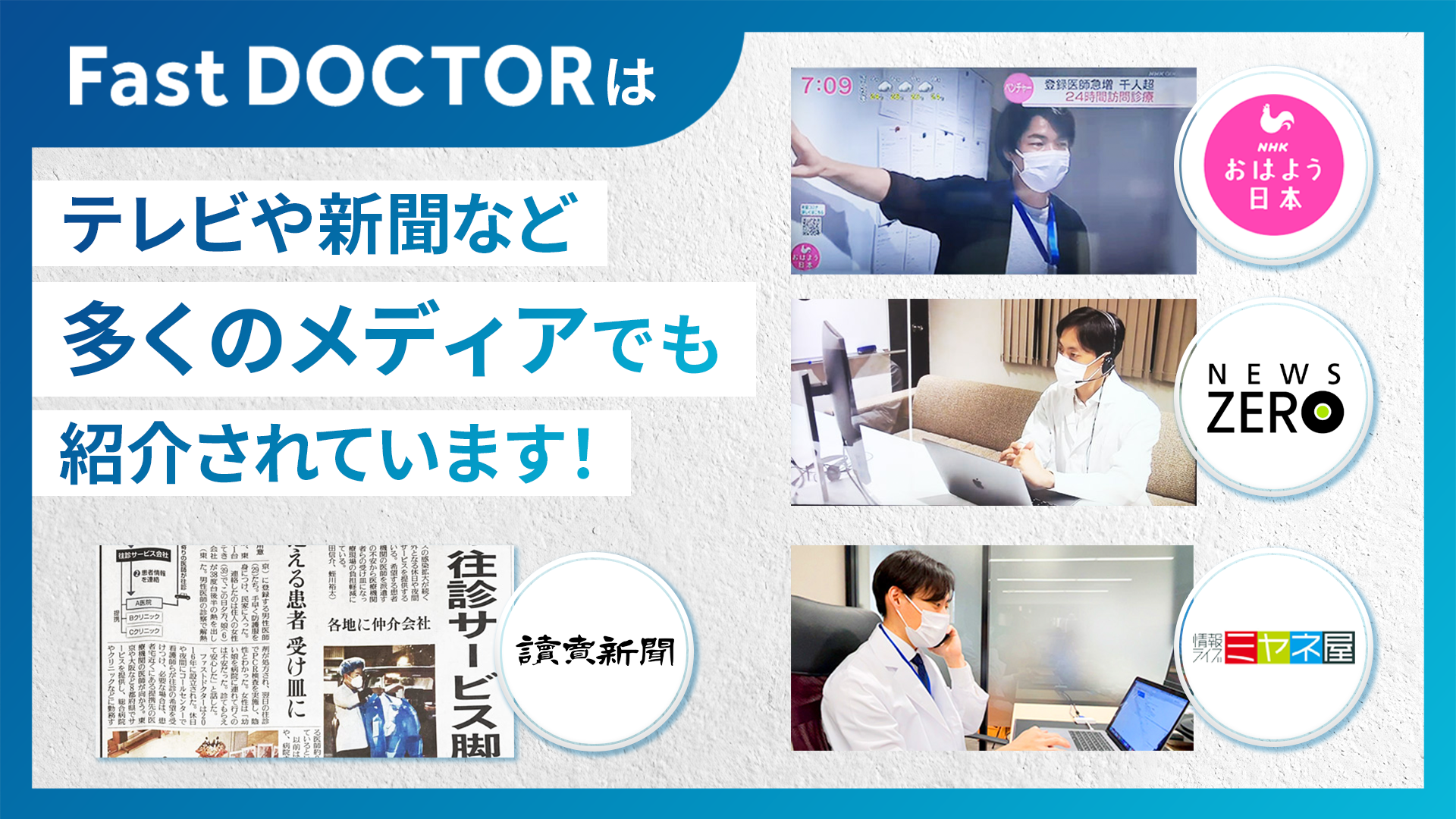


関連記事RELATED







