紙カルテから電子カルテに移行する問題点とは?解決策や導入のメリット・デメリットも解説
2024.08.23
2025.05.26
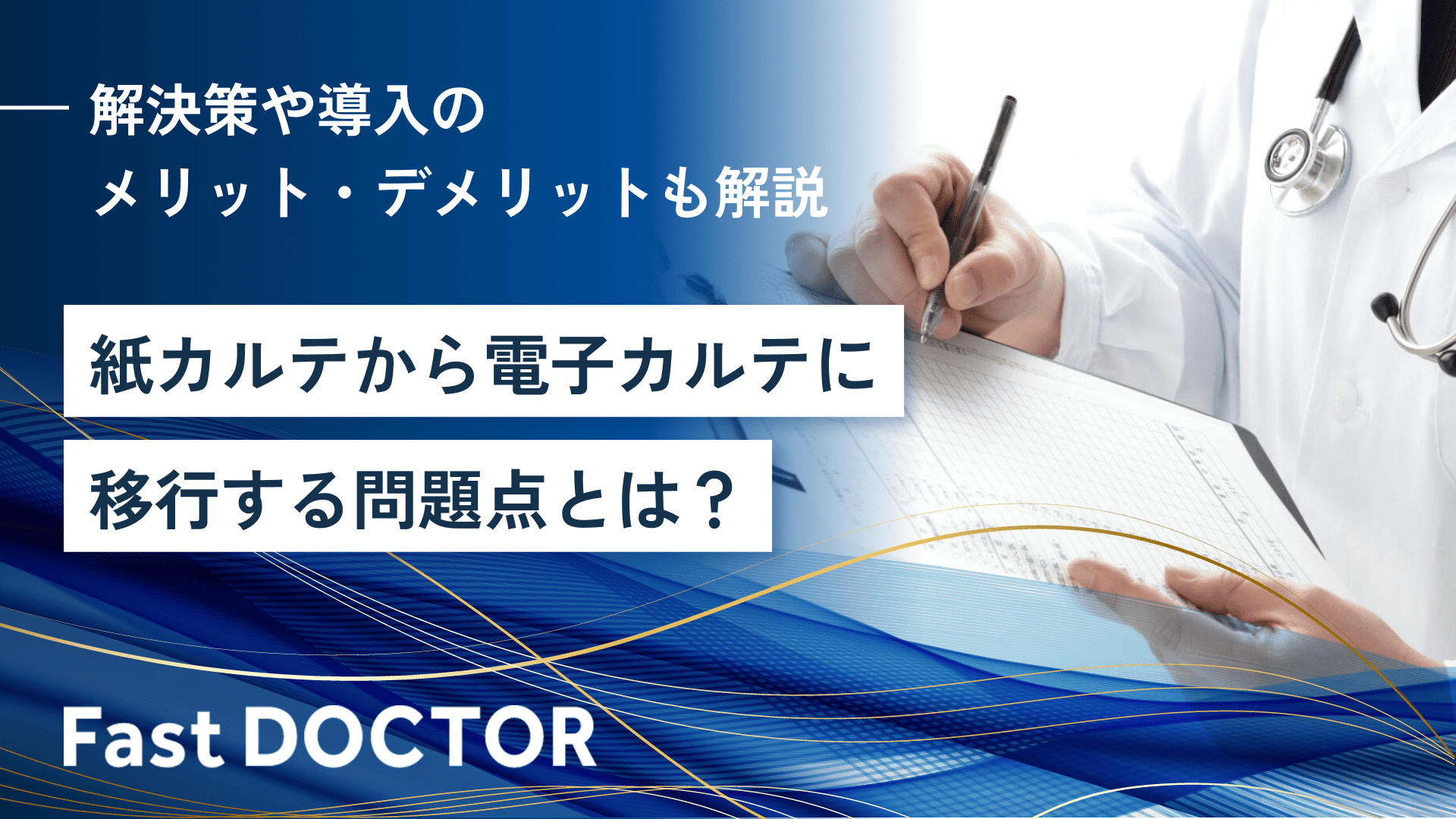

この記事の著者
電子カルテは、患者の医療情報をデジタル形式で記録・管理するシステムです。
電子カルテは紙カルテに比べて、情報へのアクセスが早かったり業務効率が向上したりとメリットが得られます。しかし、紙カルテから電子カルテへの移行は簡単ではなく、問題点も存在するのが現状です。
本記事では、電子カルテの基礎知識や導入するメリット、電子カルテへ移行する問題点などについて解説します。
電子カルテ導入にあたって考慮すべき課題や解決策について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
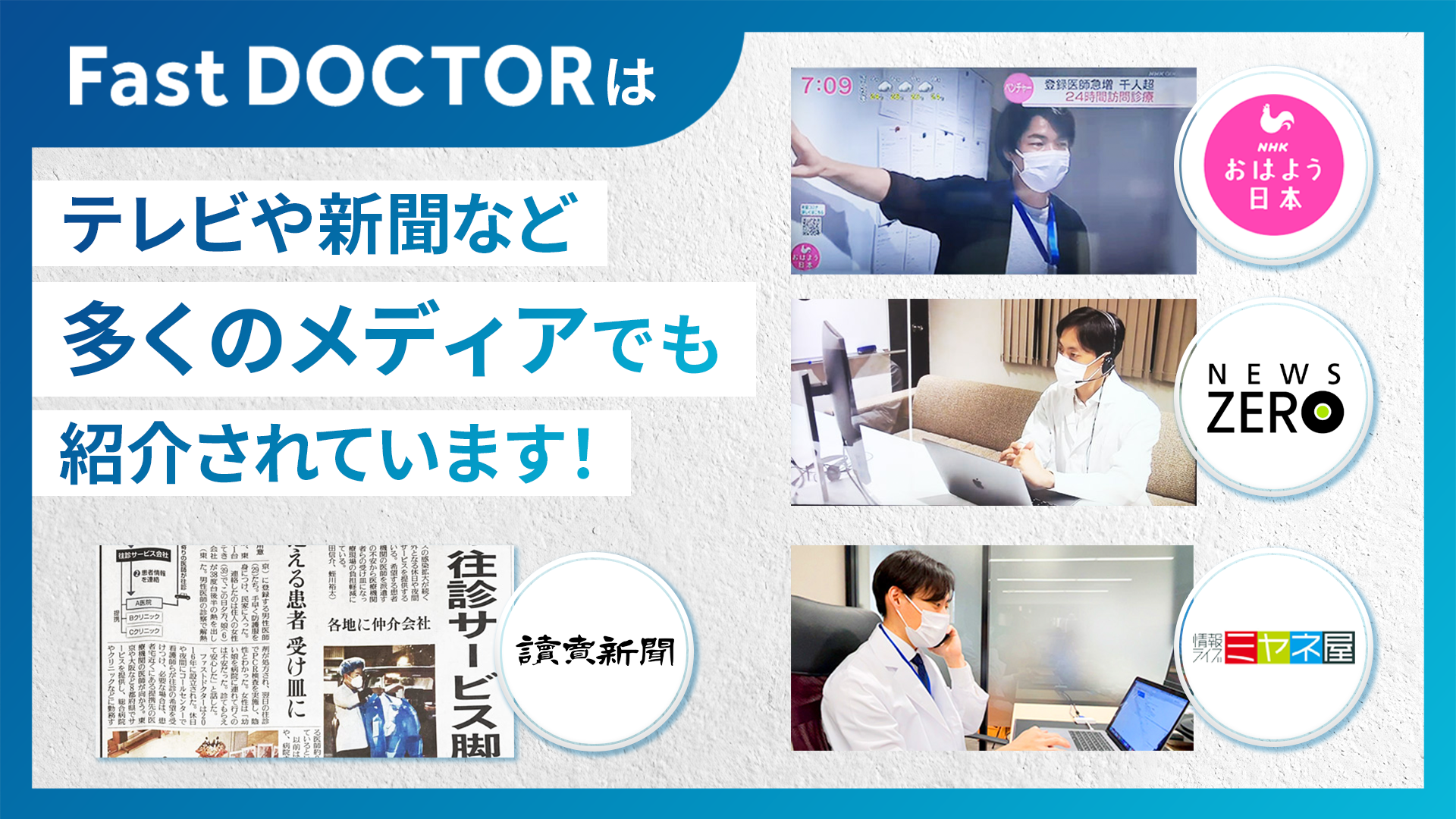
電子カルテ導入にあたって知っておきたい基礎知識
電子カルテ導入にあたって知っておくべき基礎知識として、以下2点について解説します。
- 電子カルテとは?
- 電子カルテ導入時の法規制
電子カルテとは?
電子カルテとは、患者の診療情報をデジタル形式で記録・管理するシステムです。
電子カルテは紙のカルテに比べて、患者の情報がすぐに確認でき、またいつでもどこからでもアクセスできる点が大きな利点となります。
製品によって異なりますが、電子カルテには以下のような機能が備わっています。
| 機能 | 機能内容 |
| 患者管理 | ・患者の個人情報の管理 |
| 外来管理 | ・予約状況の確認・次回予約の管理 など |
| カルテ作成・管理 | ・診療内容の記録・診察・検査結果、薬歴の参照 など |
| オーダー機能 | ・検査、薬処方、手術などのオーダー入力、管理 など |
| 文書作成・管理 | ・同意書や診断書、紹介状などの書類作成・管理 |
電子カルテ導入時の法規制
診療情報が流出してしまうと、患者に悪影響を与え、最悪の場合は営業停止になる恐れがあります。そのため、電子カルテを導入する際は、患者のプライバシー保護を必ず実施する必要があります。
電子カルテに関連する法律は複数あるため、電子カルテ導入時には必ず遵守しましょう。
| 法律 | 法律内容 |
| 個人情報の保護に関する法律 | ・個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の利益や権利を守ることを目的とした法律 |
| e-文書法(①厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令②民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について) | ・民間に義務づけられている書面の保存を、紙媒体から電子にするのを容認する法律・紙をスキャンして保存するのも認められている |
| 診療録等の保存を行う場所について | 診療録等の外部保存を行う際の基準や留意点が定められている法律 |
参照:厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 6.0 版」
電子カルテに移行するメリット
電子カルテに移行するメリットは、2つあります。
- 情報へのアクセスの迅速化
- 医師の診療効率の向上
それぞれのメリットについて、くわしく解説します。
情報へのアクセスの迅速化
情報へのアクセスが迅速になるのは、電子カルテ導入のメリットの1つです。
紙カルテの場合、カルテを確認するためにカルテがある場所へ移動し、必要な情報が記載されている箇所を探す必要があり、時間と手間がかかります。また、他のスタッフが使用している間は同時に確認ができません。
電子カルテの場合、パソコンがあればカルテの確認ができるため移動する必要がありません。また、検索することで必要な情報を引き出せるため時間も短縮できます。
加えて、複数人が同時に閲覧できるため、医療機関内の複数の部門で同時かつ正確な情報を確認することができます。複数の部門でリアルタイムで情報共有が可能となるため、チーム医療において業務の効率化ができるようになるでしょう。
参照:厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 6.0 版」
医師の診療効率の向上
医師の診療効率が向上する点も、電子カルテへ移行するメリットです。
医師の業務のうち、カルテや診断書の記載、書類の整理などは時間外労働の原因となり、負担の大きい業務です。
電子カルテへの移行で、手書きからテキスト入力になることでカルテや診断書の記載時間が短縮できます。テンプレートも活用すれば、より時間短縮になるでしょう。
また、患者情報をデジタル化していることでさまざまな情報が一元管理でき、情報検索時間が大幅に短縮され、医師をはじめ他の医療従事者の作業効率が向上するでしょう。
患者情報を迅速に確認できることは、問診内容や検査の重複、思い込みによるミスなどの減少も期待できます。
紙カルテから電子カルテに移行する問題点
紙カルテから電子カルテに移行する際には、以下2つの問題点が出てきます。
- 高額な初期投資と継続費用が必要な場合がある
- 適切なデータ移行とセキュリティ対策が求められる
電子カルテを導入する際は、問題点についても把握しておきましょう。
高額な初期投資と継続費用が必要な場合がある
紙カルテから電子カルテに移行する際は、高額な初期投資と継続費用が必要となる場合があります。
電子カルテを導入する際は、パソコンを必要台数購入したり、ネットワーク設備を整えたりと初期費用が高額になります。
また、初期費用だけでなく、電子カルテのシステム維持費やサーバーなどの更新費用、ベンダーのサポート費用、通信費など維持費用が発生します。
初期費用や維持費用が高額だと小規模の医療機関では負担が大きくなるため、電子カルテへの移行に踏み出せない場合もあるでしょう。しかし、業務効率化やスムーズな情報共有など得られるメリットは大きいため、必要な投資だと考え移行することをおすすめします。
適切なデータ移行とセキュリティ対策が求められる
紙カルテから電子カルテへの移行には、適切なデータ移行とセキュリティ対策が求められます。
紙カルテから電子カルテに全てのデータを移行するとなると、時間と労力を要します。移行作業が大規模になるケースもあるため、医療機関の状況に合った方法で移行しましょう。
たとえば、再診で来院した患者さんのカルテから電子カルテへ移行することや勤務時間内にデータ移行の時間を確保して毎日少しずつ移行をすることなどが挙げられます。
また、電子カルテに移行する際はセキュリティ対策を必ず実施しましょう。
電子カルテには患者の個人情報が記載されているため、流出したりウイルス感染したりすると大きなトラブルに発展します。
実際に、サイバー攻撃を受けて電子カルテの閲覧や入力ができなくなり、医療提供体制に影響を及ぼした事例もあります。
トラブルに発展しないよう、セキュリティ対策は忘れずに行いましょう。
紙カルテから電子カルテにスムーズに移行するためには?
紙カルテから電子カルテにスムーズに移行するための方法を4つ紹介します。
- 移行の計画を立てて手順の明確化を行う
- 情報保護と安全のための対策を行う
- 電子カルテを利用するための研修プログラムを実施する
- 電子カルテへの移行に際してメリットをスタッフへ伝えて協力を仰ぐ
それぞれ実践して、電子カルテへスムーズに移行しましょう。
移行の計画を立てて手順の明確化を行う
紙カルテから電子カルテにスムーズに移行するために、移行の計画を立て手順を明確にしておきましょう。
電子カルテに移行するためには、以下のステップを踏みましょう。
- 電子カルテの選定
- 初期設定
- データ移行
- マニュアル作成・研修実施
- 試験運用
- 本格運用
電子カルテを選定する際は、医療機関の規模やどんな場面で使用するかなどを配慮にして選ぶようにしましょう。実際、電子カルテへの移行はしたものの導入することが目的となってしまい、結局紙カルテの運用が残ってしまったという事例もあるため、電子カルテ導入の目的の明確化は重要です。
初期設定を医療機関で行うことが難しい場合、ベンダーのサポートを受けるのも1つの方法です。
データは、一気に移行するのもいいですが、膨大な量を移行するには時間と労力が必要となるため、少しずつ移行していくことをおすすめします。
初期設定、データ移行が終了したらすぐに本格的に運用するのではなく、マニュアル作成や研修の実施、試験運用をはさみましょう。試験運用で生じた問題点を改善してから本格運用に進めば、トラブルが少なくて済みます。
情報保護と安全のための対策を行う
電子カルテを導入するにあたって重要なのが、情報保護と安全のための対策の実施です。
医療情報が流出してしまうと、患者のプライバシー侵害となったり適切な医療の提供ができなくなったりとトラブルにつながる恐れがあります。
トラブルを防ぐために、サイバーセキュリティの心得として以下9つの対策を実施しましょう。
- アカウント整理と使用状況の棚卸し
- 連絡先の整備
- バックアップの実施状況の点検
- 通信制御の確認
- ログの確認
- 各種システムの更新
- 機器やデータの持ち出しルールの確認と順守
- 利用機器に対する対策
- 電子メールの確認
また、セキュリティシステムの導入やセキュリティ対策の部門を設置するのも重要な対策です。セキュリティ対策の部門を設ける際は、各部門ごとに配置するのではなく、医療機関を横断的に把握できるような部門にする必要があります。
参照:厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 6.0 版 経営管理編」
電子カルテを利用するための研修プログラムを実施する
電子カルテを利用するための研修プログラムを実施することも、電子カルテへのスムーズな移行に必要です。
電子カルテを運用する環境が適切に整備されても、メインで使用する医療従事者が使用できなければ電子カルテを有効活用できないでしょう。
医療従事者のなかには、パソコンに慣れていて直感的に使用できる方もいればスキルが十分ではない方もいます。スタッフ全員が同じように使えるようになるために、使い方の教育や研修を実施しましょう。
厚生労働省では、医療機関の経営層や医療従事者など階層別のサイバーセキュリティ対策研修の実施や医療機関内でのサイバーセキュリティ教育に活用できるコンテンツ集の掲載をしているので、活用してみてください。
電子カルテへの移行に際してスタッフにメリットを伝えて協力を仰ぐ
電子カルテにスムーズに移行するために、電子カルテのメリットをスタッフに伝えて協力を仰ぎましょう。
電子カルテへの移行は、管理職や医療職以外のスタッフのみでの対応は困難です。そのため、医療職に納得してもらい協力を仰ぐ必要があります。特に、病床数の少ない医療機関の場合、紙カルテに慣れている方が多かったり、電子カルテの必要性を感じていない方がいたりと、抵抗がある方が少なくありません。
協力してもらうためには、電子カルテへの移行によって得られるメリットを伝えるといいでしょう。メリットだけでなく、電子カルテ導入によって1人あたりの業務量や残業時間がどれだけ減るのかなど具体的な数値や事例を提示するのも1つの方法です。
参照:厚生労働省「第1回標準型電子カルテ検討ワーキンググループ資料」
課題を解決して電子カルテへ移行しよう
電子カルテ導入に関わる法律や電子カルテに移行するメリット、スムーズに移行する方法について解説しました。
紙カルテから電子カルテに移行すると、迅速な情報確認や業務効率化といったメリットが得られます。しかし、電子カルテに移行するためにはコストやセキュリティ対策の問題などが生じます。
本記事で解説した移行方法を実践し、電子カルテの導入を進めましょう。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
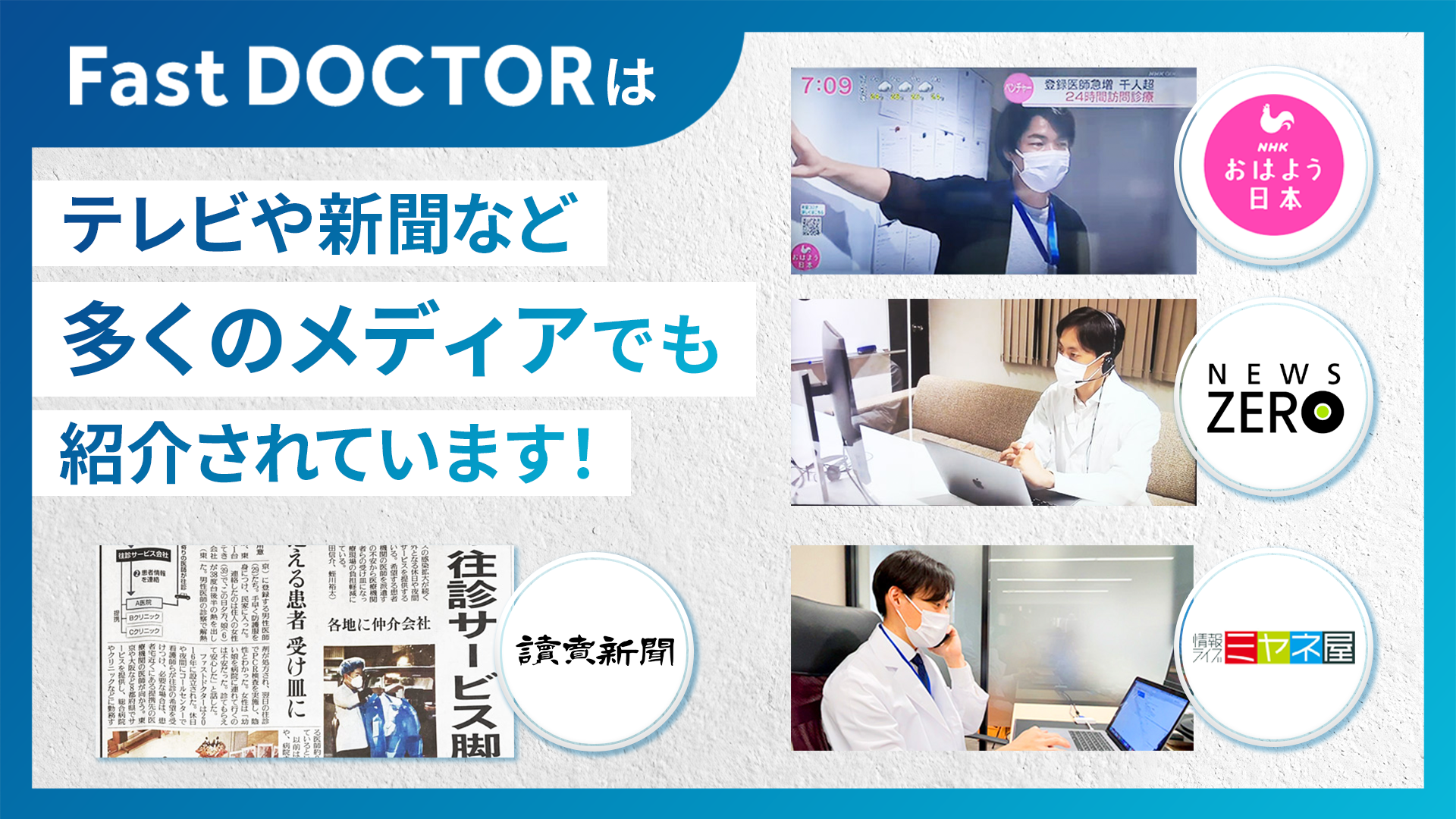


関連記事RELATED







