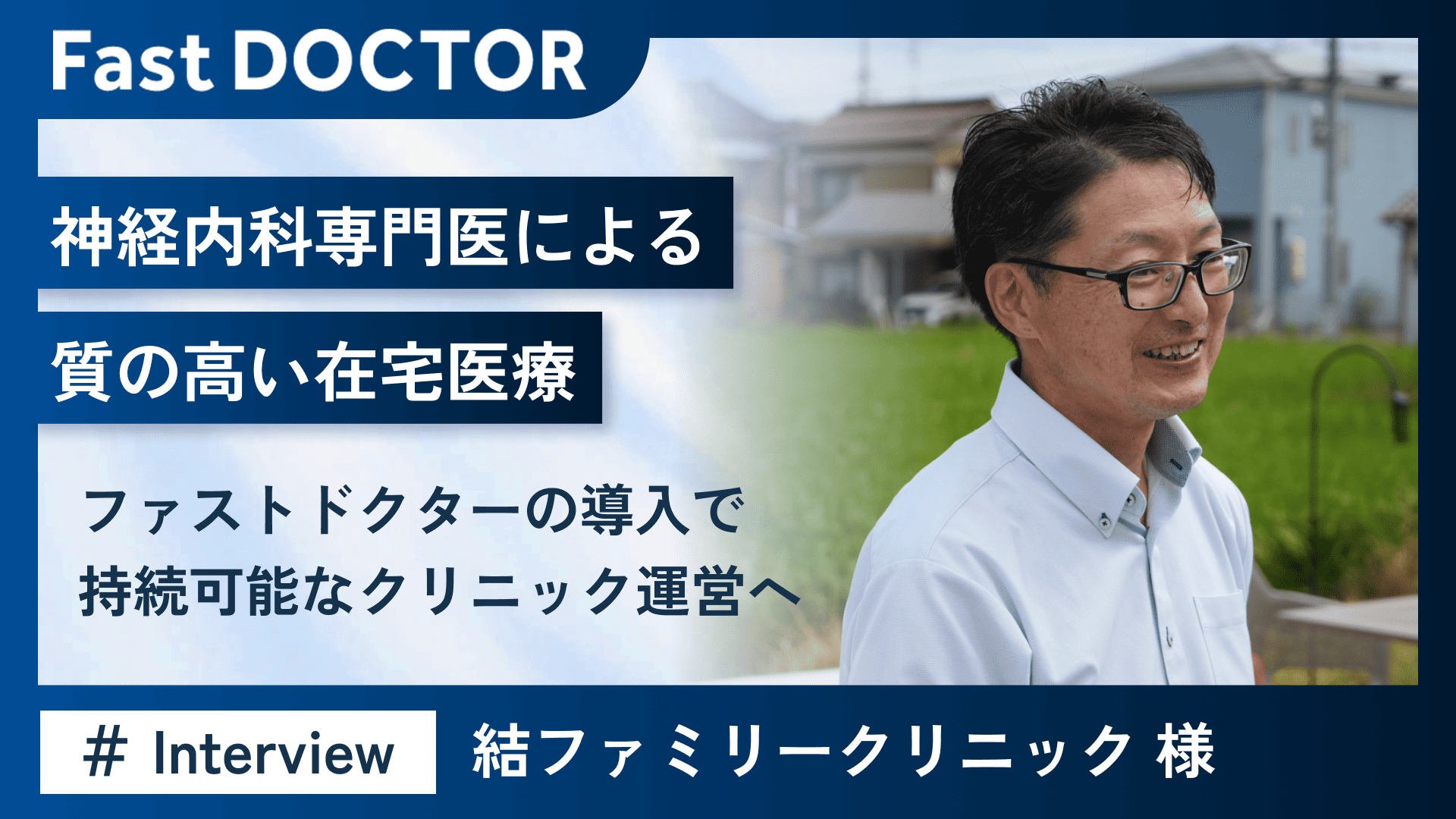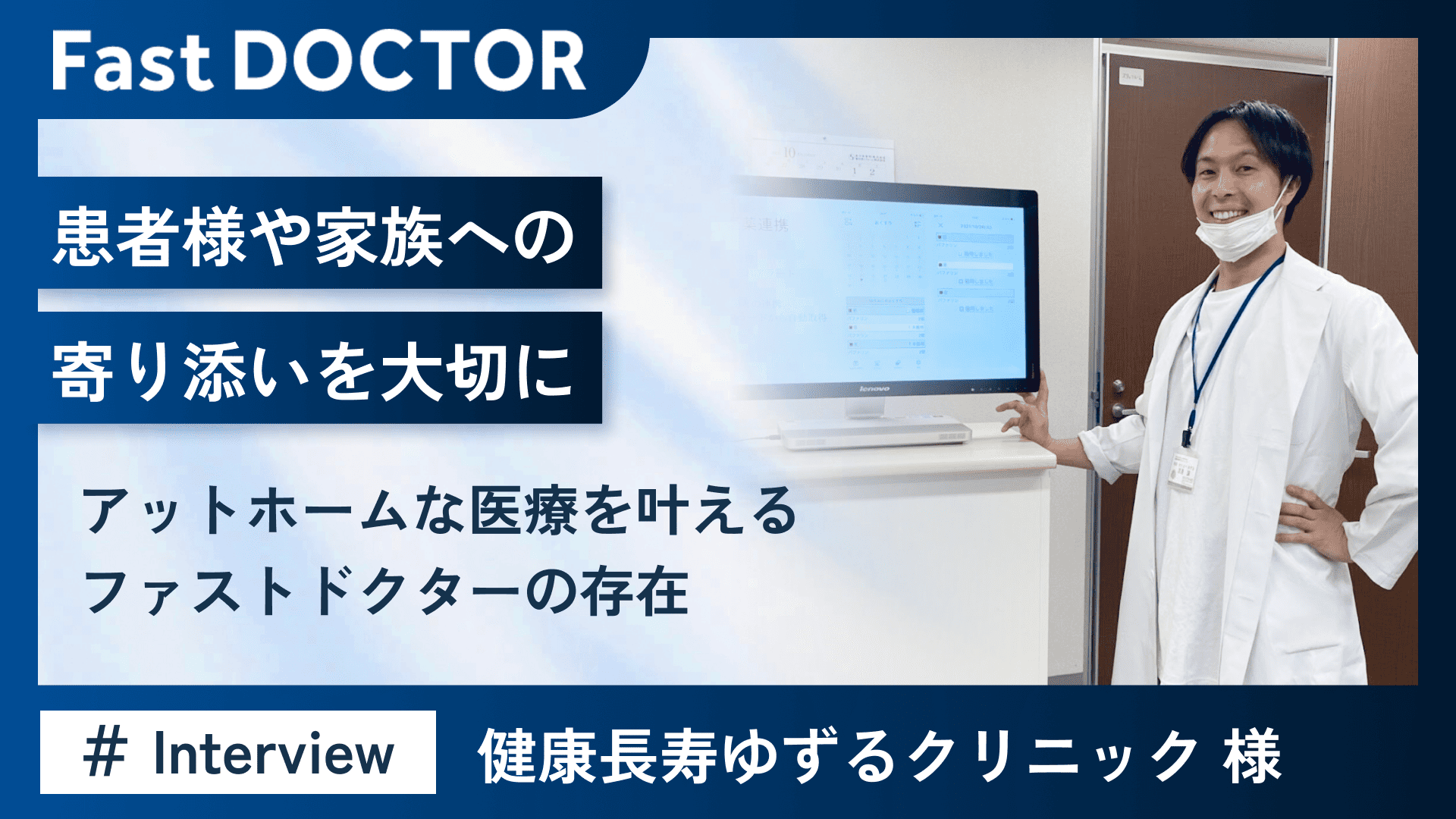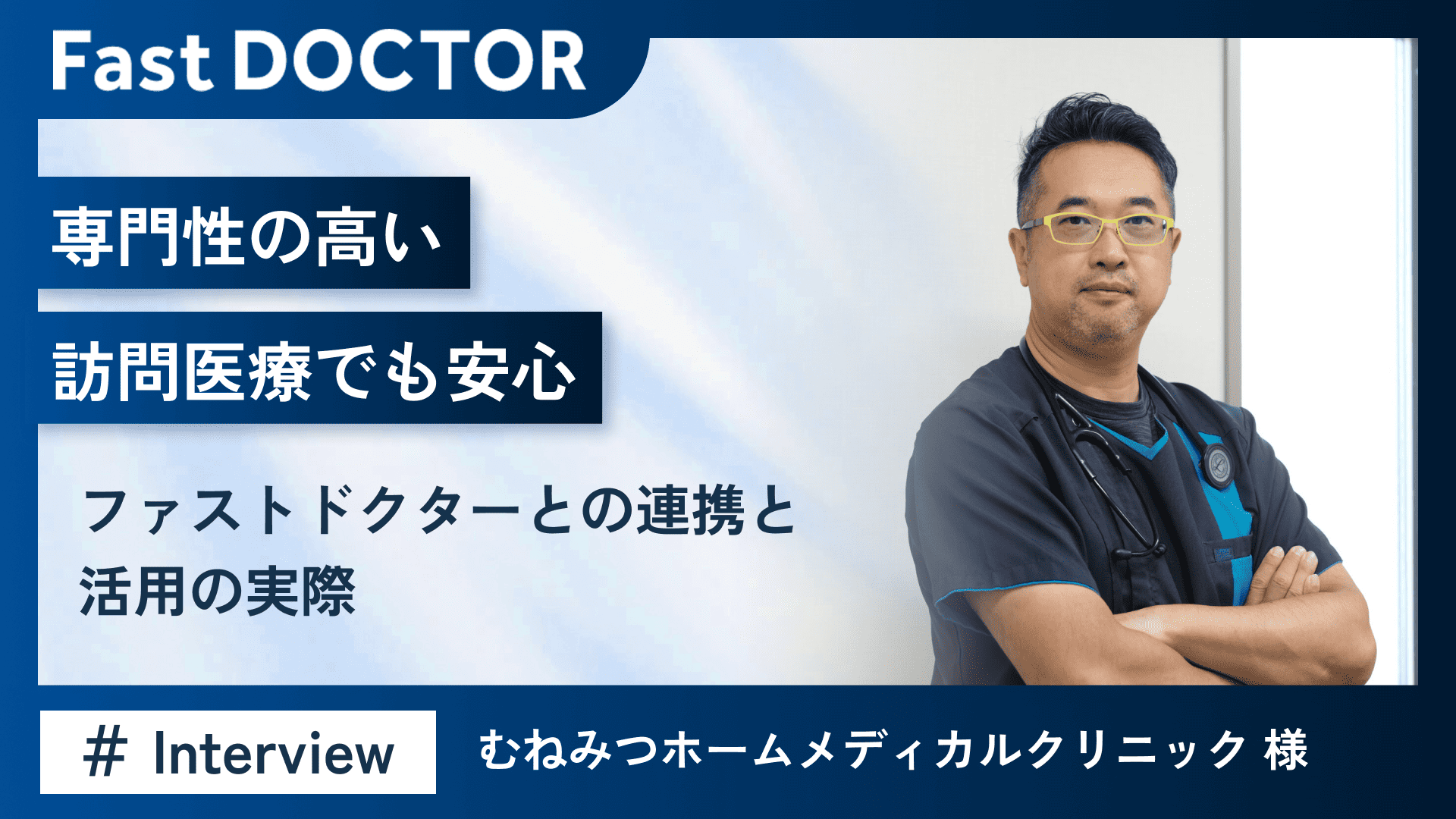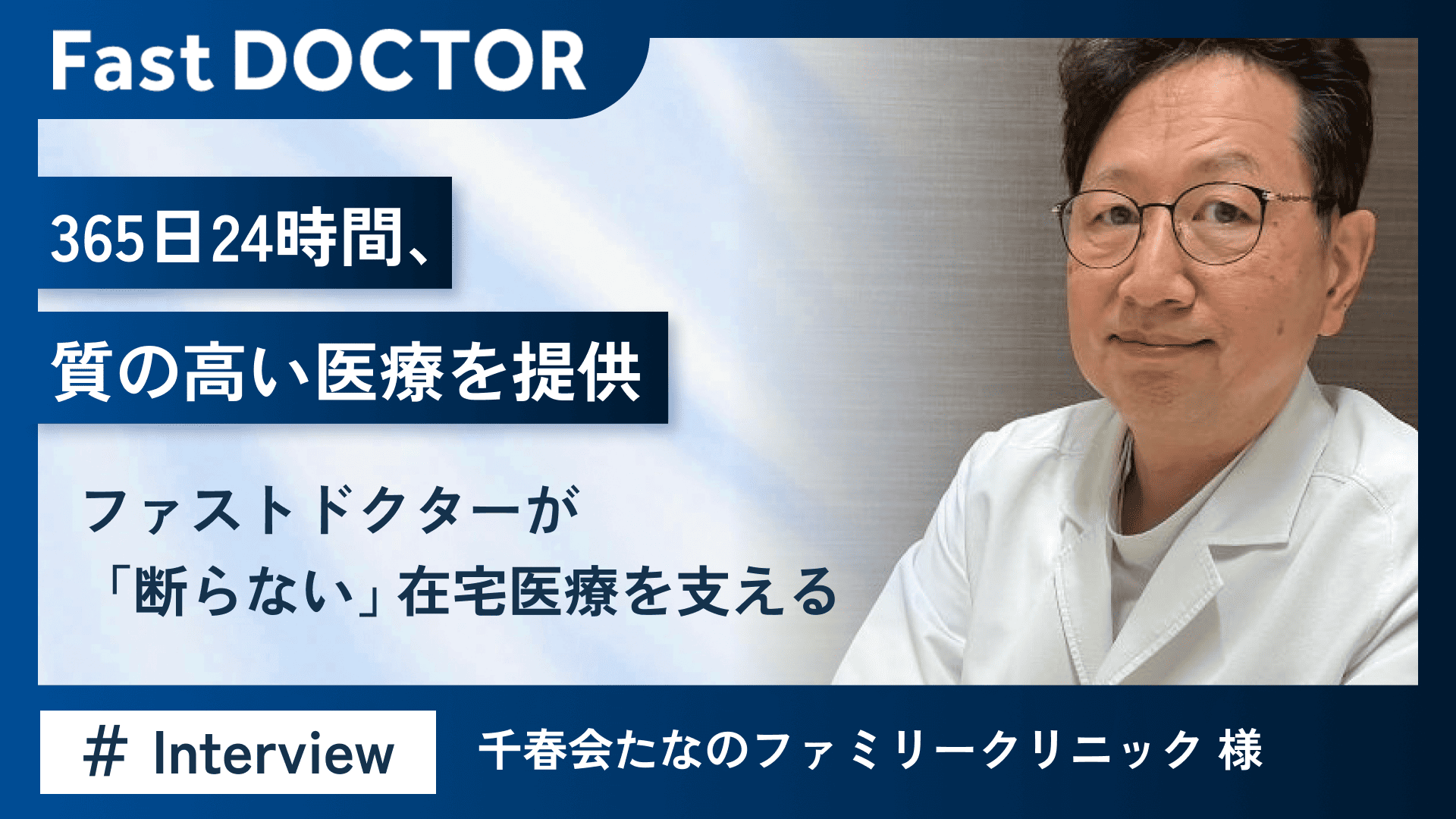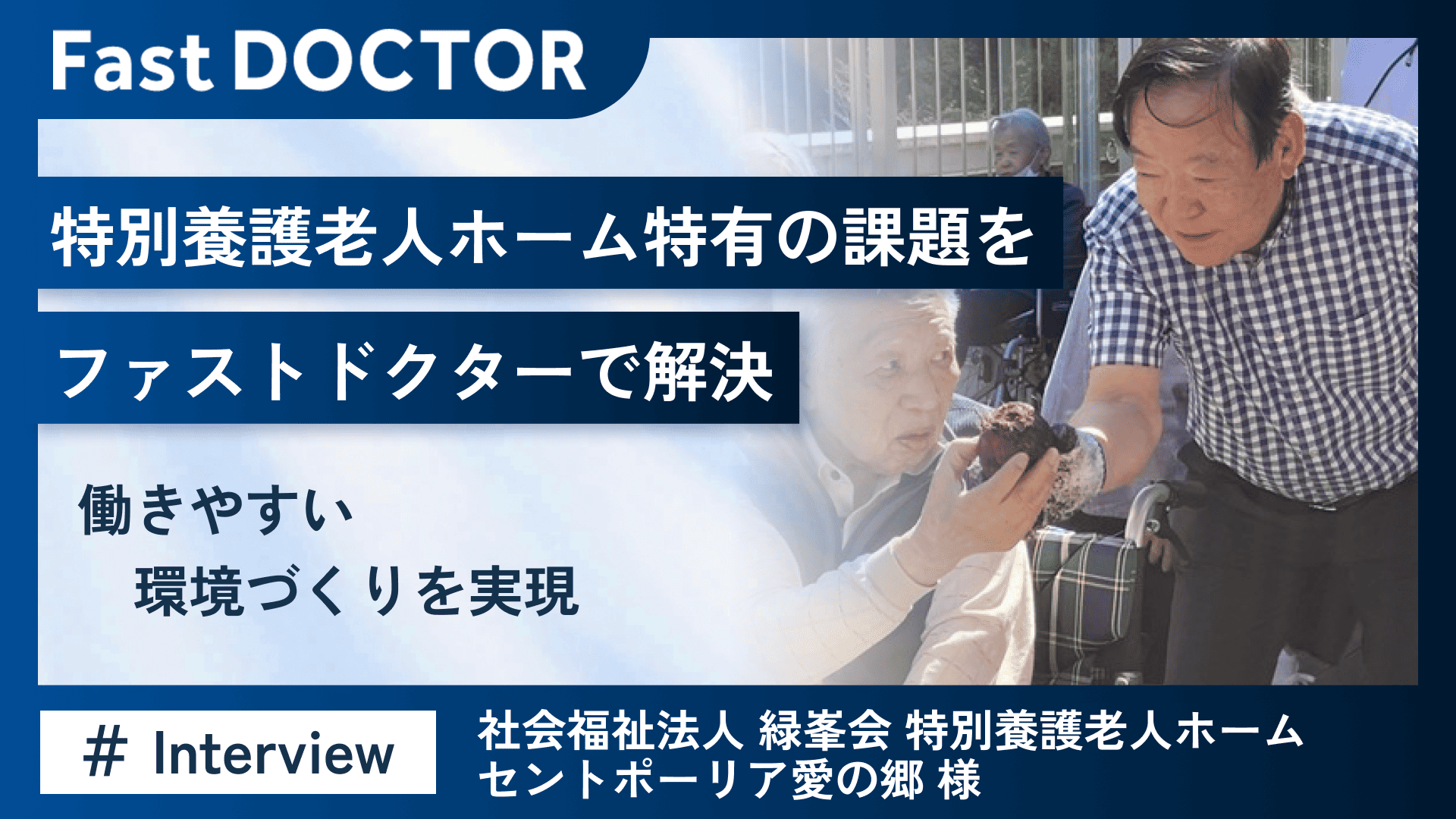北区における医療の未来と地域貢献への想い ~現代医療の問題を解決する必要不可欠のパートナー~
2024.08.28
2025.08.13
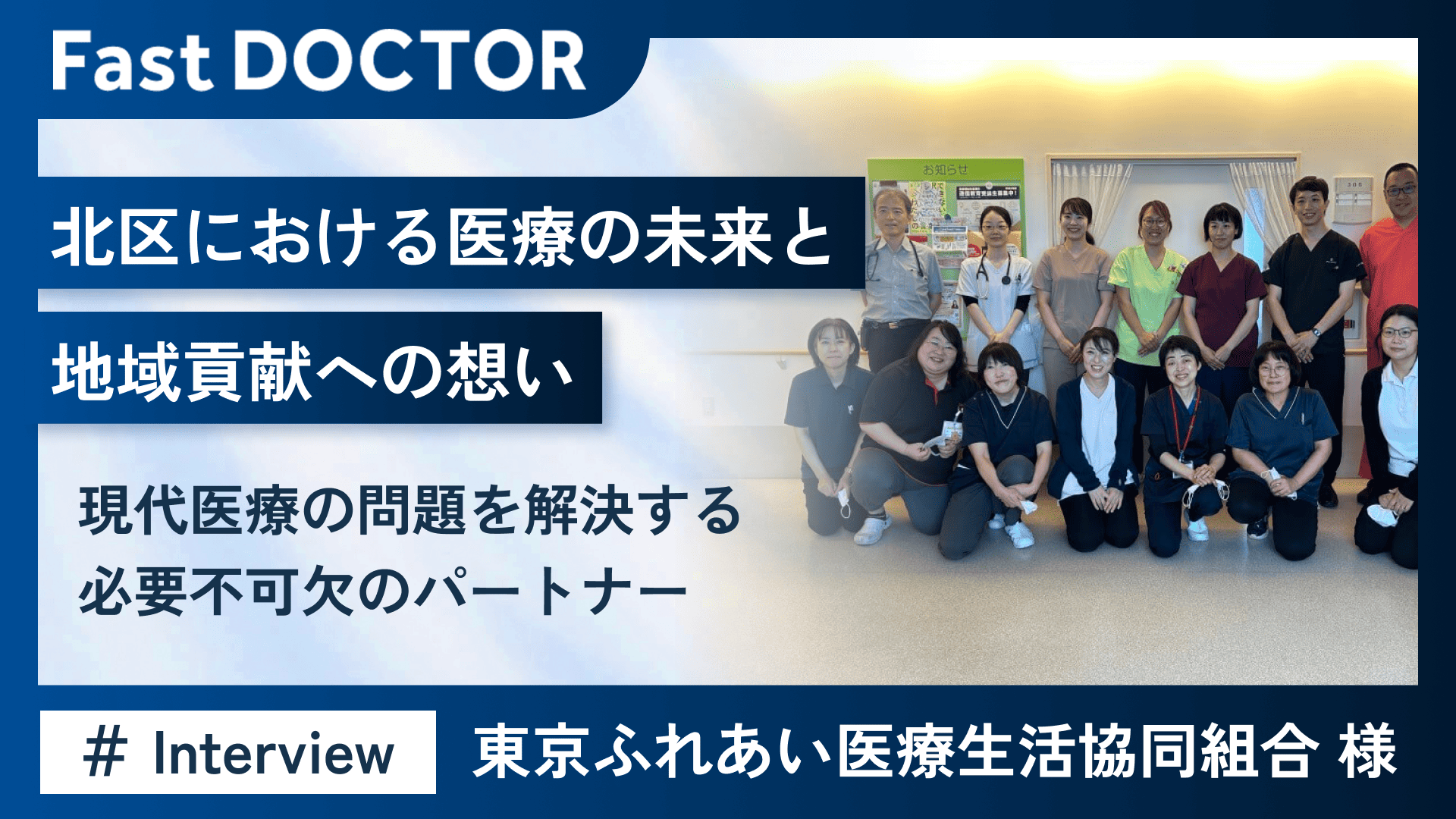

この記事の著者
医療機関プロフィール
| 組合名 | 東京ふれあい医療生活協同組合 |
| 診療所名 | 梶原診療所 宮の前診療所 オレンジほっとクリニック ふれあいファミリークリニック |
| 診療時間 | 梶原診療所 9:00~20:00(火曜日・金曜日) 9:00~17:00(月・水・木) 9:00~12:00 (土曜日) ※その他診療所の詳細はHPをご覧ください |
| HP | https://www.fureaico-op.info/ |

東京ふれあい医療生活協同組合は、教育に力を入れているため若手医師の入れ替わりが比較的激しい特徴があります。年によっては、オンコール対応できる医師の数が足りず”24時間365日”の往診体制の維持に課題がありました。
課題を解決するために、ファストドクターの時間外往診サポートのサービスを導入したことで、若手医師からも精神的・肉体的負担が軽減したと好評を得ています。
今回は「東京ふれあい医療生活協同組合」(以下、東京ふれあい医療生協)の研修・研究センター長である平原 佐斗司さまと常務理事の福地さまに、ファストドクターの導入に至った経緯やサービスの質の満足度など、ファストドクターに関するさまざまなお話を伺いました。
Q.東京ふれあい医療生協と一般的な医療法人との運営体制の明確な違いは何ですか?

東京ふれあい医療生協 常務理事福地さま(以下、福地さま):
一般的な医療法人は、医師が中心になって医療を構築する形です。しかし、我々は生活協同組合ですから、住民の方が受けたい医療を実現するために出資金を集めて、医療機関を設立している点が明確な違いになります。
その他に、一般的な医療法人は保険診療がメインの取り組みになりますが、生活協同組合の大きな目的は、地域や暮らしの向上であり健康づくりや医療・介護事業を軸に地域貢献したいと考えています。
地域の人々の健やかな暮らしを支援するために、健康づくりの諸活動や機関紙の発行、ボランティア活動など、さまざまな取り組みを実施しているのが特徴の一つです。現在では、約15,000人の組合員さまのおかげで、出資金がおおよそ4億円集まっています。
Q.東京都北区は医療においてどのような特徴を持つ地域なのでしょうか?

東京ふれあい医療生協研修・研究センター長 平原 佐斗司先生(以下、平原先生):
運営している4つの診療所のうち、母体となる「梶原診療所」と北区の認知症疾患医療センターである「オレンジほっとクリニック」が北区にあります。
北区の特徴として高齢化が進んでおり、かつ独居率が高い地域になります。他には、大きな病院が少なく、総じて医療資源が比較的乏しい地域です。
Q.東京ふれあい医療生協の強みをお聞かせください
平原先生:
東京ふれあい医療生協の最大の強みは、教育に力を入れていることによって「ぜひ、ここで学びたい」という若い医師が絶え間なく来てくれることです。
フェロー(※日本在宅医療連合学会の在宅医療専門医を取得する目的で、当院のプログラムに参加している医師)の方は、何かしらの専門的な知識を身に付けてから来ることが多いです。なので、領域によっては私よりも詳しいため、指導医にも新たな学びがあります。数名のフェローの方や常勤医・指導医の先生方によって、常に刺激し合いながら学び合う雰囲気が作れているのが特徴的です。
実際に、総合診療のプログラムとして在宅専門医を育てており、これまでに20名を超える専門医の輩出が実現できています。私がセンター長を務めている研修・研究センターでは、若手の医師をきちんとサポートする体勢が整えられているのが強みの一つです。
研修・研究センターで在宅医療を学んだ医師が北海道や広島・三重など、全国各地のさまざまな地域において、それぞれのやり方で地域医療に貢献しています。それが、我々の喜びでもあり誇りでもありますね。
また、我々は地域医療モデルで活動しているのも特徴です。専門クリニックのように、広範囲の患者さまを診るのではなく、あくまでも地域医療の一環としての在宅医療です。
そのため、地域の問題でニーズがあれば、疾患や状態にかかわらず、断ることなく受け入れます。私はこれを非選択的在宅医療と言っています。
我々を含む医師の学び合いによる刺激と、非選択性在宅医療による包括的な医療への知識によって、在宅医療の質が向上しているのが強みです。
Q.どのような課題を持たれてファストドクターの導入に至りましたか?
平原先生:
課題は”24時間365日”の訪問診療の体制を取るのが難しくなってきたことです。
我々は30年間ほど、常勤の医師で往診の体制を整えていました。若手の先生にも研修の一環として夜間や土日のオンコール対応していただいており、そこまで一人ひとりの負担が大きいものではなかったと思います。
我々のオンコールは、医師が一人で対応するという特徴があります。その中で、近年はやはりハラスメントの問題がありまして、女性医師が一人で夜間に訪問診療の対応をするのが非常に難しくなりました。
東京ふれあい医療生協が運営している4つのクリニックで計500名ほど、訪問診療の患者さまがいます。なおかつ、患者さまから一切呼ばれない日はありません。私自身が還暦を過ぎたこともありまして、訪問診療対応の体制維持が厳しくなっていたのが一番の課題でした。
上記の課題を感じている中で、ファストドクターのサービスを知り、クリニックの状況に合わせて利用できる点に魅力を感じて導入しました。
実際、土日だけでも訪問診療の対応を依頼することで、精神的・肉体的な面で負担が減り大変助かっています。
Q.在宅医療は医師の高齢化などさまざまな課題がありますが、実際にどのように感じていますか?

平原先生:
やはり外来中心のクリニックは、在宅医療との両立におけるハードルの高さから、規模が縮小しているのを感じています。
開業医の高齢化も進み、現在では平均年齢が61歳くらいですかね? 昔よりは、高齢化によって休日や夜間の訪問診療の対応が難しくなってきているのだと、周りの先生方を見ていて思います。
Q.ファストドクターを導入前にはどのような不安を抱えていましたか?
福地さま:
ファストドクター導入前は、担当している医師以外の先生が訪問診療を実施することで、患者さまがどのような反応をするのか読めない点が不安要素でした。
平原先生:
私は、医師の質の面で不安がありました。恐らく、在宅医療の経験があまり多くない先生も対応されるのだと思っていましたので。
ですが、カルテを読ませていただく限りきちんとした対応を実施いただいていますので、質も問題ないと感じています。
もちろん、在宅医のコンピテンシーは、病院で勤務する専門医のコンピテンシーと大きく異なります。在宅主治医として仕事をするためには、それなりの経験や研修が必須なことはいうまでもありません。
しかし、急性期のある局面だけ医学的に対応する場合は、医師としての基本的な能力が整っていれば十分であることに気づかされました。
もちろん、ファストドクターで対応してくれている中心世代が、初期研修制度後の若い先生方が中心で、総合的な研修を受けた世代であることも関係しているかもしれません。
福地さま:
実際にファストドクターの訪問診療サービスを利用して、サービスの質の面や患者さまの反応で大きな苦情やトラブルはありませんでした。普段と違う医師の方が夜間に訪問診療に来たことで、患者さまが動揺したという報告も、予想よりは少なかったので一安心です。
平原先生:
知らない医師が訪問診療に来ることは、患者さまも慣れているのだと思います。グループ診療を行っている医療機関では、土日のみ非常勤の医師が対応するというのは珍しくありません。
なので、ファストドクターのサービスに関しても、あまり違和感がなく患者さまも利用されたのではないかと思います。反対に、一人開業で一人の医師が診察から訪問診療まですべて対応しているケースでは、患者さまも慣れるのに時間がかかるのかもしれませんね。
Q.ファストドクター導入前には他のサービスと比較検討されましたか?

福地さま:
一社と相見積もりで比較検討しました。もう一社のサービスもインターネットの評判が非常に好評で、ファストドクターとどちらを導入するか迷っていたのを覚えています。
結果的にファストドクターのサービスを導入した決め手は、細かい疑問点への説明や我々の現状に合う見積もりの作成など、最後まで誠意をもって対応いただいた点です。
Q.人手不足の解消以外に思いもよらない改善につながったことがあればお聞かせください
平原先生:
ファストドクターは、クラウド型の電子カルテであるクリニックポータル(注:ファストドクターが自社開発している情報連携ツール)を活用して、我々の患者さまの最新情報だったり、訪問診療対応の完了報告だったりを連携します。
東京ふれあい医療生協は、元々サーバー型の電子カルテを利用していたので、情報をどのようにファストドクターのクリニックポータルに移すか、移したサマリーはきちんと伝わるのかというのが、最も課題であり苦労した点です。
しかし、苦労しただけでなく各常勤医が平常の業務の中できちんとしたサマリーを作るきっかけになりました。
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)についても、医師によって温度差がありましたが、サマリーの作成をきっかけに、より話し合ったり確認したりすることが増えたと思います。
電子カルテに情報を移す際に、きちんと患者さまにACPを聞いてクリニックポータルに情報を移すことが必要になったので、これは当初予想していなかった副次的な効果でした。
福地さま:
私はファストドクターを導入してから、若手の医師が「土日のオンコール対応がなくなっただけで、大幅にストレスが減った」という言葉を口にしているのをよく聞きます。
昔は、患者さまを24時間体制で診ることが当たり前という暗黙の了解がありましたが、現在では医師のワークライフバランスも重要と考えています。
当クリニックだけの話ではありません。地域全体で在宅医療の”24時間365日”体制を続けていくためには、ファストドクターのようなサービスが必要不可欠になるのではないかと感じています。
Q.今後、ファストドクターを活用してどのような在宅医療を目指していきたいと考えていますか?
平原先生:
やはり医療現場においても、DX化は欠かせません。さまざまな業務の効率化を進めながら供給体制を整備して、我々の地域で活動が楽しい、やりがいがあると思ってもらえる医師や看護師を増やすのが重要です。
我々のような在宅医療実施者とファストドクターのような往診サポートサービスがパートナーになって、日本全体を支えられるように機能していくのが理想的ですね。
Q.最後に、現在ファストドクターの導入を検討している在宅医療機関の担当者さまに向けて、メッセージをお聞かせください

平原先生:
ファストドクターは、現代の医療における問題を解決するために事業を続けているのが明確だと思います。そういった点で、私はファストドクターの考えに共感してサービスの導入を決めました。
実際に、ファストドクターへ往診をお願いして真摯に対応いただいています。勤務医の先生方からの評判も良く、何か困りごとがあるという話は聞いていません。ファストドクターの往診サービスを信頼していますので、検討している方はぜひ導入をおすすめします。


この記事の著者
関連記事RELATED