医師の長時間労働を改善する5つのコツ!長時間労働を引き起こす要因もあわせて解説!
2025.04.30
2025.06.11
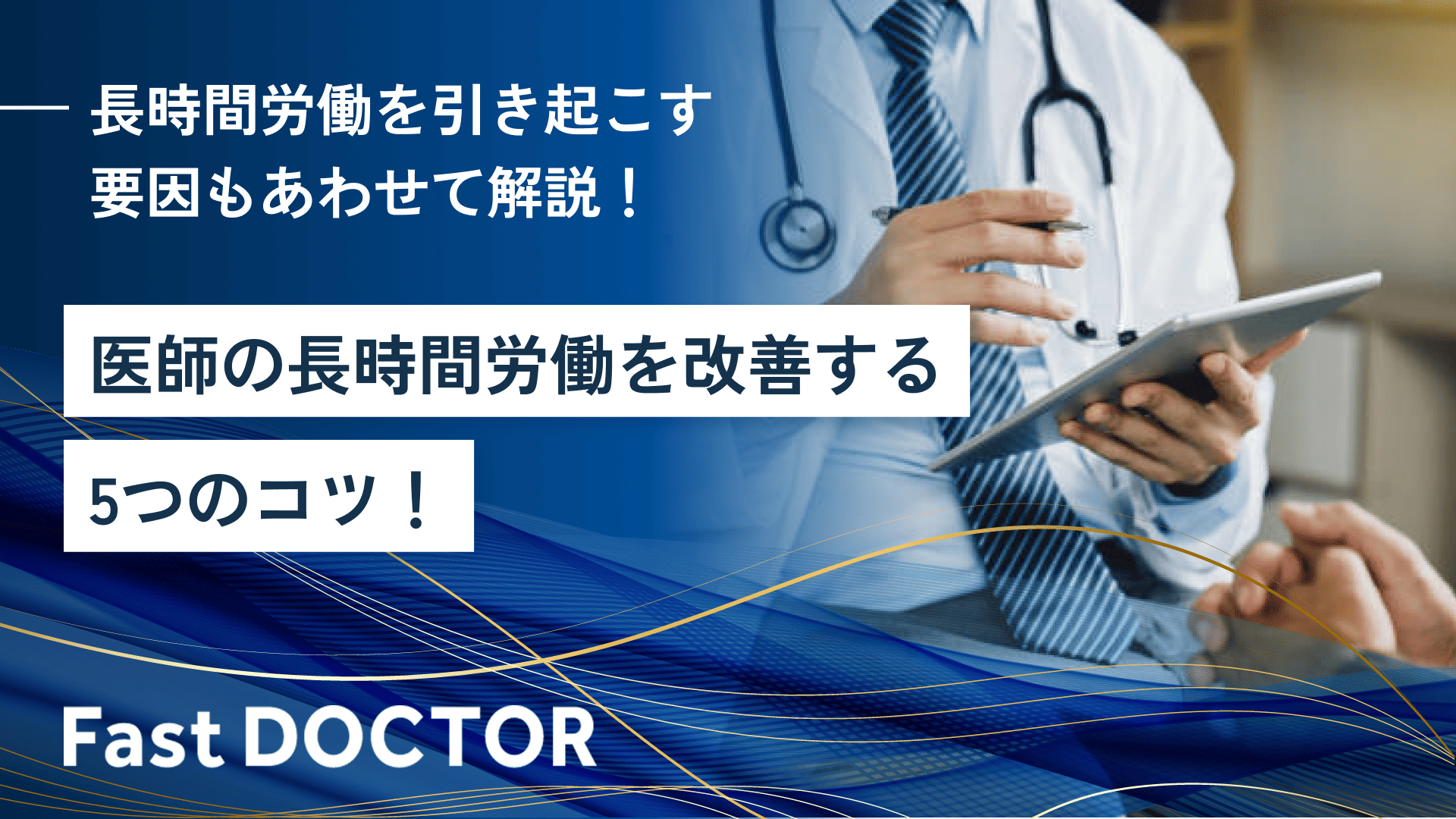
「医師の長時間労働を改善するコツが知りたい」
「医師の長時間労働を引き起こす要因は?」
このような疑問をお持ちの医療機関も多いのではないでしょうか。
2024年4月から始まった医師の働き方改革により、医療機関で働く医師の労働時間の遵守が求められています。
本記事では、医師の長時間労働を引き起こす要因や長時間労働を改善するコツを紹介します。医師の労働時間にお悩みの医療機関はぜひ参考にしてください。
なお、ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
医師の働き方改革により労働時間の遵守が必要
医師の働き方改革が進められる中、2024年4月から医師にも時間外労働の上限規制が適用されるようになりました。
医師の時間外労働の規制は、以下の3つの区分ごとで異なる上限が設けられました。
| 区分 | 対象 | 時間外労働の条件 |
| A水準 | すべての医師★診療従事勤務医 | 年960時間以下/月100時間未満(休日労働含む) |
| B水準 | 地域医療暫定特例水準 ★救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療機関 | 年1,860時間以下/月100時間未満(休日労働含む) |
| C水準 | 集中的技能向上水準 ★初期臨床研修医・新専門医制度の専攻医や高度技能獲得を目指すなど、短期間で集中的に症例経験を積む必要がある医師 | 年1,860時間以下/月100時間未満(休日労働含む) |
そのため、医療機関側は勤務体制や労務管理の見直しを迫られており、医師自身も効率的な働き方に意識を向けざるを得ない状況です。
一方で、医療現場では様々な要因から長時間労働が発生しやすい現実があり、実効性ある改革の推進には、現場の実態を理解した取り組みが欠かせません。
医師の長時間労働を引き起こす要因
医師が慢性的な長時間労働にさらされている背景には、いくつかの要因が挙げられます。
- 人手不足
- 患者と密接した関わり方
- 医師・看護師の自己研鑽
以下で、主な要因について詳しく解説します。
人手不足
医療現場における人手不足は、長時間労働の大きな要因の一つです。特に地方や中小規模の病院では、医師の数が十分に確保できていない状況が続いています。
その結果、限られたスタッフに多くの業務が集中し、一人あたりの負担が増加します。
また、急性期医療や夜間・休日の対応が必要な場面では、人員の不足がより深刻化しやすく、自己犠牲的に働かざるを得ない状況となります。
このような労働環境が常態化することで、医療従事者の体力的・精神的疲労が蓄積し、さらなる人材流出を招く悪循環にもつながります。
患者と密接した関わり方
医師は、患者の命や健康に直接関わる責任の重い職種です。患者一人ひとりの訴えや状況に丁寧に対応するためには、時間を惜しまず寄り添う必要があります。
そのため、診療やケアだけでなく、患者や家族への説明、精神的なサポートなど、多岐にわたる業務が生じます。
さらには、急変時の対応や緊急手術など、予測不能な業務も多く、勤務終了時間が後ろ倒しになることも珍しくありません。
このように、患者と密接に関わる医療の特性自体が労働時間の延長要因として作用しています。
医師・看護師の自己研鑽
医師は高度な専門知識と技術が求められる職業であり、自己研鑽の必要性が非常に高い分野です。
新しい医療技術や薬剤、ガイドラインの習得、学会参加や論文執筆など、日々学び続ける努力が不可欠です。
しかし、これらの自己研鑽活動は勤務時間外に行われることが多く実質的に労働時間が長くなります。
また、自発的な学びが評価される職場風土があるため、つい時間を割きがちになる傾向も見られます。
自己成長のための努力ではありますが、過度な負担となれば疲弊につながるため、バランスの取れた働き方が課題となっています。
医師の長時間労働が及ぼす悪影響

医師が長時間労働を強られる現状は、医師本人のみならず患者や医療現場そのものにもさまざまな悪影響を与えています。
- 身のストレスによる体調不良
- 医師・看護師の離職
- 職場環境の悪化
- 医療サービスの質低下
- 医療事故を起こすリスクの増加
ここでは、長時間労働がもたらす具体的な悪影響について詳しく解説します。
心身のストレスによる体調不良
長時間労働は肉体的な疲労に加え、精神的なストレスも蓄積させます。
特に医師は緊張状態が続くため、自律神経に悪影響を及ぼし、睡眠障害や食欲不振、消化不良などの身体的な不調を引き起こしやすくなります。
また、ストレスから免疫力が低下し慢性的な病気のリスクも高まります。
このような体調不良が続けば、専門職としての集中力や判断力の低下にもつながり、業務に支障をきたす恐れがあります。
医師の離職
過剰な労働時間や過酷な労働環境は、医師がモチベーションを失い、仕事を続ける意思を持てなくなる主な原因のひとつです。
心身の過労やストレスによりバーンアウト(燃え尽き症候群)を引き起こすことも少なくありません。
そうした状況が続けば、優秀な人材の離職が増え、医療現場にとって大きな損失となります。
経験豊富な医師の離職は、業務の円滑な引き継ぎや新人教育にも悪影響を及ぼす場合があります。
職場環境の悪化
長時間労働による職場環境の悪化は、医療スタッフのコミュニケーション不足やチームワークの低下につながります。
疲労が溜まることでイライラが募り、人間関係のトラブルが起こりやすくなります。
また、余裕を持った対応ができなくなるため、ミスやトラブルの発生率が高まる傾向も見られます。
こうした悪循環が繰り返されると、職場の雰囲気が殺伐とし、働く意欲のさらなる低下を招く結果となります。
医療サービスの質低下
医師が慢性的な疲労状態にあると、患者一人ひとりに十分な時間や心配りを注ぐことが難しくなります。
さらには、検査や治療の説明が簡略化されたり、確認作業が不十分になったりすることで、患者の満足度の低下やトラブルの原因となります。
質の高い医療サービスを提供するためには、医師が心身共に健やかな状態を保つことが欠かせませんが、長時間労働はその基盤を揺るがす危険性があります。
医療事故を起こすリスクの増加
過労による集中力や判断力の低下は、医療事故の発生リスクを著しく高めます。たとえば、薬剤の投与量の間違いや処置手順のミス、患者の情報管理の不備など、些細な不注意が重大な事故につながることがあるため注意が必要です。
また、疲労困憊の状態では迅速かつ的確な対応が難しくなり、緊急時に適切な判断ができなくなる恐れもあります。
医療現場の安全性を守るためにも、適切な労働時間の確保が不可欠です。
医師の長時間労働を解消する5つのコツ
医師の長時間労働は、医療現場における大きな課題の一つです。
過重労働は医師の健康障害やサービスの質低下を招くおそれがあるため、現場全体で改善策を考えることが必要です。
長時間労働を解消するために実践できる5つのコツを紹介します。
- 勤務時間・タスクを見える化して適正管理する
- 無駄な業務を思い切って省く
- マネジメント層の意識を変える
- 新しい勤務制度を導入する
- 一部の業務を外部委託して業務負担を減らす
これらをを取り入れることで、より健全な職場づくりに近づくことができます。それぞれ確認していきます。
勤務時間・タスクを見える化して適正管理する
働き方改革の第一歩は、勤務時間や日々のタスクを目で見て分かる形に「見える化」することです。
具体的には、シフト管理ソフトや業務記録表を活用し、スタッフごとの出退勤時刻や実際の業務内容を記録・共有します。
これにより、業務の偏りや無理な残業が発生していないか一目で把握でき、適切な人員配置やタスク配分が可能になります。
また、「何にどれだけ時間がかかっているか」を分析することで、効率化の余地も見つかりやすくなります。
無駄な業務を思い切って省く
毎日の業務の中には、必ずしも医師が担う必要のないものや、従来の慣習で継続しているだけの作業が含まれている場合があります。
例えば、会議資料作成、手書きでの記録、不要な書類の管理などが該当します。
これらの業務を一つひとつ見直し、本当に必要なタスクにだけ集中することで業務量の削減が可能です。
また、業務マニュアルを整備し、標準化することで、無駄な重複作業も減らすことができます。
マネジメント層の意識を変える
現場の働き方を本気で改善するには、医療機関の経営陣や管理職の意識改革が欠かせません。
トップダウンで「長時間労働ゼロ」を目指す姿勢を示すことで現場の行動も変わっていきます。
マネジメント層が積極的にスタッフの声に耳を傾けたり、定期的な面談や意見交換の場を設けたりすることが大切です。
新しい勤務制度を導入する
従来のシフト制だけに頼らず、時短勤務やフレックスタイム制、交替制勤務の導入など柔軟な働き方を取り入れることも有効です。
また、週休3日制やワークシェアリングの実践により、個々の負担を軽減できます。
新しい制度を導入する際は、現場の声を反映させた上で運用方法を明確にし、全員が理解・納得できるようなルールづくりを行いましょう。
制度の定着には時間がかかりますが、長時間労働の根本的な解決につながります。
一部の業務を外部委託して業務負担を減らす
医療現場で必要な事務作業や清掃、医療機器の管理など、一部の業務を外部業者に委託することで、医師・看護師が本来集中すべき医療行為により多くの時間を割くことが可能になります。
また、専門的なノウハウを持つ業者が作業を担うことで、業務の効率化や質の向上も期待できます。
外部委託を進める際には個人情報保護や安全面への配慮をしつつ、委託範囲や連携方法を明確にしておくことが重要です。
職場環境を見直して医師・看護師の長時間労働を改善しよう!
医師や看護師の長時間労働を改善するためには、勤務時間の削減や業務の整理だけでなく、働く環境そのものを見直すことも重要です。
オン・オフのメリハリをつけやすい労働環境の構築や休暇の取りやすさなどが働きやすさにつながります。
現場の声をしっかり把握し改善策を取り入れることで、スタッフの満足度と医療の質向上の両立を目指しましょう。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

関連記事RELATED







