新人看護師が仕事をやめる理由は?退職・転職を防ぐ対策を詳しく解説!
2025.04.30
2025.06.11
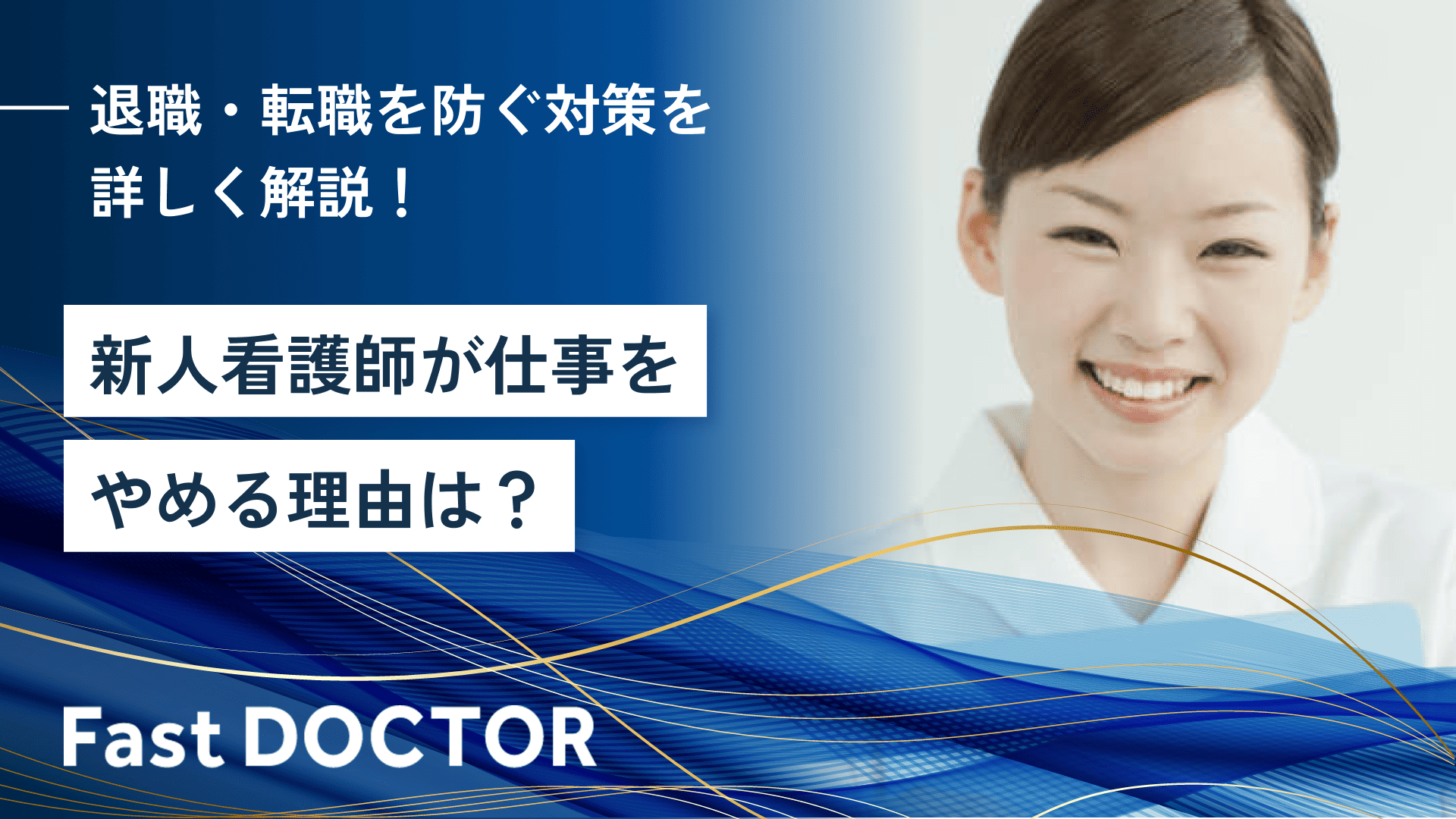
「新人看護師が仕事をやめる理由は?」
「新人看護師の退職・転職が医療機関に与える影響は?」
「新人看護師の退職・転職を防ぐ対策が知りたい」
このような疑問をお持ちの医療機関も多いのではないでしょうか?
看護師は心身に様々なストレスがかかる仕事であるため、特に新人看護師は離職率が高い傾向にあります。
本記事では、新人看護師が仕事をやめる理由や退職・転職を防ぐ対策を紹介します。新人看護師の離職にお悩みの方はぜひ参考にしてください。
なお、ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールなど新人看護師のストレスにつながる業務でお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
仕事を辞めたいと考えている新人看護師は10人に1人
新人看護師の中には、職場の環境や仕事のストレス、人間関係などさまざまな要因から「辞めたい」と感じる人が少なくありません。
2022年度の日本看護協会の「病院看護・助産実態調査」によると、2021年度の正規雇用看護職員のうち新卒採用者の離職率は10.3%という報告がされています。
最近の統計によると、新人看護師のおよそ10人に1人が、早い段階で退職を考えていることがわかります。
看護師という職業は社会的にも非常に重要な役割を担っていますが、慣れない業務や責任の重さから精神的負担を感じやすい職種とも言えるでしょう。
新人看護師が仕事をやめる8つの理由
新人看護師がせっかく念願の職場に就職しても、早期に退職を考えてしまうケースは珍しくありません。その背景には、現実と理想の違いや精神的・肉体的負担など、さまざまな理由が存在します。
まずは、実際に多い「新人看護師が仕事をやめる8つの理由」について、具体的に紹介していきます。
- 理想とのギャップが大きい
- 責任が重すぎる
- 医療事故への不安
- 職場の人間関係
- 人手不足による業務量の多さ
- 夜勤がある
- オンコールが嫌
- 残業代が出ない
それぞれ確認していきましょう。
理想とのギャップが大きい
看護師を目指す多くの人は、「患者さんに寄り添い、やりがいのある仕事がしたい」という理想を思い描いて就職します。
しかし現場では、忙しさからひとりひとりの患者と十分に関わる時間が持てなかったり、看護以外の雑務や書類仕事が多かったりして、「思っていたのと違う」と感じることが増えがちです。
このような理想と現実のギャップが大きいことが、新人看護師が仕事をやめたくなる一因となっています。
責任が重すぎる
新人看護師でも、患者の命や安全に関わる重要な業務を担う場面が多々あります。
そのため、ちょっとしたミスが患者さんの健康に大きな影響を与える可能性があり、精神的なプレッシャーは非常に大きいです。
「自分に任せて大丈夫なのか」「自分の判断が間違っていたらどうしよう」と、強い責任感から不安とストレスを感じる新人看護師は少なくありません。
責任の重さに耐え切れず、退職を考えることがあるのです。
医療事故への不安
どんなに丁寧に仕事をしていても、医療現場には常にリスクがつきまといます。
特に新人看護師は経験不足ゆえに、医療ミスへの不安が大きく「自分のせいで重大な事故が起きたらどうしよう」と思い詰めてしまうことも少なくありません。
この精神的な不安が重くのしかかり「もしものことがあったら耐えられない」と考えて退職を選ぶ人もいます。
職場の人間関係
看護の現場では、医師や先輩看護師など多くの人と連携しながら働きます。その過程で、指導の厳しさや先輩とのコミュニケーションの壁、派閥など、人間関係に悩む新人看護師は多いです。
いじめやパワハラのようなケースまで発展することもあり、「職場の雰囲気になじめない」「居場所がない」と感じて退職を考える人もいます。
職場環境のストレスは、新人看護師の定着率に大きく影響します。
人手不足による業務量の多さ
慢性的な人手不足に悩む医療現場では、新人看護師でも即戦力として働かざるを得ない状況が多くあります。
そのため、本来は段階的に覚えていくべき業務を一気に任されたり、時間外勤務や過度な業務負担を強いられたりするケースも多々あります。
自分の成長が追いつかないまま膨大な業務量に押しつぶされ、心身ともに疲弊してしまい、退職を考え始める新人看護師が増えているのです。
夜勤がある
看護師の仕事には夜勤が欠かせませんが、夜勤は体力的にも精神的にも大きな負担となります。
昼夜逆転の生活リズムや、夜間特有の緊張感によるストレス、十分な休息が取れないことで体調を崩す人もいます。
このような夜勤の負担から、「続けていく自信が持てない」と辞める決断をする新人看護師もいます。
オンコールが嫌
オンコールとは、勤務時間外でも病院からの呼び出しに備えて待機しなければならない制度です。
週末や夜間でも突然の呼び出しがあるため、常に気が抜けず、プライベートな時間にも不安がつきまといます。
「自分の時間が確保できない」「いつ呼び出されるかわからない」というストレスから、オンコールを苦痛に感じる新人看護師は多く、これが理由で離職を考えるケースも増えています。
残業代が出ない
医療現場では、残業が常態化しているにも関わらず、すべての時間に対してきちんと残業代が支払われないケースが散見されます。
「自主的な勉強会」や「引き継ぎ作業」の名目でサービス残業が発生しやすいのです。
実際に働いた時間に見合う給与がもらえないことへの不満や不公平感は、モチベーションの低下につながりやすく、これをきっかけに退職を検討する新人看護師もいます。
新人看護師の退職・転職が医療機関に与える影響
新人看護師が早期に退職や転職を選択することで、医療機関にはさまざまな悪影響が生じます。
- 人手不足による他の看護師の負担増大
- 夜勤やオンコールの体制の困難さ
- 育成コストの無駄
- 医療の質の低下
それぞれの影響を理解して適切に対策が取れるようになりましょう。
人手不足による他の看護師の負担増大
新人看護師が退職・転職してしまうと、その穴埋めをしなければならず、残る看護師に大きな負担がのしかかります。
シフトの調整が難しくなり、一人当たりの業務量が増加するだけでなく、休憩や有給取得も難しくなります。
その結果、現場の看護師たちの心身の健康が損なわれ、さらに離職を促す悪循環が生じることがあります。
こうした負担増は、現場全体のモチベーションや働きやすさにも大きく影響します。
夜勤やオンコールの体制の困難さ
新人看護師の退職や転職が相次ぐと、夜勤やオンコール体制の維持が非常に困難になります。
人手が足りなくなることで夜勤のシフト変更や回数が増加し、残った看護師の負担がさらに大きくなります。
本来は複数人で交代しながら対応すべきところを少人数で回す必要があるため、体力的にも精神的にも大きなストレスがかかります。
その結果、夜勤体制そのものが崩れ、患者への対応力も弱まるおそれがあります。
育成コストの無駄
医療機関は新人看護師を一人前に育てるために、多くの時間や費用、人材を投じています。
しかし、せっかく育成した看護師が早期に辞めてしまうと、それまでかけたコストが無駄になってしまいます。
加えて、また新たに人員を確保し、最初から育成し直す必要があり、医療機関にとっては大きな負担です。
そのため、安定して人材を確保し続けることが経営面でも重要となります。
医療の質の低下
新人看護師の退職や転職が続くことで、現場の医療の質が下がる懸念があります。
人手不足により、一人ひとりに割ける時間が減り、ケアの質が落ちるほか、慣れないスタッフばかりではミスのリスクも高まります。
また、経験豊富なスタッフに比べ、知識や技術が未熟なままのスタッフが増えることで患者対応の柔軟性やチームワークにも影響が出ます。
医療機関の信頼性を維持するためには、安定した看護体制が不可欠です。
新人看護師の退職・転職を防ぐために医療機関ができる対策
新人看護師が早期に退職や転職を選ぶ背景には、職場での不安やストレス、環境への適応の難しさなどが挙げられます。
医療機関としてはこうした悩みを最小限に抑え、長く働いてもらえる環境づくりが不可欠です。
新人看護師の退職・転職を防ぐために医療機関ができる対策を4つ紹介します。
- 新人のフォロー体制を手厚くする
- 一人ひとりの成長をサポートする環境を作る
- 手当ての増加など待遇面を良くする
- オンコール代行会社を利用する
それぞれ確認して取り入れてください。
新人のフォロー体制を手厚くする
新人看護師は、業務に慣れるまでの間に多くの戸惑いや不安を抱えやすいため、手厚いフォロー体制が求められます。
たとえば、定期的な面談、勉強会の開催など、困ったことがあればすぐに相談できる環境を整えることが重要です。
また、先輩看護師が積極的に声をかけたり、失敗を責めるのではなく成長を促す声掛けを心掛けたりすることで、職場への安心感が生まれます。
こうした取り組みによって、新人看護師が孤立せずに自信を持って成長できる職場環境を作ることが大切です。
一人ひとりの成長をサポートする環境を作る
看護師として成長する過程は人それぞれ異なります。そのため、画一的な教育ではなく、一人ひとりの得意分野や苦手分野、将来のキャリア志向を把握したうえで個別にサポートする環境づくりが不可欠です。
個人別の面談やフィードバックを取り入れ、目標設定を共に行いながら仕事に取り組むことがポイントです。
また、研修や資格取得のチャンスを与えたり、成長を認め合う風土を醸成したりする工夫も効果的です。
こうした支援により、新人看護師は自分の強みを見つけながら安心して働き続けることができます。
手当ての増加など待遇面を良くする
待遇面での不満が新人看護師の退職理由となるケースも少なくありません。
基本給や夜勤手当、資格手当の見直しはもちろん、通勤手当や食事補助など細かな制度も充実させると良いでしょう。
また、福利厚生の拡充や、ワークライフバランスを保つための有給取得推進、短時間勤務制度の導入も効果が期待されます。
経済的・生活面での安心感があると、看護師は腰を据えて職場に取り組むことができます。待遇の改善に積極的に取り組むことが、長期的な定着につながります。
オンコール代行会社を利用する
夜間や休日のオンコール対応は、看護師にとって大きな負担となり、離職の原因となることがあります。
オンコール代行会社を活用することで、スタッフの負担を軽減し、肉体的・精神的な疲労を減らすことができます。
特に小規模な医療機関ではオンコール代行を導入することでスタッフのワークライフバランス向上に大きな効果が期待できます。
オンコールのシフトへのストレスを減らすことで、職場全体の定着率向上にもつながります。
新人看護師自身で取れる対処法
新人看護師として現場に立つと、緊張や不安、さまざまなプレッシャーを感じる場面が多いものです。
しかし、その不安や悩みを少しでも和らげるために、自分で実践できる対処法を知っておくことは大切です。
- 完璧を求めすぎない
- 悩んだ際は1人で抱え込まない
- 十分な休息をとる
自分に合った方法を取り入れて、無理なく業務を続けることが成長につながります。
完璧を求めすぎない
看護師になりたての頃は責任感から「失敗してはいけない」「完璧にこなしたい」と強く思いがちですが、最初から全てを完璧にできる人はいません。
ミスをしたり、分からないことがあったりするのは当然のことです。大事なのは、失敗を恐れすぎず、その経験から学ぶ姿勢を持つことです。
自分の成長段階を認め、できることを一つずつ丁寧に積み重ねる意識を持つことで、少しずつ自信もついてきます。
悩んだ際は1人で抱え込まない
慣れない職場や仕事の中で悩みを感じても、それを1人で抱えてしまうと心身の負担が大きくなってしまいます。
些細なことでも、先輩や同期、他のスタッフに相談することで客観的な意見やアドバイスが得られ、不安が軽減することが多いです。
相談することは決して弱さではなく、よりよい看護を提供し成長するために必要な行動ですので、積極的に周囲とコミュニケーションをとるように心がけましょう。
十分な休息をとる
看護師は心身ともに負担の大きな仕事です。睡眠不足や疲労が蓄積すると、ミスのリスクが高まり、気持ちも不安定になりがちです。
無理をせず、仕事以外の時間ではしっかりと休息をとり、好きなことに没頭する時間を持つことも重要です。
また、適度な運動や食事にも気を配り、生活リズムを整えることで、心身の健康を保ちやすくなります。
自身の健康管理を意識することが、長く看護の現場で活躍する基盤となります。
働きやすい職場環境構築が医療の質を高める
職場の雰囲気やサポート体制は、新人看護師一人ひとりの働きやすさに大きく影響し、ひいては提供される医療の質にも直結します。
安心して働ける職場ではスタッフ間のコミュニケーションが円滑になり、ミスの防止や迅速な対応が可能となります。
また、互いに助け合える環境があることで、スタッフは自信を持って患者に接することができ、より良い医療サービスの提供が実現するでしょう。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
夜間休日の往診やオンコールなど新人看護師のストレスにつながる業務でお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

関連記事RELATED







