遠隔医療の課題を解説!医療格差の現状や遠隔医療を行うメリット、今後の必要性とは
2024.08.23
2025.05.26


この記事の著者
遠隔医療とは、情報通信技術を活用して地域に関係なく平等に医療を提供することです。遠隔医療の実施により、へき地や過疎地域にも医療を提供できたり、院内感染のリスクを低下させられるなど大きなメリットがあります。しかし、セキュリティ管理の問題や必要なシステムの教育など、実施するためには課題が生じます。
本記事では、遠隔医療の目的や実施するメリット、遠隔医療の今後のメリットなどについて解説します。
遠隔医療の導入によって得られるメリットや課題解決策が知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
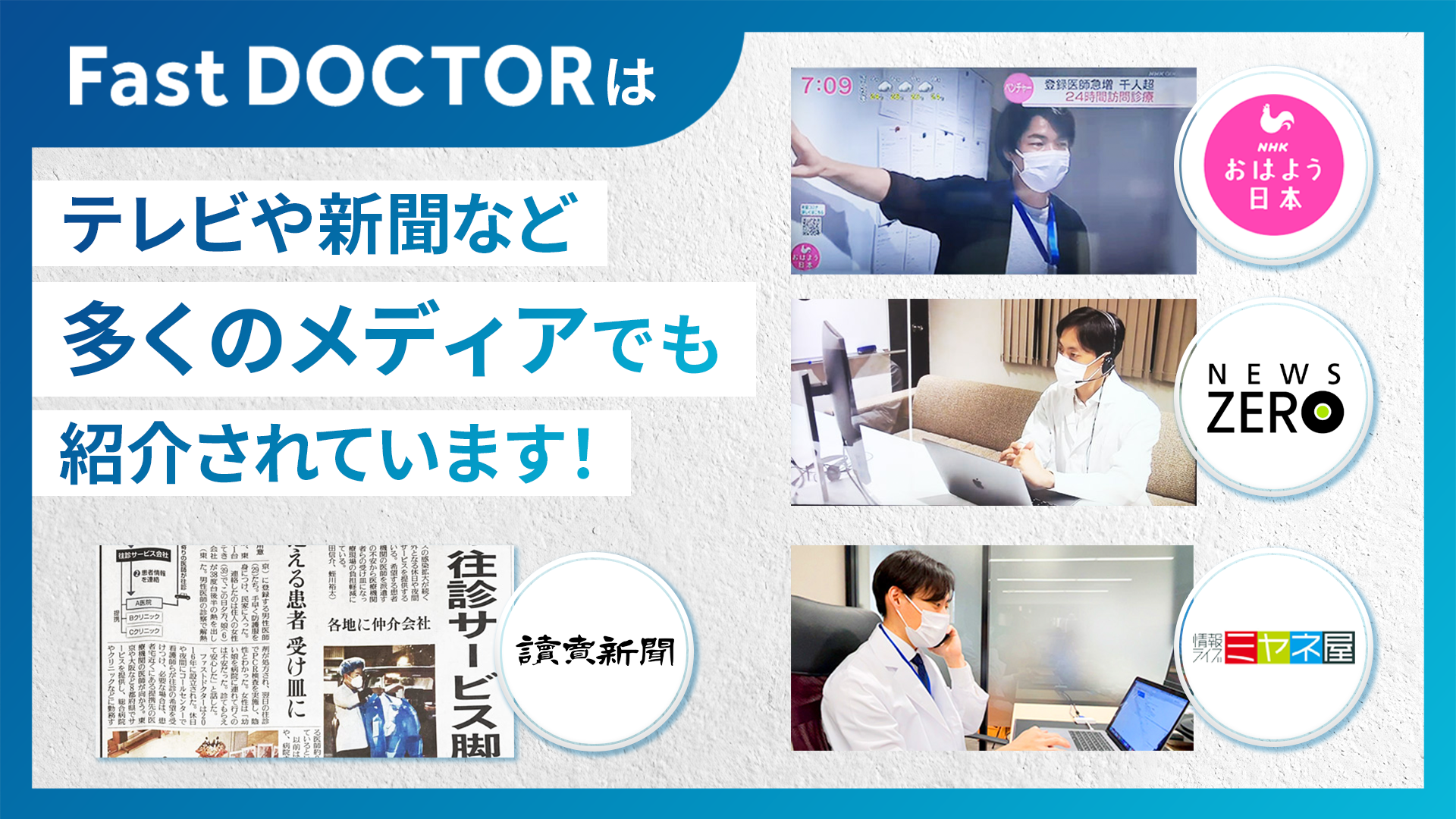
遠隔医療とは?
遠隔医療について、以下2つに分けて解説します。
- 遠隔医療の定義と概要
- 遠隔医療の役割と目的
遠隔医療の定義と概要
遠隔医療とは、情報通信技術を活用して地理的な障壁を超えて医療サービスを提供することです。
遠隔医療は、以下4つの形態に分けられます。
| 形態 | 概要 |
| D to P(医師対患者) | ・遠方にいる患者にオンラインで医師が診察や治療を行う |
| D to P with Dまたは医療従事者(医師対患者・医療従事者) | ・患者側に主治医や看護師、介護士など医療従事者が同席するケース・医師と医療従事者間の情報共有ができる・患者と医師間のスムーズな意思疎通が実現する |
| D to N(医師対医療従事者) | ・看護師が遠方の医師からの指示やアドバイスを受けられ、可能な範囲の検査や処置を行う |
| D to D(医師対医師) | ・遠方にいる専門医の指示を仰げる・若手医師の教育や相談ができる・遠方にいても患者の情報共有ができる |
患者への診断や治療だけでなく、患者に関わる医療従事者同士の情報共有や医療教育も、遠隔医療には含まれています。
厚生労働省「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」
遠隔医療の役割と目的
遠隔医療の役割は、医療従事者や介護従事者など患者の治療・ケアに関わる人達が、場所を問わず迅速かつ円滑に必要な情報を伝達・共有できるような環境を整えることです。
この役割によって、地域に関係なく平等に医療を提供できる環境の実現が期待できます。
本来であれば、地域関係なく患者の周りに医療機関などが整備され、必要なときに医療を提供できるのが理想です。しかし、高齢化や医師不足・医師偏在などの問題で実現が難しい地域もあります。
医療の提供が難しい地域でも医療にアクセスしやすくなり、患者に必要な医療を提供できるようにすることを目的として遠隔医療が実施されています。
参照:総務省「遠隔医療モデル参考書‐オンライン診療版改訂版」
遠隔医療を実施する3つの大きなメリット
遠隔医療を実施すると、以下3つのメリットが得られます。
- へき地や過疎地域、離島にも医療が提供できる
- 医療機関のコスト削減と効率化が期待できる
- 感染症に罹患するリスクが低下する
それぞれのメリットについて、くわしく解説します。
へき地や過疎地域、離島にも医療が提供できる
遠隔医療は、医療機関を受診しなくても診察や治療が可能なため、医療機関が少なかったり医療従事者が足りなかったりするへき地や過疎地域、離島にも医療の提供が可能です。
へき地や過疎地域、離島だと医療機関がなく、通院のために何時間もかけて移動する必要があります。特に、高齢者が1人で移動するには負担が大きく、その影響でで通院をやめてしまうケースも少なくありません。
また、医師が出張で訪れたとしても、1回に診察できる人数が限られていたり、災害などで出張できなかったりと、多くの人に必ず医療が提供できるとは言い切れないでしょう。
遠隔医療は移動の負担がなくなるため、へき地や過疎地域、離島でも定期的に医療をうけることが可能です。
医療機関のコスト削減と効率化が期待できる
遠隔医療は、医療機関のコスト削減と効率化が期待できるというメリットもあります。
遠隔医療だと、物理的な診療スペースやスタッフの需要が減少し、訪問診療や往診で発生する移動費もかかりません。実際、利尻島の遠隔医療では、眼科の場合だけで約13億円の費用削減につながったという結果も出ています。
加えて、遠隔医療は医師の患者宅への移動がなくなるため、移動時間を事務作業やスキルアップのために利用できるでしょう。また、専門医の指示を仰げることで専門外の診断を下すストレスも軽減できます。これらは、医師の負担軽減につながり働き方改革にも貢献できます。
また、遠隔診療であれば、時短勤務やパート勤務など時間に制限のある医師でも対応可能のため、在籍している医師のなかで勤務医は手術を、パート医師は遠隔診療をなどと役割分担が可能となります。
感染症に罹患するリスクが低下する
感染症に罹患するリスクが低下するのも、遠隔医療のメリットです。
対面診療の場合、医師と患者が直接接触するため感染するリスクが高まります。また、医療機関には多くの患者や医療従事者がいるため、感染症がうつる可能性も高いでしょう。高齢者の場合、感染症が重症化して生活レベルが低下する恐れもあります。
しかし、遠隔医療は医療機関に行く必要がなく医師との接触もないため、感染症のリスクが大幅に下がります。
日常的に遠隔医療を実施して感染症の蔓延を防ぐことも重要ですが、特に感染症が流行っている時期は、少しでも罹患するリスクを下げるために遠隔医療を活用したほうが良いでしょう。
遠隔医療が抱える課題と解決策
遠隔医療にはメリットがありますが、課題もあります。ここでは、以下3つの課題の解決策を紹介します。
- ITリテラシーと技術的な難易度
- 診療の質と緊急時対応
- 法規制とプライバシー問題
ITリテラシーと技術的な難易度
遠隔医療の課題の1つに、医療従事者と患者双方のITリテラシーと技術的な難しさがあります。
遠隔医療では、オンライン診療のためにパソコンやスマートフォンなどの通信機器が必要です。加えて、アプリケーションの立ち上げやボリューム調整などの操作も実施できなければいけません。そのため、技術に不慣れな患者や医師は、遠隔医療のためのシステムを操作するのに苦労する可能性があります。
医療機関側は、使いやすいシステムを導入する、遠隔医療に必要なシステムのレクチャーや勉強会を実施するなどして、円滑に遠隔医療が実施できるような体制を整えましょう。
ちなみに、オンライン診療を実施する医師は厚生労働省の研修を受講する必要があるため、受講を忘れないよう医師にアナウンスしましょう。
また、患者には家族や訪問看護師、介護士などの力をかりて、遠隔医療実施前に必要機器の操作方法をレクチャーすることをおすすめします。
参照:総務省「遠隔医療モデル参考書‐オンライン診療版改訂版」
診療の質と緊急時対応
遠隔診療には、緊急時にどう対応するかの課題があります。
遠隔診療は、目の前に患者がいるわけではないため、緊急時に即座に対応することが難しい場合があります。しかし、医師は患者の安全が確保されるよう適切な対応をしなければいけません。
そのために、急変時の救急車やドクターヘリ、ドクターカーの手配方法など対応フローを確立しておきましょう。加えて、搬送先の医療機関に患者情報が提供できるようなシステムを導入をしておくと、処置までの時間が短縮できます。
また、遠隔医療だけでなく定期的に対面診療を実施して、患者の状況を把握することも重要です。遠隔医療はあくまで対面診療の補助的な役割ということを頭に入れておきましょう。
参照:厚生労働省「遠隔救急支援システムを活用した救急医療体制について」
法規制とプライバシー問題
法規制とプライバシー問題も、遠隔医療の抱える課題です。
遠隔医療を実施する際は、患者のプライバシー保護とデータセキュリティが必須のため、医療機関全体でセキュリティを向上させる必要があります。
遠隔医療のためのシステム管理を、利用する診療科の医師が担当している場合もあるでしょう。しかし、医師だけでは専門知識がなくセキュリティ管理が手薄になっている可能性があります。セキュリティ管理が手薄になっていると、個人情報が流出したりウイルスに感染したりとトラブルが起こりかねません。
トラブルに発展しないために、医療機関内にIT部門やセキュリティ管理部門を設けるのも1つの方法です。新たに部門を設立するのはコストがかかりますが、リスク管理を考えると必要経費でしょう。
参照:総務省「遠隔医療モデル参考書-医師対医師(DtoD)※の遠隔医療版-」
遠隔医療の今後の未来と展望は?
遠隔医療によって、今後は以下2つの未来が待っていると考えられます。
- 技術進化の影響を受けて推進されていく
- 医療格差の是正が期待できる
それぞれの展望について解説します。
技術進化の影響を受けて推進されていく
遠隔医療は、5GやAIなど技術進化の影響を受けてさらに推進されていくと考えられます。
大容量の情報を超高速でリアルタイムで届けられる5Gによって、光回線が届いていない地域の医療機関でもデータ量の多い映像や画像がスムーズに通信できるようになるでしょう。それによって、オンライン環境が整っていない患者宅からでも、精度の高い映像や画像で患者の状態把握が可能となります。
また、AIの診断精度が向上し医師が診断補助としてAIを活用できるようになれば、1人で診断するという精神的負担の軽減にもつながるでしょう。
参照:総務省「遠隔医療モデル参考書-医師対医師(DtoD)※の遠隔医療版-」
総務省「5G等の医療分野におけるユースケース(案)【改訂版】概 要」
医療格差の是正が期待できる
遠隔医療が推進されていくことで、へき地や離島などにも医療の提供が可能となり医療格差の是正が期待できます。
また、患者対医師だけでなく医師対医師の遠隔医療も活用することで、地方にいながら高いスキルを学べるようになるため、都市部に医師が集まることが減り地方の医師確保にも役立つでしょう。
地方の医師が増えていけば、遠隔医療の緊急時にドクターヘリなどで対応できる医療従事者も確保でき、当該地域の医療の質向上にもつながります。
遠隔医療によって医療格差が是正されれば、どの地域でも平等に医療が提供できるようになるでしょう。
医療格差を是正するために遠隔医療を実施しよう
遠隔医療の定義や目的、遠隔医療の実施するメリット、遠隔医療が抱える課題と解決策などについて解説しました。
遠隔医療は、情報通信技術を活用して地理的な障壁を超えて医療サービスを提供することです。遠隔医療を実施するとへき地や離島などにも医療を提供できたり、コスト削減や効率化ができたりと大きなメリットが得られます。
一方で、ITリテラシーの教育や緊急時の対応方法の確立、セキュリティ管理部門の設立など、準備すべきことが多くあります。
医療格差の是正が期待できる遠隔医療は、技術進化とともに推進されていくと思われるので、今から遠隔医療の導入を検討していきましょう。
ファストドクターでは、夜間休日の往診を解消するために、現場を知る往診医やスタッフが往診・オンコールをワンストップで代行します。低コストかつ低リスクで24時間体制を貴院とともに作り上げ、切れ目のない医療の提供が可能となります。
提携医療機関数は641機関を突破しており、委託患者数は93,700人以上、5都市6医師会と契約を結んでいます。多くの医療機関で導入されている実績があり、提携後、離職率や働き方の改善を実感していただいております。
また、現在ファストドクターでは在宅医療を行う医療機関者様を対象に、無料トライアルを含めた特別キャンペーンを実施しています。夜間休日の往診やオンコールでお悩みの場合は、ぜひご相談ください。
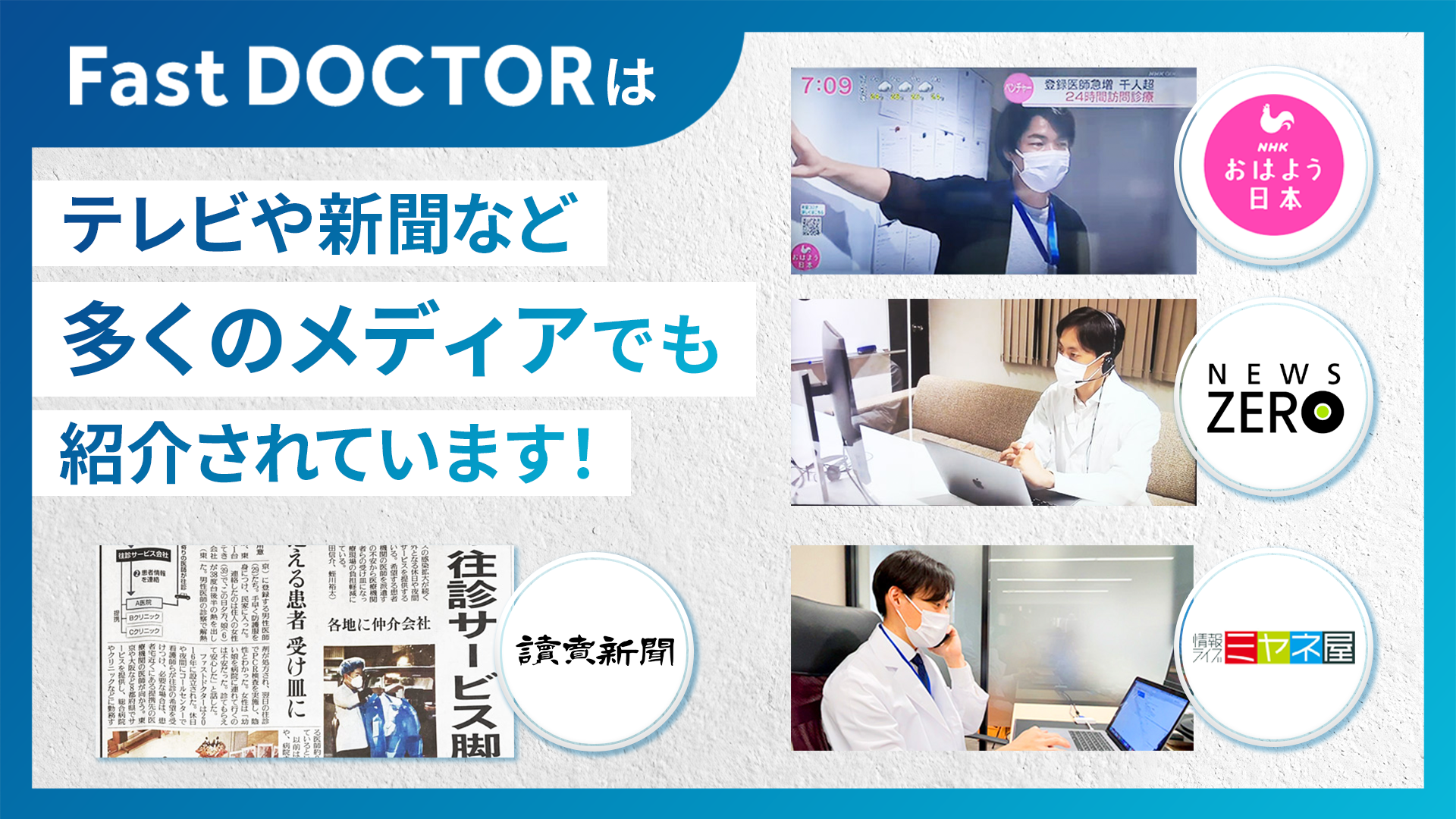


関連記事RELATED







