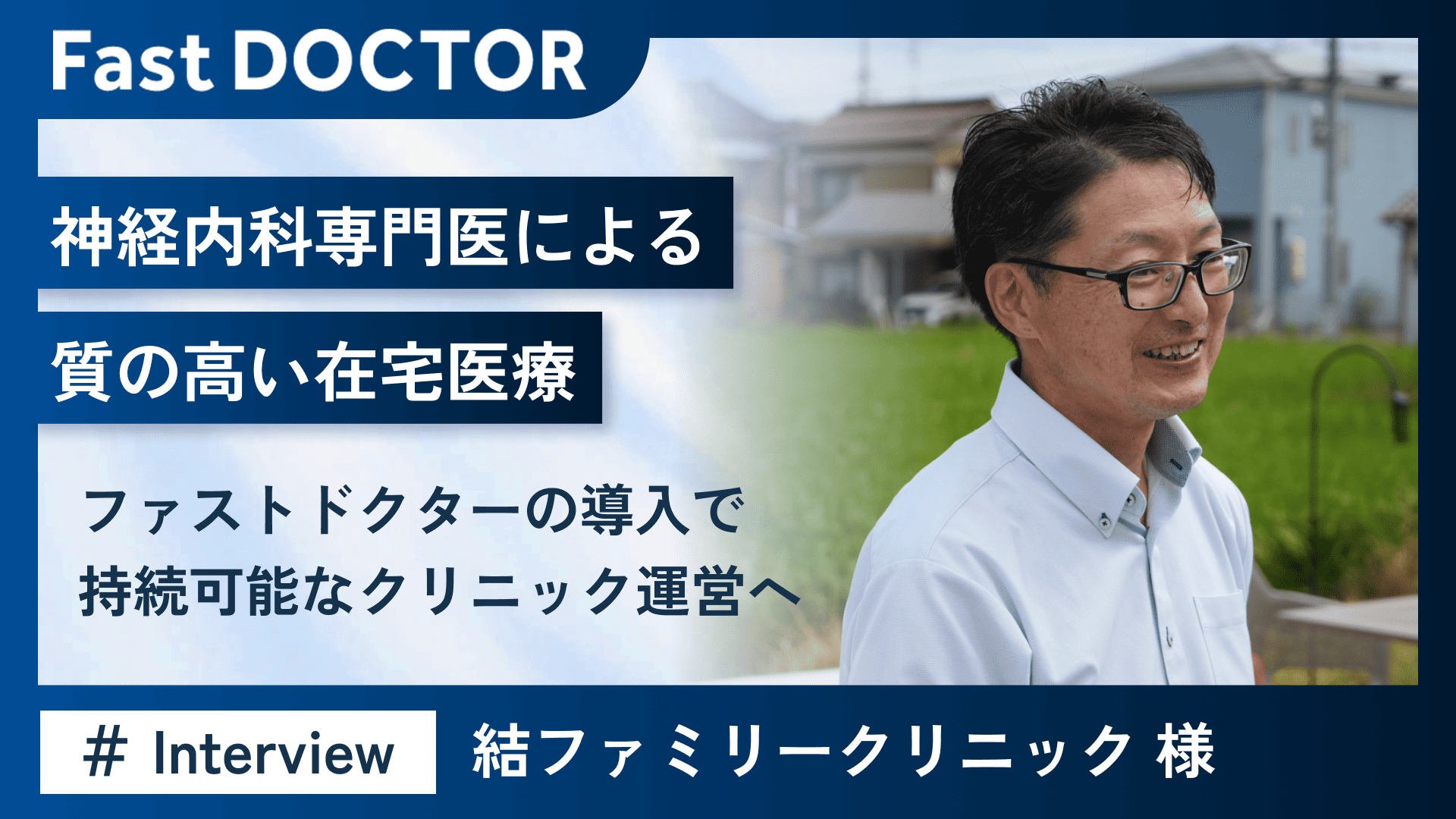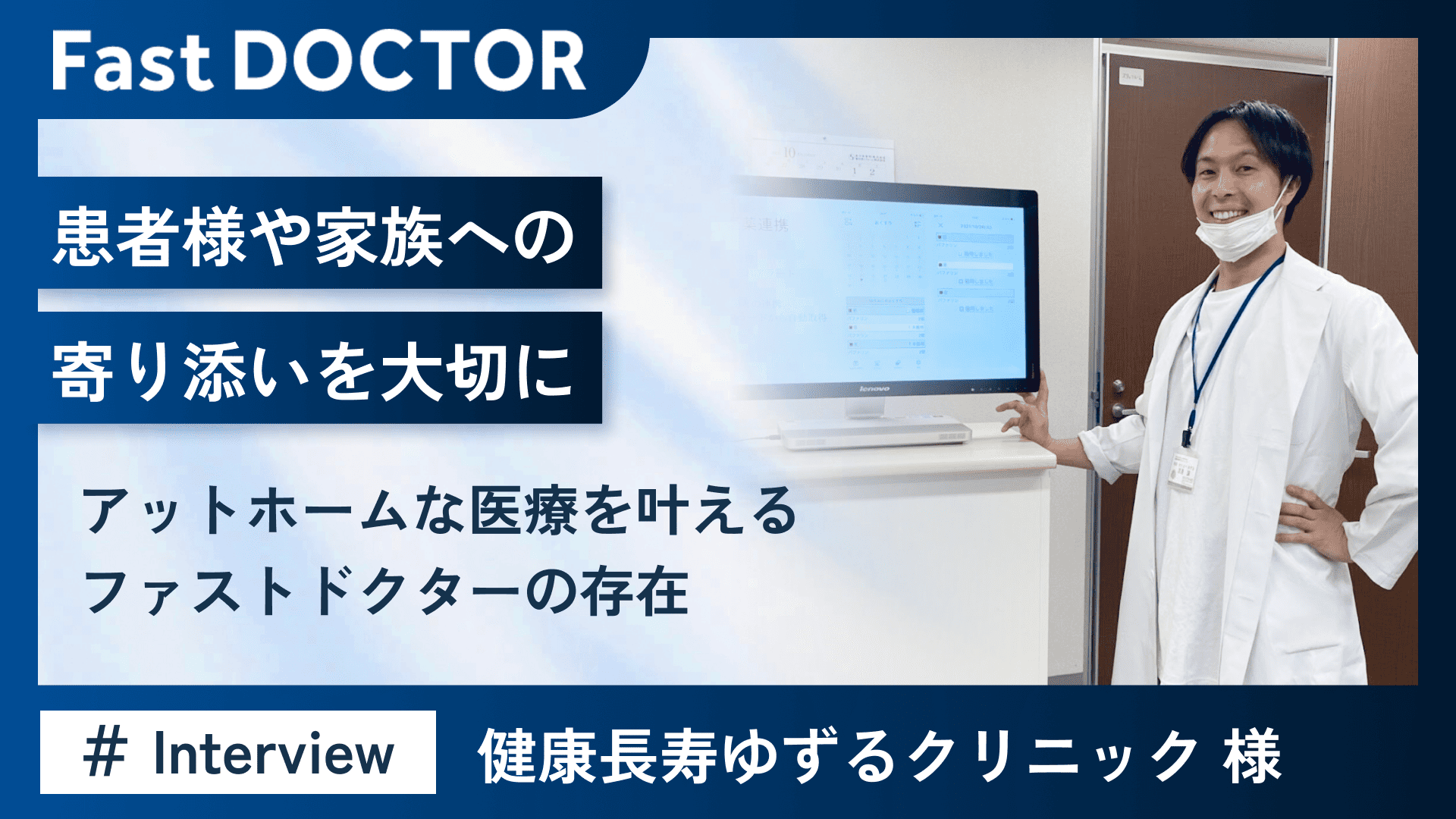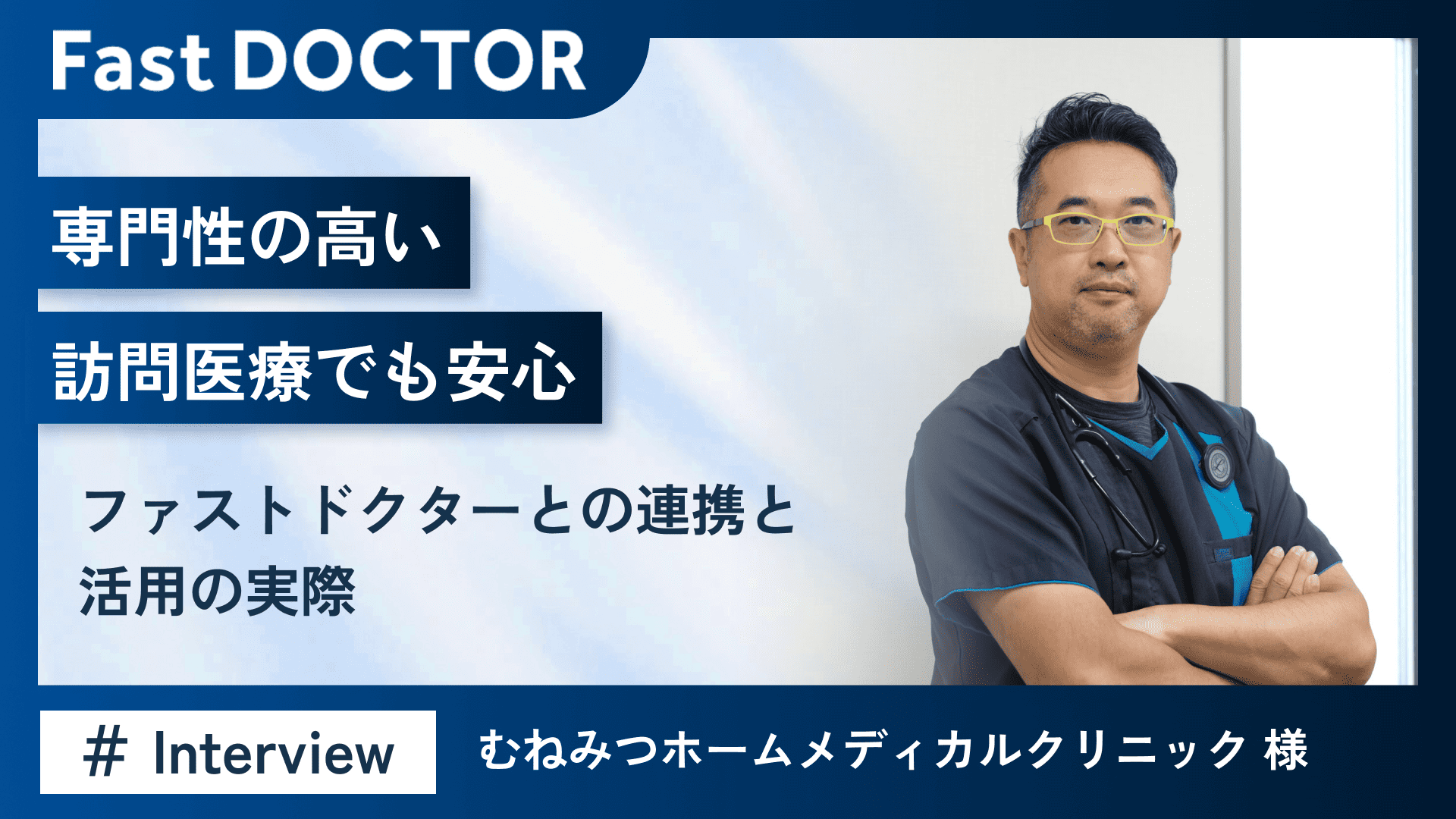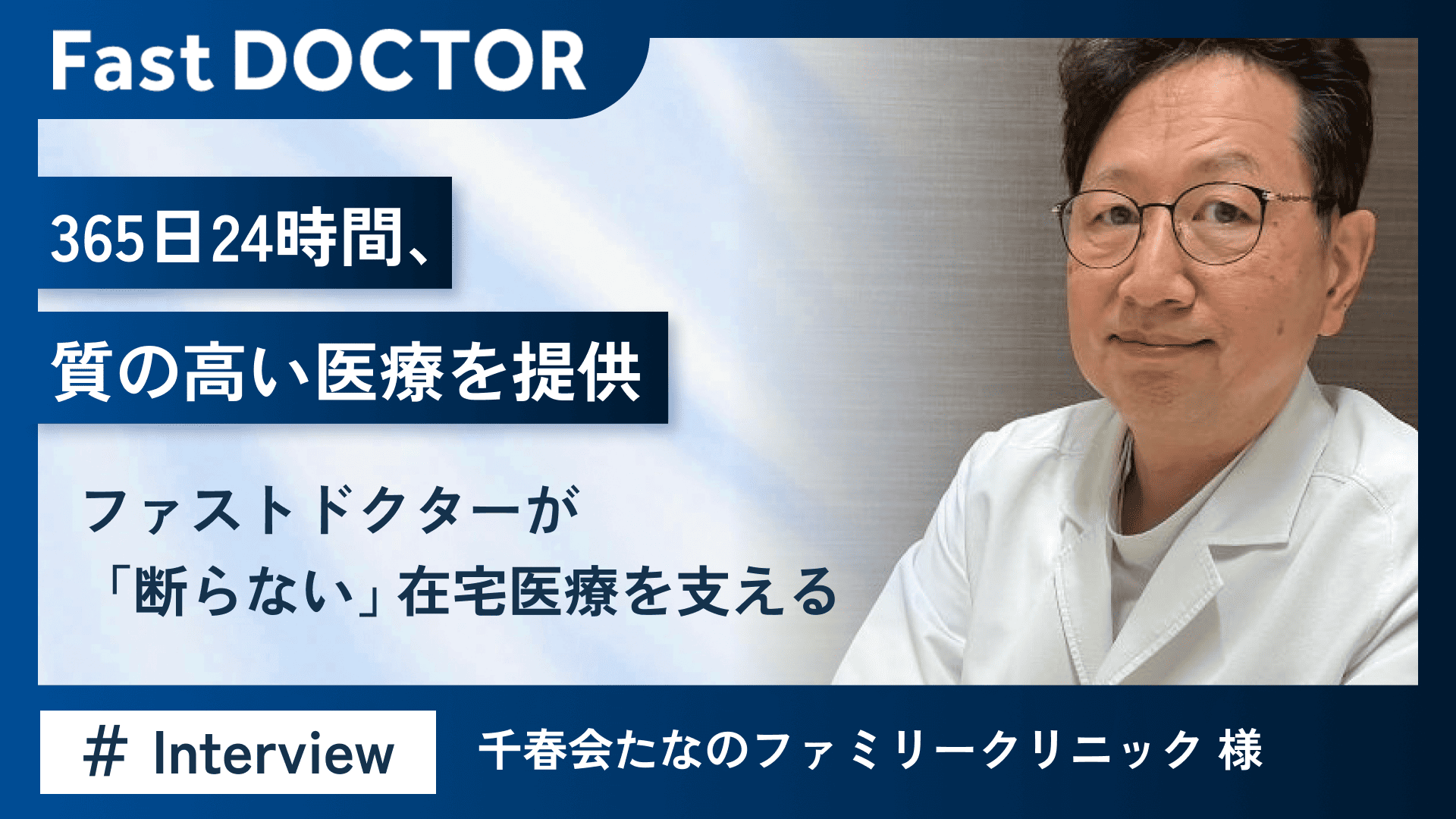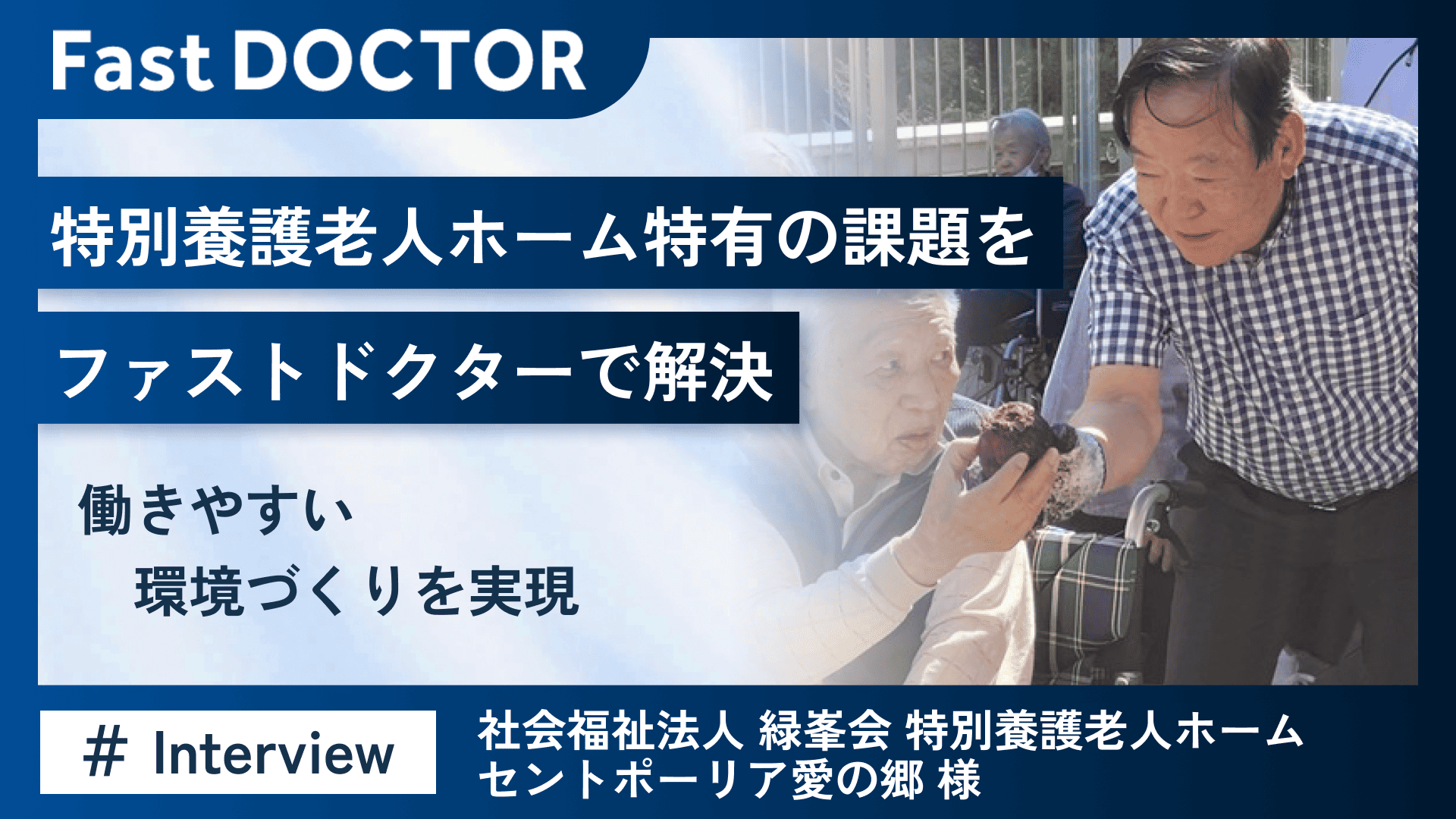神経内科専門医による質の高い在宅医療~ファストドクターの導入で持続可能なクリニック運営へ~
2025.07.27
2025.09.12
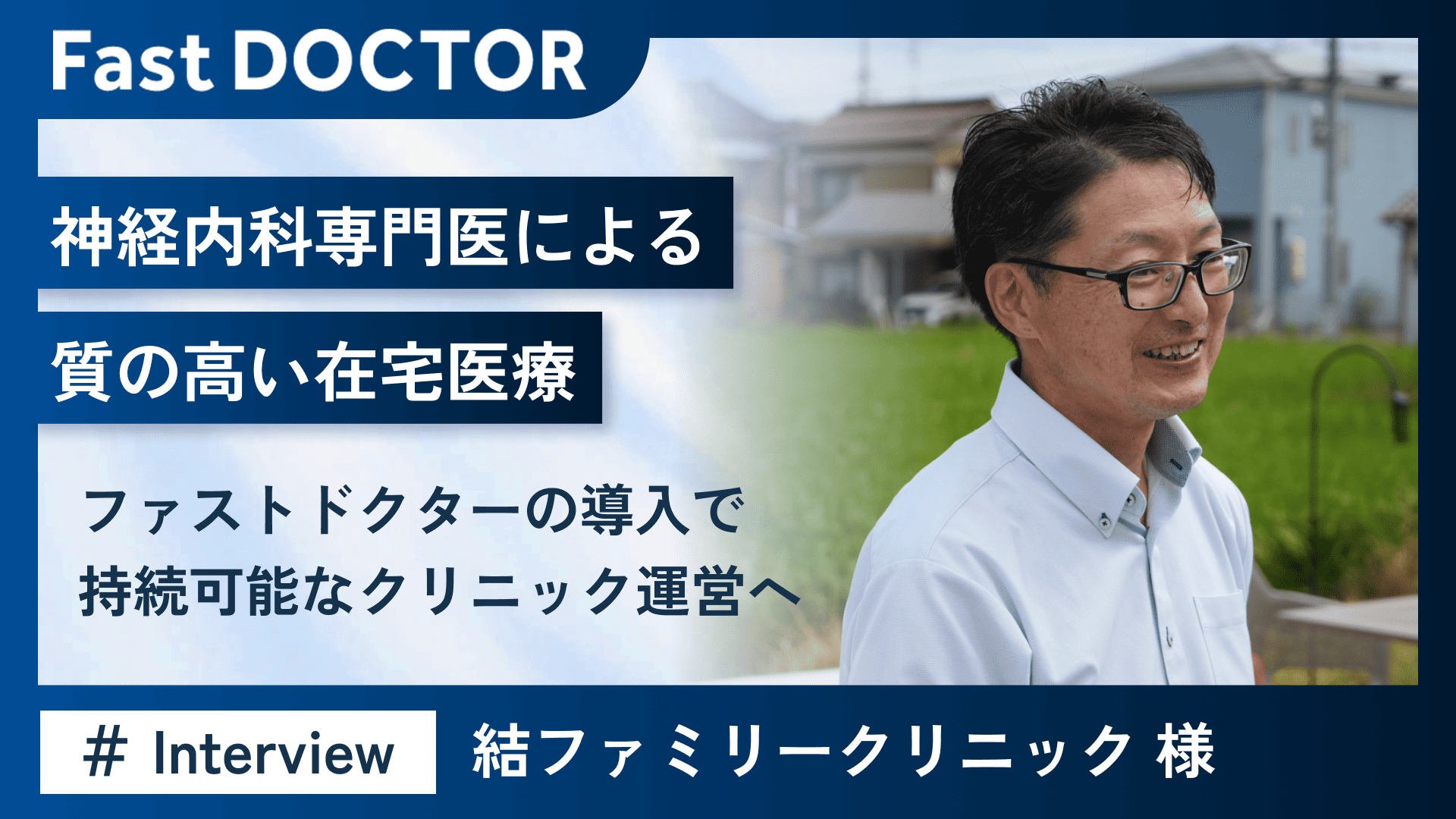

この記事の著者
愛知県犬山市にある「結ファミリークリニック」は、患者一人ひとりの希望に丁寧に寄り添いながら在宅診療を提供しているクリニックです。
院長の鈴木欣宏先生は、神経内科の専門医として、神経難病の専門的な治療にも対応。最新の知見を取り入れながら、質の高い在宅医療の提供に日々尽力しています。
また、同院では、往診に対応できる常勤医師が鈴木院長1人体制のため、土日の往診をメインにファストドクターを導入したそうです。
今回は、鈴木院長に「結ファミリークリニック」の強みや、ファストドクター導入による変化についてお話を伺いました。
連携力を強みに、一人ひとりに寄り添う在宅医療
Q.結ファミリークリニックの強みを教えてください。
鈴木先生:
当院の強みは、神経難病の進行期を専門的に診ている点です。神経難病は、進行すると病状が変化してきます。例えば、パーキンソン病では、外来へ通院できる時期はまだ歩けるためHoen-Yahr分類で1〜3度と軽症であり、運動症状が主症状です。
この時期は普通に動ける時間をできるだけ長くするため、さまざまな抗パーキンソン病薬を調整します。
しかし、在宅医療で診る方は通院することができない方が対象となるため、必然的にHoen-Yahr分類3~5度の重症の方を診ることになります。この時期は抗パーキンソン病薬が効きにくくなるだけでなく、幻覚、嚥下障害、転倒骨折など様々な合併症が出現してきます。
それらをコントロールするには、これまで運動症状の改善のために追加してきた薬剤を必要最低限に減らす一方で、適切な薬剤を追加するという難しい調整が求められます。
さらに内服調整だけでは十分に対応できないため、多職種の連携が必要になります。
幻覚に対しては訪問看護による家族指導、嚥下障害に対しては嚥下訓練できる言語聴覚士や訪問歯科、転倒骨折に対しては理学療法士と福祉用具などと連携しており、その連携をスムーズに進めるためにMedical Care StationというICTを利用し、迅速に情報共有できるようにしています。
また、日本在宅医療連合医学会の専門医を取得し、研修施設となっていることも強みの一つです。在宅医療はまだ歴史の浅い領域のため、つい我流に走ってしまう傾向があると感じています。
専門医を取得して学会に参加することで、標準的な在宅医療を行うことができていると思います。
Q.在宅医療以外に取り組んでいることはありますか?
鈴木先生:
災害対策にも積極的に取り組んでおり、地震だけでなく水害や積雪、火災などあらゆる災害に対応できるようにBCP(事業継続計画)の策定に取り組んでいます。
また、緊急時に対応できるように安否コールというアプリを導入しています。
地域の啓発活動として、保健所や地域の老人会への講演活動も行っています。内容は在宅医療だけでなく、神経難病、人生会議、予防医学など様々なテーマに取り組んでいます。
Q.外来診療も行っているそうですね。
鈴木先生:
はい、月2回ではありますが、外来も行っています。神経難病の患者さんを診られる外来がこの地域には少ないため、まだ訪問診療が必要ではない早期の方の受け皿として、外来診療も行っています。
大切にしている診療の軸は守りつつ、頼れる部分はファストドクターの力を借りる
Q.どのような形でファーストドクターを利用されていますか?
鈴木先生:
当院では、土日の往診をファストドクターに依頼しています。利用し始めてから約2年経過していますが、私自身の休みを確保し、継続できる運営体制の構築を目的として導入しました。
ファーストタッチはまず当院の看護師が電話を取って振り分けをします。当院はACPを大切にしているため、患者さん一人ひとりの価値観によっては、いきなり新しい医師が介入すると混乱される場合があります。
特にがんの方のように急激に症状が進行する場合には、患者さんに信頼されるために時間をかけて話をしているため、それを共有するのは困難です。
また、認知症の方は知らない人が家に入ってくるだけで混乱する場合があります。それを考慮して当院の看護師が振り分けを行います。特に看取りは患者さんとの関係性が何よりも大切なため、これまで依頼したことはありません。
Q.ファストドクターを導入したきっかけについて教えてください。
鈴木先生:
当院は医師が常勤1人のため、負担軽減が不可欠で、代行往診サービスの導入を検討しました。
特に犬山市は愛知県でも端のため、対応してくれるところがありませんでしたが、ファストドクターさんに相談したところ、対応圏外にもかかわらず快く対応してくださいました。
Q.実際に利用してみて、ファストドクターの対応はどうでしたか?
鈴木先生:
ファストドクターの先生方は、皆さんしっかりと対応してくださいますし、事前の情報共有もモバカルという電子カルテで情報共有ができています。
患者さんからも「とても丁寧に対応してくれた」と伺っています。ただ、ファストドクターの先生が他の患者さんへの対応で遅れてしまう場合には、依頼してから診察までの時間がかかってしまうため、その時にはお断りして私が対応しています。
Q.ファストドクターを2年ほど利用されているとのことですが、医師の質に関してはいかがでしょうか。
鈴木先生:
質の高い先生方に対応していただいていると感じます。もちろん、当院では患者さんが大切にしている価値観に基づいて診療を提供しているため、代わりに診察していただくことの難しさはあると思います。
一方で、発熱や腹痛など緊急対応が必要な疾患への対応は、ファストドクターに安心して依頼できています。
持続可能なクリニックを実現するためにファストドクターが貢献
Q.ファストドクターを導入前に抱えていた不安や、導入後の変化を教えてください。
鈴木先生:
1番の不安は、私の知らない医師が患者さんを診ることでした。しかし、実際に導入してみて、今のところ患者さんからの評判は悪くはないので、安心して任せられています。
私に話を聞いてほしいという患者さんの場合には、非常勤の医師だとお断りされることもありますが、全体としては、ファストドクターを導入したことで負担はかなり軽くなりました。
たとえば、休みが取れるようになったので、 体力が回復して、平日の診察に集中できるようになりました。家族との時間を持てるようになったことも、導入してよかった点のひとつです。
Q.今後の目標には、どのようなものがありますか?
鈴木先生:
当院では、今年度の目標に「持続可能」を掲げています。
これは、自分自身が体力的にも無理なく診療を続けていけるようにとの意味も込めていますし、災害が発生した際にもちゃんと継続できるような医療体制を整えておくことの意味を込めたものです。
さらに、スタッフの入れ替えがある場合にも、業務の引き継ぎがスムーズに行えるよう、業務の言語化などにも取り組む必要があると感じています。
単にクリニックの規模を拡大することが目的ではなく、質を維持しながら、スタッフ一人ひとりが負担なく働き続けられる体制を整えていきたいです。その一環として、AIの導入やタスクシフトといった仕組みも、積極的に活用していくつもりです。
医師・クリニックが共存していく時代に向けて
Q.最後に、メッセージをお願いします。
鈴木先生:
これからは、医者やクリニック同士が争う時代ではなく、共生していく時代だと思っています。 お互いに協力しながら、医療の質を高め、同時に現場の負担を減らしていけることが理想です。
そうした新しい形を作っていくことが、在宅医療や診療所などさまざまなところで、今後ますます求められてくるのではないでしょうか。
そのなかで、ファストドクターのような往診代行サービスが、今後の医療にとって欠かせない存在になっていくと感じています。


この記事の著者
関連記事RELATED